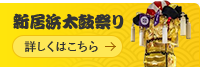サイト内検索
本文
令和6年第5回新居浜市議会定例会会議録 第4号
目次
議事日程
本日の会議に付した事件
出席議員
欠席議員
説明のため出席した者
議会事務局職員出席者
開議(午前10時00分)
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 一般質問 議案第77号~議案第80号
野田明里議員の質問(1)
1 市長の考える新しいにいはまについて
古川市長の答弁
1 市長の考える新しいにいはまについて
野田明里議員の質問(2)
1 市長の考える新しいにいはまについて
古川市長の答弁
1 市長の考える新しいにいはまについて
野田明里議員の質問(3)
1 市長の考える新しいにいはまについて
2 少子高齢化の改善のための子供への取組について
(1) 包括的性教育
高橋教育長の答弁
2 少子高齢化の改善のための子供への取組について
(1) 包括的性教育
沢田福祉部こども局長の答弁
2 少子高齢化の改善のための子供への取組について
(1) 包括的性教育
野田明里議員の質問(4)
2 少子高齢化の改善のための子供への取組について
(1) 包括的性教育
(2) 部活動など成長期の様々な活動
ア 合理的かつ効果効率的な取組
高橋教育長の答弁
2 少子高齢化の改善のための子供への取組について
(2) 部活動など成長期の様々な活動
ア 合理的かつ効果効率的な取組
野田明里議員の質問(5)
2 少子高齢化の改善のための子供への取組について
(2) 部活動など成長期の様々な活動
ア 合理的かつ効果効率的な取組
高橋教育長の答弁
2 少子高齢化の改善のための子供への取組について
(2) 部活動など成長期の様々な活動
ア 合理的かつ効果効率的な取組
野田明里議員の質問(6)
2 少子高齢化の改善のための子供への取組について
(2) 部活動など成長期の様々な活動
イ 活動時間や休養日
高橋教育長の答弁
2 少子高齢化の改善のための子供への取組について
(2) 部活動など成長期の様々な活動
イ 活動時間や休養日
野田明里議員の質問(7)
2 少子高齢化の改善のための子供への取組について
(2) 部活動など成長期の様々な活動
イ 活動時間や休養日
高橋教育長の答弁
2 少子高齢化の改善のための子供への取組について
(2) 部活動など成長期の様々な活動
イ 活動時間や休養日
野田明里議員の質問(8)
2 少子高齢化の改善のための子供への取組について
(2) 部活動など成長期の様々な活動
ウ 活動時間帯や栄養摂取状況
高橋教育長の答弁
2 少子高齢化の改善のための子供への取組について
(2) 部活動など成長期の様々な活動
ウ 活動時間帯や栄養摂取状況
野田明里議員の質問(9)
2 少子高齢化の改善のための子供への取組について
(2) 部活動など成長期の様々な活動
ウ 活動時間帯や栄養摂取状況
エ 指導力向上の取組
高橋教育長の答弁
2 少子高齢化の改善のための子供への取組について
(2) 部活動など成長期の様々な活動
エ 指導力向上の取組
野田明里議員の質問(10)
2 少子高齢化の改善のための子供への取組について
(2) 部活動など成長期の様々な活動
エ 指導力向上の取組
(3) 成長期の行動と社会問題との関連
高橋教育長の答弁
2 少子高齢化の改善のための子供への取組について
(3) 成長期の行動と社会問題との関連
野田明里議員の質問(11)
2 少子高齢化の改善のための子供への取組について
(3) 成長期の行動と社会問題との関連
古川市長の答弁
2 少子高齢化の改善のための子供への取組について
(3) 成長期の行動と社会問題との関連
野田明里議員の質問(12)
2 少子高齢化の改善のための子供への取組について
(3) 成長期の行動と社会問題との関連
休憩(午前10時52分)
再開(午前11時03分)
伊藤謙司議員の質問(1)
1 市民文化センターの建て替えについて
古川市長の答弁
1 市民文化センターの建て替えについて
伊藤謙司議員の質問(2)
1 市民文化センターの建て替えについて
古川市長の答弁
1 市民文化センターの建て替えについて
伊藤謙司議員の質問(3)
1 市民文化センターの建て替えについて
古川市長の答弁
1 市民文化センターの建て替えについて
伊藤謙司議員の質問(4)
1 市民文化センターの建て替えについて
古川市長の答弁
1 市民文化センターの建て替えについて
伊藤謙司議員の質問(5)
1 市民文化センターの建て替えについて
古川市長の答弁
1 市民文化センターの建て替えについて
伊藤謙司議員の質問(6)
1 市民文化センターの建て替えについて
古川市長の答弁
1 市民文化センターの建て替えについて
伊藤謙司議員の質問(7)
1 市民文化センターの建て替えについて
2 コンパクトシティー構築について
原副市長の答弁
2 コンパクトシティー構築について
伊藤謙司議員の質問(8)
2 コンパクトシティー構築について
古川市長の答弁
2 コンパクトシティー構築について
伊藤謙司議員の質問(9)
2 コンパクトシティー構築について
古川市長の答弁
2 コンパクトシティー構築について
伊藤謙司議員の質問(10)
2 コンパクトシティー構築について
3 繁華街の今後について
宮崎経済部長の答弁
3 繁華街の今後について
伊藤謙司議員の質問(11)
3 繁華街の今後について
宮崎経済部長の答弁
3 繁華街の今後について
伊藤謙司議員の質問(12)
3 繁華街の今後について
4 小中学校の統廃合について
高橋教育長の答弁
4 小中学校の統廃合について
伊藤謙司議員の質問(13)
4 小中学校の統廃合について
高橋教育長の答弁
4 小中学校の統廃合について
伊藤謙司議員の質問(14)
4 小中学校の統廃合について
高橋教育長の答弁
4 小中学校の統廃合について
伊藤謙司議員の質問(15)
4 小中学校の統廃合について
5 小中学校のプール施設・授業について
高橋教育長の答弁
5 小中学校のプール施設・授業について
伊藤謙司議員の質問(16)
5 小中学校のプール施設・授業について
高橋教育長の答弁
5 小中学校のプール施設・授業について
伊藤謙司議員の質問(17)
5 小中学校のプール施設・授業について
6 小学生の通学時の荷物について
高橋教育長の答弁
6 小学生の通学時の荷物について
伊藤謙司議員の質問(18)
6 小学生の通学時の荷物について
高橋教育長の答弁
6 小学生の通学時の荷物について
伊藤謙司議員の質問(19)
6 小学生の通学時の荷物について
休憩(午前11時56分)
再開(午後 1時00分)
河内優子議員の質問(1)
1 子育て支援について
(1) 四国で一番の子育て支援
(2) 子ども・子育て支援事業計画
(3) 命名書の発行
(4) 出産・子育て応援給付金
(5) 誰でも通園制度
(6) ギャンブル依存症と児童手当
2 防災・減災対策について
(1) 孤立集落
(2) 感震ブレーカー
(3) 災害時協力井戸登録制度
(4) 災害ケースマネジメント
3 停電時の対応について
4 落雷対策について
5 教育行政について
(1) 不登校支援
(2) 睡眠教育
古川市長の答弁
1 子育て支援について
(1) 四国で一番の子育て支援
(5) 誰でも通園制度
2 防災・減災対策について
(1) 孤立集落
(4) 災害ケースマネジメント
高橋教育長の答弁
4 落雷対策について
5 教育行政について
(1) 不登校支援
(2) 睡眠教育
久枝福祉部長の答弁
1 子育て支援について
(6) ギャンブル依存症と児童手当
後田消防長の答弁
2 防災・減災対策について
(2) 感震ブレーカー
小澤市民環境部危機管理監の答弁
2 防災・減災対策について
(2) 感震ブレーカー
(3) 災害時協力井戸登録制度
3 停電時の対応について
沢田福祉部こども局長の答弁
1 子育て支援について
(2) 子ども・子育て支援事業計画
(3) 命名書の発行
(4) 出産・子育て応援給付金
(6) ギャンブル依存症と児童手当
河内優子議員の質問(2)
2 防災・減災対策について
後田消防長の答弁
2 防災・減災対策について
河内優子議員の質問(3)
5 教育行政について
沢田福祉部こども局長の答弁
5 教育行政について
河内優子議員の質問(4)
委員会付託
休憩(午後 1時58分)
再開(午後 2時08分)
日程第3 報告第25号
古川市長の説明
後田消防長の説明
日程第4 議案第81号、議案第82号
古川市長の説明
髙橋総務部長の説明
委員会付託
日程第5 議案第83号~議案第87号
古川市長の説明
加地企画部長の説明
委員会付託
散会(午後 2時29分)
本文
令和6年12月12日(木曜日)
議事日程 第4号
第1 会議録署名議員の指名
第2 一般質問
議案第77号 令和6年度新居浜市一般会計補正予算(第5号)
(各常任委員会付託)
議案第78号 令和6年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
(市民福祉委員会付託)
議案第79号 令和6年度新居浜市水道事業会計補正予算(第1号)
(経済建設委員会付託)
議案第80号 令和6年度新居浜市公共下水道事業会計補正予算(第1号)
(同上)
第3 報告第25号 専決処分の報告について
第4 議案第81号 新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
(企画教育委員会付託)
議案第82号 新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
(同上)
第5 議案第83号 令和6年度新居浜市一般会計補正予算(第6号)
(同上)
議案第84号 令和6年度新居浜市渡海船事業特別会計補正予算(第1号)
(同上)
議案第85号 令和6年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)
(同上)
議案第86号 令和6年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
(同上)
議案第87号 令和6年度新居浜市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)
(企画教育委員会付託)
――――――――――――――――――――――
本日の会議に付した事件
議事日程のとおり
――――――――――――――――――――――
出席議員(25名)
1番 小野 志保
2番 伊藤 義男
3番 渡辺 高博
4番 野田 明里
5番 加藤 昌延
7番 井谷 幸恵
8番 河内 優子
9番 黒田 真徳
10番 合田 晋一郎
11番 神野 恭多
12番 白川 誉
13番 伊藤 嘉秀
14番 越智 克範
15番 藤田 誠一
16番 田窪 秀道
17番 小野 辰夫
18番 山本 健十郎
19番 高塚 広義
20番 藤原 雅彦
21番 篠原 茂
22番 伊藤 謙司
23番 大條 雅久
24番 伊藤 優子
25番 仙波 憲一
26番 近藤 司
――――――――――――――――――――――
欠席議員(1名)
6番 片平 恵美
――――――――――――――――――――――
説明のため出席した者
市長 古川 拓哉
副市長 原 一之
企画部長 加地 和弘
総務部長 髙橋 聡
福祉部長 久枝 庄三
市民環境部長 長井 秀旗
経済部長 宮崎 司
建設部長 高橋 宣行
消防長 後田 武
上下水道局長 玉井 和彦
教育長 高橋 良光
教育委員会事務局長 竹林 栄一
監査委員 鴻上 浩宣
企画部文化スポーツ局長 守谷 典隆
福祉部こども局長 沢田 友子
市民環境部危機管理監 小澤 昇
――――――――――――――――――――――
議会事務局職員出席者
事務局長 山本 知輝
議事課長 德永 易丈
議事課副課長 鴨田 優子
議事課副課長 岡田 洋志
議事課調査係長 伊藤 博徳
議事課議事係長 村上 佳史
議事課主事 田辺 和之
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前10時00分開議
○議長(小野辰夫) これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程につきましては、議事日程第4号のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(小野辰夫) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において伊藤優子議員及び仙波憲一議員を指名いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第2 一般質問 議案第77号~議案第80号
○議長(小野辰夫) 次に、日程第2、議案第77号から議案第80号までを議題とし、昨日に引き続き一般質問並びに質疑を行います。
順次発言を許します。まず、野田明里議員。
○4番(野田明里)(登壇) おはようございます。
みらい新居浜野田明里です。
議員になって覚えた言葉の一つに、一丁目一番地という言葉があります。一番実現させたい最優先課題のことだそうですね。今回の私の質問は、私にとっての一丁目一番地、最優先課題を超えて、私の活動の根源のようなものです。ですので、今回はいつもと違い少しだけ暑苦しいかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
古川市長が就任されて初の議会ですので、まずは古川市政の一丁目一番地について伺いたいと思います。
それでは、通告に従いまして質問させていただきます。
まずは、市長の考える新しいにいはまについて。
四国で一番の子育て支援を一丁目一番地に掲げていらっしゃいますが、それはなぜでしょうか。
そして、四国で一番の子育て支援とは、具体的にどのような支援をお考えでしょうか。
また、市民はどのような子育て支援を望んでいると感じていらっしゃいますか、お願いいたします。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) おはようございます。
野田議員さんの御質問にお答えいたします。
私の考える新しいにいはまについてでございます。
四国で一番の子育て支援を市政の重要課題の一つとして掲げた理由といたしましては、子育て支援の充実が、新居浜市の将来を担う子供たちの育成と若い世代が安心して暮らせる環境を整えるために必要不可欠であると認識しているからでございます。少子化が進む中、子育てしやすい町としての差別化は、住みたい、住み続けたい、または移り住みたいと思われるまちづくりの基盤になると確信しております。そのことを踏まえ、具体的な支援につきましては、子育て世代が必要な支援をスムーズに受けられる環境を提供するとともに、教育環境の向上を図りたいと考えております。
次に、市民が望む子育て支援についてでございます。
今までに市民の皆様から安心して子育てを支えられる環境整備など、様々な御意見をお伺いしており、これらの声をしっかりと受け止め、具体的な施策につなげたいと考えております。
今後におきましても、様々な立場の市民や団体の声を聞きながら、未来を担う子供たちの笑顔があふれる新居浜市の実現に向け、全力で取り組んでまいります。
○議長(小野辰夫) 野田明里議員。
○4番(野田明里)(登壇) ありがとうございます。私も子育て支援の充実を訴え続けているので、古川市長のお考えは、非常にうれしく思っております。改めまして、市長御就任おめでとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
私の下にも子育て世代の皆さんやお孫さんがいらっしゃる方、若い人を応援したいと思ってくださる方たちからの期待の声がたくさん届いています。
その一方で、子育て支援以外の支援もしてもらえるんだろうか、子育て世代以外は取り残されてしまうのではとの不安の声も聞こえてきております。そのような不安に感じていらっしゃる声は、認識されていますでしょうか。
また、子育て世代ではない方たちの支援は、どのようにされていくのか、お考えをお聞かせください。
これらのこと以外にも力を入れていきたい取組についてもお聞かせください。よろしくお願いいたします。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) 野田議員さんの御質問にお答えをいたします。
子育て支援以外の支援についての不安の声は、私もお伺いをしております。子育て支援の充実とともに、私の公約の柱であります地域経済の活性化、防災能力の強化に取り組んでまいりたいと考えており、誰も取り残さない優しいコミュニティーづくりの実現のため、積極的に現場に足を運び、対話を重ね、市民の多様な声を伺いながら、世代を問わず、市民に寄り添う施策を展開してまいりたいと考えております。
○議長(小野辰夫) 野田明里議員。
○4番(野田明里)(登壇) ありがとうございます。
2月に岡山県奈義町に個人研修にお邪魔しました。奈義町は、人口約5,700人ほどの小さな町ですが、合計特殊出生率が2019年には2.95、2022年に少し減りはしていますが、それでも2.3という少子化とは縁遠い町です。研修の冒頭で、担当の職員さんが、子育て支援は高齢者支援ですとはっきりとおっしゃいました。子供や子育て世代が安定することが何よりの高齢者支援だと。なので、その考えを最初に子育て世代以外の方にしっかりと説明して、納得していただいたそうです。そして、子育て世代ではない方たちに、一番の子育ての応援者になっていただいているそうです。地域で子供を育むとは、まさにこのことだと感じました。子育てしていない方が、いかに子供や子供を育てている人たちに寄り添い、協力し合えるか、そしてそのようにして育てられた子供たちは、きっと地域への愛を育んでいき、いつか自分が大人になったときに上の世代を助け、下の世代を引っ張り上げ、町のためにできることを行っていこうとなるのではないかと感じました。まさに、議会初日に市長がお話しされた優しさあふれ、ぬくもりが感じられる町ではないでしょうか。このようなよい循環をつくり出す第一歩を古川市長にはぜひつくり出していただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
では次に、少子高齢化の改善のための子供への取組について質問いたします。
まずは、包括的性教育について質問いたします。
様々な支援策や対策などが行われても、なお歯止めが利かなくなっている少子化問題。新居浜市でも1人の女性が一生の間に出産する子供の人数を表す合計特殊出生率も、ついこの間まで四国1位だったのが、今回愛媛で3位、四国で6位と一気に下がってしまっているようです。
その反面、若い子供たちの妊娠問題や性被害が深刻化しています。ここ数年、減少傾向が見られていた人工妊娠中絶件数ですが、令和5年度はその傾向が逆転し、再び増加に転じていることが母体保護関連の統計により分かっています。この増加の背景には、特に若年層の中絶件数の増加が関係していると考えられ、20歳未満の中絶件数の増加が顕著です。20歳未満で見ると、特に19歳の中絶件数が最多、次いで18歳と続くようです。また、20歳から24歳及び25歳から29歳の層における中絶件数の増加も目立っています。
このような若年層の妊娠、中絶の背景には、妊娠に対する教育や避妊方法の普及がまだ不十分であること、そのような教育へのアクセスの問題が依然として存在していること、そしてサポート体制の整備の必要性が考えられるそうです。少子化で皆さんが対策を講じられているその傍ら、こうして新しく宿った命、そして自分の心や体を傷つける選択をしている人がいるということ、本当に心が痛みます。
包括的性教育とは、体や生殖の仕組みだけではなく、人間関係や性の多様性、ジェンダー平等、幸福など幅広いテーマを含む教育のことで、まさに子供たちが直面している前述の問題の解決の糸口となり得る取組ではないかと考えられます。
愛媛県の宇和島市では、こころまじわうプロジェクトと呼ばれる包括的性教育によって、性を正しく理解するための取組が2020年度から行われています。それぞれの学年に合ったテーマで、産婦人科医や助産師など、専門家の講話プラス学級担任主導で行われる話合い中心の学級活動が、宇和島市内の全中学校、全学年で行われています。1年生では、思春期の心と体の変化についてなどを保健体育の学習とも関連づけながら、外部講師の講話から科学的に学びます。誤った性情報から抱いていた性へのマイナスイメージが、正確な情報を学ぶ中で、大切なこととして捉えられるようになるそうです。そして、学活では、性的いじめや性暴力についてみんなで話し合うそうです。2年生では、助産師さんから科学的に正確な情報として受精や妊娠、誕生についての講話を聞いた上で、学活では、性への関心が高まるのは当たり前。だけど、自分だけではなく、相手のことも大切にするには、性の行動においても同意が大切だということを考えます。3年生では、産婦人科の先生から避妊や中絶、性感染症など、妊娠、出産に付随するトラブルなどについての講話を聞き、学活では、デートDVについて話し合うそうです。4年前から宇和島の全中学校で始まったこの取組。2021年度からは小学校にも広がっているそうです。講話を聞くだけの講座ではなく、学級担任の先生たちも授業に取り組むことで、先生たちも子供たちと一緒に性について考え、学ぶことができる講座になっているそうで、その結果、下ネタのように面白半分で性のことを話すのではなく、正確な情報を基に、性のことを先生やお友達と話すことは大切なことなんだというように、子供たちの性への意識も変わってきているそうです。性的なことで悩んだときにも、一人で悩まず、誰かに相談してもいいんだと思ってほしい、外部講師も学級担任も関わり、学校ぐるみ、地域ぐるみで取り組むことで、相談できる大人、そして相談できる場所が増えていくことにつながっていきます。
また、性被害に関しても、令和5年3月30日に出された性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針では、性犯罪、性暴力は、被害者の尊厳を踏みにじる行為であり、決して許されない。相手の同意のない性的な行為は、性暴力であるなどの社会認識を社会全体で共有し、取組を強化していくとして、令和5年度から令和7年度まで、さらなる集中強化期間として取り組まれている最中です。加害者がいなければ、被害者は生まれません。幼少期からの包括的性教育に取り組むことが、加害者も被害者もつくらない、幸せな行動選択ができるための性の学びにつながります。
東日本大震災や能登半島地震の際も、性被害に遭われた方、性被害の恐怖におびえながら過ごされていた方が、私たちの想像以上にいらっしゃったと実際に現地にて支援活動をされた方からその現状についてお話を聞かせていただき、報道されていない現実に本当に愕然としたと同時に憤りを感じました。南海トラフ巨大地震への備えが急がれる今、自然災害自体を防ぐことはできませんが、それに伴うこのような被害は防ぐことができます。いいえ、必ず防がなければいけません。防災の観点からも、包括的性教育の必要性をこれまで以上にひしひしと感じております。
このような社会の大きな変化に伴い、子供たち自身の日常も大きく変化し、そのことから、子供たちが学生時代に直面する悩みやトラブルも保護者の学生時代とは大きく変化しています。まずは、ここについて保護者が学ぶこと、今の時代の当たり前を大人が知ることもとても大事なことだと宇和島のこのプロジェクトの中心で活動されている産婦人科の先生から伺いました。この先生たちが、宇和島市以外の小中学校にも出向き、思春期教室を開催されたり、大人に向けての学習会を開催されているほか、お隣の西条市では、保護者から学校に働きかけて、性教育の取組を実現させていたりと、愛媛県内でも広がりを見せている包括的性教育。
そこで、質問です。
新居浜の出生数や合計特殊出生率が下がった要因は、どのように分析されていますか。
それに対して、どのような対策を講じられていますか。
新居浜の若年層の妊娠問題や性被害など、性に関する問題の現状はどのようになっていますか。また、それらの対策として、どのような取組が行われていますか。
現在、新居浜では、子供たちに向けて、どのような性教育や性の啓発が行われていますか。大人に向けた取組は何かありますか。
以上、よろしくお願いいたします。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。高橋教育長。
○教育長(高橋良光)(登壇) 少子高齢化の改善のための子供への取組についてお答えいたします。
包括的性教育についてでございます。
まず、子供たちに向けた啓発につきましては、小中学校において、学習指導要領に基づき、児童生徒の発達段階に応じた性教育を行っております。本市独自の事業として、性教育の基盤となるみんなで子育て地域の絆「いのちの授業」を行っております。この事業の中で、小学校では、誕生学プログラムにより、自尊感情を育み、命の大切さや命のつながりの尊さを学び、中学校では、いのちの授業として、赤ちゃんやその母親と触れ合う機会を提供することにより、赤ちゃんが持つ周りの人たちを幸せにする力を体感してもらうとともに、命や子供を育てていくことの大切さや喜び、また人に対する思いやりの心を学ぶ取組を実施しております。
次に、大人に向けた取組につきましては、いのちの授業を保護者参観日に実施するほか、保健だよりや学校だより等で保護者の方にも学校における性教育の取組を知っていただくことで、啓発にも努めております。
なお、御案内のありました宇和島市でのプロジェクトは、性を正しく理解する上で参考になると考えますことから、先進事例として情報収集に努めてまいりたいと考えております。
○議長(小野辰夫) 沢田福祉部こども局長。
○福祉部こども局長(沢田友子)(登壇) 本市の出生数や合計特殊出生率の低下の要因と対策についてお答えいたします。
本市の出生数や合計特殊出生率の低下につきましては、様々な要因が影響していると考えております。多様な生き方を選択する人が増えていることや、若い世代の経済的な不安定さや出会いの機会の減少、仕事と子育ての両立の難しさ、子育ての孤立感や負担感、子育てや教育に係る費用負担など、社会全体で取り組むべき課題が山積しているのが現状であると分析しております。
これらの対策として、不妊治療に関する助成対象の拡大や子育て相談や一時預かりにも対応できる子育て支援拠点施設の大型ショッピングモール内への設置、こども家庭センターすまいるステーションでの専門的な資格やスキルを持った職員のチーム体制によるサポートなどに取り組んでいるところでございます。
一方で、子ども・子育て支援事業計画策定に向けて、高校生からの意見聴取を行ったところ、子供を育てることが大変そうだとの回答が非常に多く、楽しそうだという回答を大きく上回っておりました。
このことからも、子育て支援制度や将来に向けた人生設計に関わる情報などは、子育て中の世代だけに発信すればよいのではなく、これから大人になる子供たちにも適切に知ってもらうための取組も必要ではないかと考えております。
次に、本市の若年層の妊娠問題や性被害など、性に関する問題の現状についてでございます。
近年、本市の窓口においては、性被害に関する相談実績はありませんが、10代で母子健康手帳を発行する事例もあります。10代の若年妊婦に見られる問題としては、身体的な未熟さから、妊娠、出産すること自体が母体や胎児に大きなリスクとなることで、妊娠中のきめ細かな健康管理が必要であることや妊娠届出時に未婚であるなど、社会的基盤が脆弱であることなどがあります。
それらに対する取組といたしましては、母子健康手帳発行時の保健師等による面談やその後も電話相談や家庭訪問等を行い、妊婦の心身の状態や養育環境を確認し、状況に応じた情報提供や関係機関へのコーディネートにより、安心して出産、子育てできるよう支援しております。
また、予防教育として、市内の高校3年生を対象に独り立ちサポートブックを配布し、妊娠や性感染症などの性に関する正しい知識の普及啓発や市内高校でのプレコンセプションケアに関する出前講座を実施いたしております。
○議長(小野辰夫) 野田明里議員。
○4番(野田明里)(登壇) ありがとうございます。
徳島県阿南市には、DV防止の啓発活動や性教育を行う大変ユニークな団体がいらっしゃいます。パープルシードあなんというその団体。DVのない地域づくりを目指して、自治体と連携を図りながらDVについての意識を高めたり、多くの人に知ってもらうための講演会を行ったり、阿南市内の中学校でデートDV防止セミナーや講演会を行われているのですが、その団体のキャッチフレーズが、男たちの挑戦、そう、中心メンバーが男性、御本人たちの言葉をそのままお借りするとおっちゃんたちなんです。女性の問題と捉えられがちなDVの防止策を、男性目線で考え、みんなの意識、とりわけ男性の意識が変わらなければ、DV、性被害はなくならないとの見解から、男性が加害者とならない地域社会づくりを目指されています。新居浜にもこのパープルシードあなんさんの取組に興味を持ってくださっている男性、おっちゃんたちがいらっしゃいます。先ほどお話ししてくださいました教育、科学的に正しい情報を知るということも大切だと思いますし、男性がもっと取り組めるような、そのような取組も必要かと思います。新居浜市もぜひこのような民間の方、いろいろな取組と連携していただきながら、子供たちに、責任ある大人が、愛を持って正しい情報を教える機会をつくっていただければと思います。
では、次の質問に移ります。
部活動など成長期の様々な活動について質問いたします。
運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン及び文化部活動の在り方に関する総合的なガイドラインが、平成30年にスポーツ庁と文化庁によりそれぞれ策定され、それを基に平成30年6月に愛媛県が運動部活動の在り方に関する方針を策定、新居浜市でも、新居浜市立中学校に係る部活動の方針を平成30年8月に教育委員会が策定され、そのガイドラインに合わせた部活動改革が行われてきたとお聞きしています。さらに、令和4年夏に取りまとめられた部活動の地域移行に関する検討会議の提言を踏まえ、前述のガイドラインを統合した上で全面改定し、新たに学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドラインが令和4年12月、今から2年前に策定され、部活動改革が加速しています。平成30年に策定されたガイドラインでは、部活動の運営上の留意点や体制整備、活動時間や大会の参加について、そして休養日についてなどが定められています。ほかにも熱中症等の事故防止の観点から、活動の中断、延期、中止を含めた適切かつ柔軟な対応を行うことや安全管理の徹底、体罰、ハラスメントの根絶、顧問の指導力の向上など、従来の部活動の教育的な側面に加えて、合理的でかつ効率的、効果的な活動を行うための細かな取決めが示されています。また、新居浜市の方針では、運動部、文化部及び学校が主体となって行うスポーツ・文化活動、駅伝や朝練、全般についての方針とすると明記されています。部活動に関する関心事と言えば、目下地域移行に関してだと思いますが、今回はこのガイドラインを基に質問させていただきます。
まずは、合理的かつ効果効率的な取組についてです。
大変暑さの厳しかった今年の夏休みに、熱中症を予防する目的で、部活動などの活動が中止になったことはありましたか。
また、夏場の活動中に緊急搬送になったことはありましたか。
熱中症を予防する目的で、活動内容を工夫等して行うなどはありましたか。
これらの活動において、体罰やハラスメントなどを含む心身の安全管理は、どのように行われていますか、お聞かせください。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。高橋教育長。
○教育長(高橋良光)(登壇) 部活動など成長期の様々な活動についてお答えいたします。
合理的かつ効果効率的な取組についてでございます。
近年、子供たちの活動場所の気温や暑さ指数から、学校長の判断により、熱中症予防のために活動を中止したことがございました。
また、夏休み期間の活動中における熱中症による救急搬送は1件あり、運ばれた生徒は、病院で点滴処置を受け、回復後帰宅したと報告を受けております。
次に、熱中症予防に向けての取組といたしましては、生徒の活動場所に暑さ指数計測器を設置、教員は携帯型の計測器を常備するほか、活動時間の短縮や場所によっては活動をちゅうちょなく中止することとしております。
また、活動指導中におきましても、顧問等は細かく児童生徒の体調を確認し、可能な範囲で複数の教員で活動に携わっております。
次に、体罰やハラスメントなどを含む心身の安全管理につきましては、日頃から教職員への指導を行っております。また、部活動指導員に対しましては、県教育委員会主催の研修会への参加を義務づけ、適切な指導に努めております。
○議長(小野辰夫) 野田明里議員。
○4番(野田明里)(登壇) 1点お伺いさせてください。
恐らく来年以降も夏休みの暑さはとても厳しくなるものと思われるのですが、来年以降の対策、今年よりさらに強化していくような対策は、部活動において何かありますか。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。高橋教育長。
○教育長(高橋良光)(登壇) 野田議員さんの御質問にお答えをいたします。
暑さが厳しくなる来年以降、どのように取り組んでいくのかということですけれども、現在、取り組んでいることの中で生じた課題を整理しながら、これを基本として、来年も取り組んでいくというところです。
○議長(小野辰夫) 野田明里議員。
○4番(野田明里)(登壇) ありがとうございます。
次に、活動時間や休養日についてです。
1週間に16時間、これは何を意味する数字か御存じでしょうか。実は、1週間に同じトレーニングを行った場合、リスクなくパフォーマンスを向上させられるトレーニング時間のボーダーラインです。同じトレーニング、同じ運動を行う時間が、1週間に16時間まではパフォーマンスは向上します。強くなる、うまくなるということですね。しかし、16時間以上になると、パフォーマンスは向上しないどころかけがのリスクが高まります。練習はやればやるだけ強くなる、うまくなるというわけではないのです。これは、科学的に証明されていて、このあたりの数字を基に部活動のガイドラインが策定されているそうです。練習は、やったらやっただけ強くなる、うまくなると思われている方はまだまだたくさんいらっしゃいますが、そうではなく、練習と休養、栄養のバランスを考え、効率的、効果的にトレーニングを行う必要があるということです。特に、成長期の運動のし過ぎは、大変危険です。私たちは、基礎代謝といって、特に活動をしていなくても、ただ生きているだけでエネルギーを消費しています。目が覚めた状態で寝転がっているだけでも、エネルギーは消費されています。そこから起き上がり、体を動かすと、さらにエネルギーを消費します。成長期には、体を大きくするために、さらにさらに莫大なエネルギーが必要ですが、部活動などの運動をすると、これにかなりのエネルギーが使われるため、成長に回すエネルギーが足りなかったり、中には日常の活動に使用するエネルギーすら枯渇している子供も大変多いそうです。皆さんの学生時代にも、ハードな部活動をしていて、授業中ずっと寝ているお友達はいませんでしたか。あの子たちは、決してサボっているわけではありません。ハードなトレーニングでエネルギーを消費し尽くしているため、起きて授業を受けるエネルギーさえなく、寝ることで消費エネルギーを極力少なくする、言わば生命を維持するための超省エネモードになっているということです。大げさではなくて、本当に命の危機的状況ということなのです。この状態が続けば、疲労骨折などのけがや貧血などの体調不良、メンタルの不調、女の子は月経が止まるなどになってしまいます。今の子供たちは、部活動の後に塾に行っている子がたくさんいらっしゃって、そのため睡眠不足、栄養不足で、少し昔の子供たちよりさらにこのような危機的状況に陥りやすくなっているということが言えます。
そこで、お尋ねいたします。
部活動のガイドラインには、部活動の活動時間は、学期中は長くとも平日は1日2時間程度、週末や長期休業中は1日3時間程度とされていますが、きちんと守られていますか。
また、休養日として、学期中は少なくとも平日1日、週末どちらか1日を休養日に当てる、週末どちらも大会等に参加した場合は、ほかの平日に休養日を振り替える。長期休業中は、週当たり2日以上の休養日を設定し、一定期間の休養期間、オフシーズンを設定するとも定められていますが、このあたりもきちんと守られていますか。
駅伝が大変盛んな新居浜ですが、部活動以外の駅伝のような活動ではどうでしょうか、お願いします。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。高橋教育長。
○教育長(高橋良光)(登壇) 活動時間や休養日についてお答えいたします。
原則として、各校ともスポーツ庁が示されたガイドラインに沿った活動を実施しておりますが、総体や新人戦など大会前には生徒の状況を確認しながら、規定を超える時間の練習を行う場合もございます。その際には、保護者の理解も得て、大会終了後に休養日を確保するようにしており、これは駅伝大会に向けての練習においても、同様の取扱いであると認識しております。
○議長(小野辰夫) 野田明里議員。
○4番(野田明里)(登壇) すみません、1点お伺いいたします。
保護者の理解を得た上で、大会後に休日などを振り替えるということでしたが、保護者の方は、このガイドラインの存在であったり、存在の意義であったりというところは、皆さん知っておられるんでしょうか。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。高橋教育長。
○教育長(高橋良光)(登壇) 野田議員さんの御質問にお答えをします。
各保護者が、このガイドラインについてよく理解しているかということであると思います。
なかなか詳しいところまで理解している方は少ないと思いますけれども、少なくとも活動時間とか、休養日とか、このあたりについては平成29年度ぐらいから行っておりますので、平日は2時間程度、土、日はどちらか1つをお休みにする、週の中にも1日休養日を取ると、このことについては理解されているものと思います。
また、必要があれば、保護者への啓発等について、各学校も丁寧に対応するようにということは申し述べたいと思います。
○議長(小野辰夫) 野田明里議員。
○4番(野田明里)(登壇) ありがとうございます。
すみません、まだもう少しガイドラインについて掘り下げていきます。
次に、活動時間帯や栄養摂取状況についてです。
体内時計によって、身体機能が最大限発揮され、けがのリスクが低いのは、15時から18時とアメリカのテキサス大学の研究で分かっているそうで、オリンピックレコードや世界記録が出るのもこの時間帯だそうです。体が目覚めきっていないときに体を動かすことは、当然体に負担をかけ、けがのリスクも高めることは簡単に想像できます。さらに、夜も寝るのが遅く、睡眠不足、きちんと朝御飯を食べているのかも心配です。消費エネルギーがただでさえ多く、なのに摂取エネルギーがないとなると、もう命は危機中の危機です。効率的、効果的な活動を行うとなると、時間帯や栄養摂取状況も気になります。
そこで、お尋ねいたします。
学期中の部活動や駅伝などの活動時間帯はいつでしょうか。
朝練をされているところはありますか。
朝練と放課後の両方に活動されている場合、活動時間はトータルで2時間以内ときちんと守られていますか。
朝練をされている場合、子供たちは、朝御飯を食べて練習に参加しているのでしょうか。
また、朝練後の栄養補給、補食状況はどのようになっていますか。よろしくお願いいたします。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。高橋教育長。
○教育長(高橋良光)(登壇) 活動時間帯や栄養摂取状況についてお答えいたします。
まず、活動時間帯につきましては、各学校の方針によりますが、始業前と放課後の時間帯となり、両方の時間帯に活動する場合には、先ほど申し上げました練習時間の対応に準じた取扱いを行っております。
次に、栄養摂取状況につきましては、各御家庭での対応になりますが、学校ではきちんと朝食を食べ、練習に臨むことを指導しております。
また、朝練習後の補食につきましても、必要としている生徒は各自でおにぎりを持参している場合もあると伺っております。
○議長(小野辰夫) 野田明里議員。
○4番(野田明里)(登壇) ありがとうございます。朝練であったり、朝練後の補食状況は、年々とても改善されてきているように感じています。これからもそのあたりの改善、ぜひよろしくお願いいたします。
次に、顧問など指導者の指導力向上の取組についてです。
子供たちは、強くなりたい、うまくなりたい、勝ちたいと思えばとことん頑張ります。驚くほどの集中力でオーバートレーニングにもなりやすくなります。しかし、やればやるだけ効果が出るわけではないということ、そして効率よくトレーニングするための科学的な指針もたくさん示されています。体の仕組みを基に打ち出されているこれらのガイドラインの数字と子供の気持ち、そして昨今の変化の激しい自然環境などをきちんと理解して上手に導いていくことが指導者には求められてくると思うのですが、顧問の先生をはじめ、外部コーチなど、チームの指導者にはガイドラインの周知や啓発、教育等をされていますか。
地域移行が進んだ際に、学校関係者ではない方が指導に携わる場合、今後はどうされていきますか、お願いします。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。高橋教育長。
○教育長(高橋良光)(登壇) 指導力向上の取組についてお答えいたします。
教職員には、職員会議や部活動指導者研修を通じてガイドラインを周知徹底しており、外部コーチには、顧問との意思疎通を図り、指導方針に理解をいただいた上で御協力をいただいております。
なお、部活動指導員の方にも研修が義務づけられており、事前にガイドラインを熟知した上で指導に当たっていただいております。
今後、運動部活動の地域移行が進んだ場合には、各種目の公認指導者の資格を有する方に指導に携わっていただくことが理想ではございますが、現状としましては、愛媛県のできるところから、できるものからの方針の下、指導に携わってくださる方には、部活動指導員の方が受けている研修を受講していただくことで、指導力の向上に努めてまいります。
○議長(小野辰夫) 野田明里議員。
○4番(野田明里)(登壇) ありがとうございます。体を動かすだけが練習ではありません。作戦を練る、敵を知る、ルールについての熟知を行う、メンタルの強化、チームワークを高めるなどなどできることは山ほどあります。もちろん休養や栄養も練習のうちです。指導してくださっている指導者の方たち、顧問の先生たち、サポートしている保護者や地域の方たち、施設の管理をされている方、本当にたくさんの方たちに支えられて成り立っているこれらの活動が、携わっている方、そして何よりも子供たちが、頑張ったことが悲しい結果に、けがとか体調の不良、不調、そういうことにつながってしまわないことを本当に願ってやみません。特に、私も子供が部活動を頑張っているときにそうだったんですが、ついつい頑張っているからとやらせてしまうことがありました。保護者の方たちも、子供たちもなんですけど、頑張ったら頑張っただけうまくなる、強くなる、勝ちたい、でもけがしてしまう、しんどくなってしまう、どっちを取ろうかなっていったときに、頑張っているからもっとさせてやりたいなを取ってしまいがちなんだと思いますが、そうではなくて、しっかりと自分の体を大切にすることと強くなることはイコールです。ここが分かれば、けがをしてしまったり、体調が悪くなってしまったり、また本当に女の子の月経が止まってしまうなんていうことがなくなっていくのではないかと思いますので、ぜひ子供、そして保護者への周知をお願いしたいと思います。
また、このガイドラインが策定された経緯や意義などに立ち返ることも地域移行を考える上での何かヒントになるようにも感じますので、ぜひいま一度ガイドラインの意義を携わる方皆さんで考えていただければと思います。
続いて、成長期の行動と社会問題との関連についてです。
私が部活動などについてここまでしつこくしつこく掘り下げて聞いたのには実はわけがありまして、社会問題、特に不妊や高齢者の寝たきりなどと成長期の行動は大変密接につながっています。先ほども成長期の運動のし過ぎ、栄養不足や休養不足がけがのリスクを高め、心身の不調を引き起こし、女の子は月経が止まってしまうなど、命の危機的状況だとお伝えしました。これは、成長期である今現在の体や心に起こる問題です。実は、成長期のエネルギー不足からくる影響は、今現在の体と心だけではなく、数か月後、数年後、はたまた数十年後にも影響を及ぼすことが分かっています。運動のし過ぎを発端としたエネルギー不足だけではなく、行き過ぎたルッキズムや無理なダイエットからくる栄養不足による若年層の極端な痩せが本当に増えています。ある程度の体脂肪を蓄えることで、エストロゲンと呼ばれる女性ホルモンが分泌されるようになるのですが、極端な痩せで体脂肪が蓄えられていないと、このエストロゲンが分泌されなくなってしまいます。エストロゲンは、月経に深く関わるホルモンで、この分泌がなくなると月経が止まってしまう、つまり妊娠しなくなってしまいます。妊娠し、胎児がお母さんの子宮で育つには、エネルギーがたくさん必要ですが、そのお母さんとなる体自体が、生きるためのエネルギーが極端に不足していると、妊娠どころではない、自分が生きるためにエネルギーを使おうと脳が判断し、妊娠しないようにエストロゲンの分泌を止めてしまうのです。これは言い換えると、お母さん自身の体を命の危機から守ろうとしているとも言えます。そして、さらに成長期にエストロゲンが分泌されないと、骨の密度がどんどん低くなっていきます。このような状態が続くと、骨粗鬆症になり、寝たきりになってしまう危険も出てくるのです。
エネルギー不足だけではなく、日焼けを極端に嫌う若い女性も増えており、骨をつくるのに必要なビタミンDが日光に当たらないことで不足することからも骨粗鬆症の危険は高まります。少しでも出生数を増やそうとたくさんの子育て支援を用意し、出産や子育てに関する助成金や制度を整えても、そもそも子供を妊娠、出産できる体ではない女性が本当に増えています。
また、不妊治療の支援や健康寿命の延伸にと大人に向けて様々な取組をされていますが、不妊や健康が阻害されてしまう根っこは、子供の頃に体の奥底に知らない間にそっと芽吹いていることもあります。そして、体に何か問題が起こったときに、それがずっと以前の自分の行動が原因であったかもしれないと気づいても、もうその頃に戻って改善させることは当然できません。
こうして様々な問題の原因が、成長期や若い頃の行動に起因していることが、科学の進歩などでどんどん判明してきた現在、このようなことを知っているということ、成長期の頃に知って行動することが何よりの予防策になります。こう考えると、今行われている少子化対策や健康政策は、起こってしまった問題をしのぐためのもの、対症療法でしかないようにも感じます。根本を改善するために、若年層への啓発や教育が本当に大切になってくるように思うのですが、新居浜市のお考えをお聞かせください。
このような取組は、これまで行われてきましたか。また、今後はどのようにされていきますか、よろしくお願いいたします。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。高橋教育長。
○教育長(高橋良光)(登壇) 成長期の行動と社会問題との関連についてお答えいたします。
若年層への啓発や教育につきましては、中学校学習指導要領の保健分野の目標に、生涯を通じて心身の健康の保持増進を目指し、明るく豊かな生活を営む態度を養うと掲げられており、これまでも、保健の授業等で自他の健康に関心を持つことや、現在だけでなく、生涯を通じて健康の保持増進や回復を目指すことといった実践力の基礎を育てるための教育を行っております。
今後も、子供たちが生涯を通じて心身ともに健康に過ごすことができる社会を目指して、教育活動を進めていきたいと考えております。
○議長(小野辰夫) 再質問はありませんか。野田明里議員。
○4番(野田明里)(登壇) ありがとうございます。本当に、学校教育だけではなくて、社会教育であったりだとか、市役所の中の担当の課で言うと教育委員会だけではなくて、様々な課が関わりながらしていくべき政策だと思うのですが、そのあたりはどうでしょうか。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) 野田議員さんの再質問にお答えをいたします。
議員さんがおっしゃられるとおり、様々な分野に関わってくることであるというふうに思っておりますので、部局を横断して考えていきたいというふうに思っております。
○議長(小野辰夫) 再質問はありませんか。野田明里議員。
○4番(野田明里)(登壇) ありがとうございます。
田畑が、何も育たないほど痩せていることに気づかずに、一生懸命種をまいても何も実りません。何度まいても、何度も失敗します。これに対して、種を支給したり、何も実らなかったときに、補償や補填を行う、そのような支援を続けても結果は何も変わりません。何も実りません。やがて、一生懸命種をまき続けた人は、諦めていきますし、一生懸命支援している人も疲弊していきます。まさに、今の子育て支援や少子化対策のことだとは思いませんか。すべきことは、まず土地を育てること、育むこと、そしてすべき支援は、土地を育てる、育むサポートだと思います。男女平等を目指し、様々な取組を行っても、科学が進歩しても、現時点ではどうしても変えられないことがあります。それは、子供を産むことができるのは、女性だけであるということです。人口が増えない、子供が増えないのなら、働き手として移民をとのやり取りも一般質問初日に行われましたが、海外から日本にそうしてやって来てくださったその方たちも、自分の国ではその国の女性から生まれています。結局、どこかで女性が産まなければ、子供は増えません。このことが、あまりにも埋もれてしまっているように感じてなりません。そして、同時に、男性がいなければ、女性は妊娠することはできないということも埋もれてしまっているように思います。性イコール生、性教育、性別などの性は、つまり生命、生きることです。性教育は、人が生きるための教育です。様々な価値観の中で、いろいろなものを抱えて皆さん生きています。その中でも、女性が産みたい、産もうと前向きに思える世の中に、産みたいと思ったときに授かれる世の中に、そしてそんな女性と同じ目線で男性が歩んでいける、そんな世の中に、そしてそのような人たちをしっかりとサポートできるような町であってほしいと思います。そして、性に対する悲しい思いをする方がいなくなるように、まずはしっかりと町を育て、育む取組をしていただきたい。しかし、これには本当に時間がかかることだと思います。もしかしたら、古川市長の任期4年では成し遂げられないかもしれません。それでも、今始めなければ、私たちは次の世代、子供たちにも同じ思いをさせてしまいます。同じような悲しい思いをする子供は一人もつくりたくない、そのように思います。時間がかかることを、皆さんしっかりと胸にとどめながら、今できることを少しずつ始めていく、これが無駄のない行財政の第一歩、そしてあるようでなかった大きなチャレンジではないでしょうか。時間がかかること、そしてできなかったことをとがめるのではなく、その次の策をみんなで考えていける、そのような私たち大人で、私たち新居浜市でありたいなと思います。そのような新居浜市をどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
○議長(小野辰夫) この際、暫時休憩いたします。
午前10時52分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前11時03分再開
○議長(小野辰夫) 休憩前に引き続き会議を開きます。
伊藤謙司議員。
○22番(伊藤謙司)(登壇) 自民クラブの伊藤謙司です。
通告に従いまして質問をさせていただきます。
古川新市長においては、就任1か月程度と間もない本会議ですので、まだ体制が整っていないところでしょうが、市長選挙での公約についての質問については、御自身の思いを語っていただければと思いますので、よろしくお願いします。
それでは、市民文化センターの建て替えについて質問させていただきます。
この市民文化センター建て替えについては、前年度も質問させていただきましたが、市長も交代されましたので、再度お尋ねさせていただきます。
まず、今回の市長選挙で、古川市長はマニフェストに、市民文化センターの建て替え問題ということを上げられています。昨日も読んだんですが、マニフェストを少し読ませていただきますと、建設費約210億円をかけて文化センターが建設予定です。現在の文センでも利用者が少なく、固定椅子など構造上、避難所として活用できないばかりか、市民ニーズに応えれる多目的な使い方もできません。既にある総合文化施設あかがねミュージアムも、市民の利用が少ない中、新居浜市に本当に必要な施設かどうかの再検討や本市の活性化につながる別事業への転換が必要です、このように書かれています。
内容は、新文化センター施設の必要性を再度問うということですが、もう少しこの問題について議論をさせていただきたいと思います。
現在の文化センターの場所では、集客はできないということですか。それとも、ただ単に現状計画している建物の計画が駄目だということでしょうか。市長のマニフェストから読み取りますと、新文化センターは、建設地、立地も含めて、計画はゼロベースで考えると感じていますが、お考えをお聞かせください。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) 伊藤謙司議員さんの御質問にお答えします。
市民文化センターの建て替えについてでございます。
私は、さきの市長選挙におきまして、本市の課題の一つとして、市民文化センターの建て替えについては、建設費や施設の在り方を含め、再検討する必要があると訴えてまいりました。現在の場所での集客見込みや現状の建物計画につきましては、これまで基本構想や基本計画を策定する中で、市民の皆様や関係者の皆様の御意見をお聞きしながら検討し、積み上げてこられたことは十分認識いたしておりますが、その上で、市民文化センターの建て替えについては、人口減少社会に直面している中での15年後、20年後の新居浜市の姿を想定しながら、立地や建物の規模、機能、財源等も勘案し、総合的に判断してまいりたいと考えております。
○議長(小野辰夫) 伊藤謙司議員。
○22番(伊藤謙司)(登壇) 今、市長の御答弁で、立地も考えるということだったんですけども、ちなみにあそこの場所じゃないところに建てるっていうこともお考えにあるというお話だったんですが、あそこが空き地になった場合の利活用も考えてのそういう御発言なんですかね。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) 伊藤議員さんの御質問にお答えします。
空き地になるかどうかも含めて、総合的に判断をしていきたいというふうに思っております。
○議長(小野辰夫) 伊藤謙司議員。
○22番(伊藤謙司)(登壇) 空き地なんていうのは、もちろん市役所の前ですんで、まさか公園にするわけにもいかんのんで、その辺も考えながらしていただきたい。
それと、もう計画が大分進んでます。耐用年数が残り10年を切っているスケジュールなんですが、これは最終の耐用年数は守っていく、今までにスケジュールがもう組まれているんですが、令和10年から解体工事というスケジュールで入っているんですけども、後ろの完成というところは守られていくっていうスケジュールで行くんですか。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) お答えをいたします。
後ろ、完成年度も含めて、まずはいつまでにこの問題について判断するのかということでありますけれども、今この場で正確にお示しすることはできませんが、市民との対話を深めていく中で、やはり令和9年度が大ホール等ほかの使用目標年数の到達でありますので、それを迎える前にしっかりと判断をしていきたいというふうに思っています。
○議長(小野辰夫) 伊藤謙司議員。
○22番(伊藤謙司)(登壇) ぜひ完成、後ろは合わせながらやっていただきたいのは、これはお願いしておきます。
それと、何かどうもアリーナという言葉が先に先に走っている感じがします。アリーナに関する市長のお考えというのを聞きたいんですが、イメージ的に、松山の県武道館とか松山のコミュニティセンター、ああいう感じのことを思われてアリーナっていうことの発想で出されとんですか。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) お答えをいたします。
私のイメージとしては、やはり市民が多目的に使えるもの、かつ稼働率が上がるものではないかというふうに思っております。ですので、伊藤議員がおっしゃられるように、雰囲気としては、松山の愛媛県の県武道館といったような形で、ある程度1階の椅子が可動式であって、用途に応じて柔軟に対応できる、そんな施設のイメージであります。あとは、やはり防災に対して、緊急時に対応できるものではなければならないということも念頭にあります。
○議長(小野辰夫) 伊藤謙司議員。
○22番(伊藤謙司)(登壇) 確かに、緊急時に使いやすいような広い場所というのは大事だと思います。けど、今松山の市民会館が老朽化して、建て替えしようかなという話になっとると思うんですが、松山でJRの駅前にアリーナを造るというお話をされているのはもちろん市長も御存じやと思うんですけども、何か松山在住の音楽家の方が、アリーナじゃ残響音なんかで音楽として成り立たないよ。できたらアリーナじゃなくてホールをお願いしたいということなんですけども、今新居浜の文化センターは、音がいいというんで結構評判がええそうです。これは市長が思われとるよい音響で楽しもうというような、アリーナじゃなくてホールという考えはないんですかね。文化センターとしては無理なんですかね。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) 確かに、音響という部分では、アリーナでは物足りないと感じる方はいらっしゃるかというふうに思います。ただ、いろんな角度から考えていかなければならないという中で、やはり松山市とは町の規模が違うので、今後の人口の推移ですとか、財政力ということを考えると、ある程度施設を集約化したり多目的化していくということが必要なんではないかということで、なるべく多くの人が使えるような形、また本市の発展につながるものということで、私のイメージとしては、多目的なアリーナというところでございます。
○議長(小野辰夫) 伊藤謙司議員。
○22番(伊藤謙司)(登壇) すみません、昨日の答弁で、気軽にいつでもというお話をされとったと思うんですが、答弁の中にもあったんですけど、保育園の発表会なんかというたら、椅子を並べるとなかなか労力がかかると思うんですよ。逆にいうたら、そんなことも考えたら、利用率が下がっていくんじゃないかなと思うんですが、アーティストのコンサートなんかは松山市にお任せして、どっちかというたら、市民が使う、どうも何か市長のイメージだと、新居浜市外の方のイメージになるんですよね、ホールとして考えると。だから、市内の方を一番に考えていくとなると、やっぱりできたら着座のホールのほうがいいんかなと思うんですけども、その辺利用率の低下も考えて、アリーナでいけるんですか、その辺をお答えしていただけたら。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) お答えいたします。
稼働率に関しては、むしろ高めていく施設というものをイメージしております。今、お話しにもありましたように、例えば幼稚園、保育園の発表会等々でありますが、今園児数もすごく減っておりまして、大ホールでやっていたものを中ホールに変更しようかという話も伺っております。そういった意味では、やはり適正規模というものも考えないといけないと思いますし、例えば椅子に関しましても、これはまた財源や予算との兼ね合いもあるのですが、例えば可動式というものもありますし、随分以前に比べて性能も上がっているということも伺っております。ですので、そのあたりも検討しながら考えていきたいというふうに思います。
○議長(小野辰夫) 伊藤謙司議員。
○22番(伊藤謙司)(登壇) 市長のお考えは、ある程度分かってきたんですけども、近隣にないというんで、西条市なんかは総合文化会館で1,100人、松山市民会館2,000人、県文で2,700人、2,000人ちょっとオーバーぐらいの収容ができるような施設はぜひぜひお願いしたいと思います。
それと、場所のほうも、できればあまり私は変えたくない、あそこの場所でできる限りやっていただくほうが現実的かなと思います。新文化センターの建設見直しは、市長の判断で、また議会の判断も必要なんですけども、もう少し考えながら、あまり慌てず、性急な判断をされないようにしていただきたい。老朽化が進んでますんで、後ろは決めてやっていただくことをお願いして、この問題については終わりたいと思います。
次に行きます。
コンパクトシティー構築について質問させていただきます。
現在の新居浜市を見ますと、コンパクトシティーとは真逆な方向に行っているのではと疑問を持ちます。昔からの名残で、川西、川東、上部西、上部東と4地区に大きく分かれているのは変わらずであります。人口の動向を見ますと、上部地区、特に中萩地区に人口は変わらず多く、現在も新築住宅は上部に多いと思われます。私が物心ついたとき、中学生のときには、中萩中学校は県下で1、2番目のマンモス中学校であったイメージがあります。しかし、もう一世代上の方からお話を聞きますと、中萩地区は急速に大きくなったと聞きます。実際、バブル期には、川西地区などは地価が高騰し、住宅地を購入することが難しく、購入しやすい地価の上部への人口流出が多く見られたのは、私も成人し、住宅販売メーカーにいましたので、目の当たりにしたことは覚えています。今、なぜこのようなことを議論しようと思ったのかと言えば、今後の新居浜市のまちづくりにおいて、町の形態をいま一度考え直すべきではと思い述べさせていただいております。
市内の勤務地を見ますと、住友企業は臨海地区にあり、鉄工団地、また流通倉庫は黒島の工業団地と、現在の住宅の多い地域と住宅増加地域と勤務地が乖離しているのではと思っています。朝晩の通勤時の渋滞問題は、バイパスなどインフラ整備を多岐にわたり行っていますが、あまり改善もされていないようにも思います。今後のインフラ整備の維持経費を考えていきますと、このままの人口形成でいいのかなと疑問に思います。現在、新居浜市内では、川西地区において人口減少が特に進んでいるように思い、空き家、空き地も多数見受けられます。立地適正化計画にも上げられていますが、拡大した市街地のままでは、今後の暮らしやすさが損なわれてしまうおそれもあるとし、コンパクトなまちづくりが必要であるとされています。
そこで、質問させていただきます。
今後の居住地の誘導として、新居浜市行政としてはどのように町をコンパクトにしていくつもりですか。勤務地と居住地の場所の乖離ということは重視されていますか、お尋ねします。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。原副市長。
○副市長(原一之)(登壇) コンパクトシティー構築についてお答えいたします。
まず、居住地の誘導についてでございます。
本市では、新居浜市立地適正化計画を作成し、コンパクトで魅力と活力のあるまちづくりを進めることとしております。立地適正化計画においては、人口減少の中にあっても、一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティーが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域として居住誘導区域を設定しております。居住誘導区域は、人口や土地利用、公共交通の利便性や災害リスクなどを勘案しつつ、医療、福祉、商業等の都市機能が集積した都市拠点となるべき区域である都市機能誘導区域の周辺に定めており、今後も立地適正化計画に即したまちづくりを進め、都市拠点の魅力向上を図ることで、長期的な時間軸の下、緩やかな誘導によるコンパクトシティーの形成を目指してまいりたいと考えております。
次に、勤務地と居住地の場所の乖離についてでございます。
勤務地と居住地が近いことは、通勤にかかる時間が短く、通勤時の交通混雑の解消にもつながるものと考えますが、住居と工業、いわゆる住工の混在は、住環境の悪化が懸念されることから、土地利用に当たっては、居住環境や生活利便性をより重視しており、住居系、商業系、工業系のそれぞれに適した種類に区分して定めることが重要であるというふうに考えております。
○議長(小野辰夫) 伊藤謙司議員。
○22番(伊藤謙司)(登壇) 先ほど副市長のほうから御答弁いただいたんですが、冒頭でお話ししたんですけども、町の拠点というのを川西、川東、上部西、上部東、この4か所に大きく分けて集約していくんか、それとも新居浜市のどこか、よく言われているんですが、駅裏、泉川とか駅前とか、あの辺りに1か所に持っていくんか、それによって大分違うと思うんですけども、4か所の拠点なんか1か所なんか、その辺難しい答弁やと思うんですけども。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――4か所がええんか、1か所がええんか。―――――――お願いします。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) 伊藤議員の御質問にお答えをいたします。
コンパクトシティーという概念ですが、私個人としてはですが、例えば最近新居浜市内の交通網が随分整備されて便利になりつつある部分もあると思います。例えば、道が便利になることで、町の移動時間が短くなったりとかするっていうことも一つ考え方としてはコンパクトに近づくんじゃないかなというふうに思っております。そういったことも含め、将来の人口推計なども勘案しながら、町の中心をどこに持っていくかということは、やはりしっかりと考えていかなければならないというふうに思っています。確かに、現状市内にばらばらに拠点があるような感じがして、すごく難しい部分があると思いますが、やはり新居浜市を一つというイメージで考えていきたい、そのことをお伝えしたいと思います。
○議長(小野辰夫) 伊藤謙司議員。
○22番(伊藤謙司)(登壇) ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
今市長のほうからもお話があったんですけども、1つ提案なんですけども、駅前の区画整理をしたように、自分ちの近くで申し訳ないんですが、昭和通りから北側って、勤務地に近いところなんですけども、元塚から中須賀周辺とか、新田辺りの再建築不可の住宅が多いところ、ああいうところを再開発して、通勤時間とかそういうところの快適なまちづくりなんかというのも、ちょっと大胆な発想で申し訳ないんですけども、こういう大きな発想なんかというのは、もしできるかどうかというのもお聞かせいただきたいなと思います。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) 御質問にお答えいたします。
やはり、私自身も10年後、20年後ぐらいの未来図はしっかりと描いていきたいというふうに思っております。そんな中で、町をどういう形にするのかというのは、これから議会の皆様や職員の皆様と一緒に相談をしながら、そして市民との対話を深めながら考えていきたいと思います。
○議長(小野辰夫) 伊藤謙司議員。
○22番(伊藤謙司)(登壇) ちょっと今のままではコンパクトシティーというのは難しいと思いますので、インフラ整備も限界が来ると思います。ぜひ目指す町はこういうコンパクトシティー、ひいては移住、定住なんかも来ていただける町になると思いますんで、ぜひこの辺は力を入れてやっていただきたいなと思います。
次に行きます。
繁華街の今後について質問させていただきます。
市内の繁華街の中心と言えば敷島通り、若水周辺であると思っております。現に居酒屋、スナック、バーなどの飲食店は、その周辺が新居浜で一番多いのは今も昔も変わっていません。敷島通りや若水辺りには、最近も新しいビルが建設され、新しいテナントが多く入店されています。しかし、その反面、古い雑居ビルも多数あり、耐震にも合致しないビルがあることも現実であります。
そういった現状の中、繁華街の中心、敷島通りにありますABプラザというテナントビルが、現在空きビルとなっています。民間の企業の経営のことですので、行政がどうのこうのということではないと思いますが、あえて議論させていただきます。
やはり、市内繁華街のど真ん中の立地ですので、今後の動向というのは、繁華街の活性化、また発展に関係性が多岐にわたりあると思います。それも、地上5階建ての繁華街随一の大きなテナントビルです。周辺への影響が大きいのは当然であると思います。
そこで、分かる範囲で結構なんですが、現状ABプラザの跡地利用は、何かお話は聞かれていますでしょうか。
また、行政として、繁華街活性化のため、ビルオーナーなど企業にお願いしていること、また繁華街の活性化の施策は何かされていますでしょうか、お答えください。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。宮崎経済部長。
○経済部長(宮崎司)(登壇) 繁華街の今後についてお答えいたします。
まず、ABプラザビルの現状についてでございます。
ABプラザビルにつきましては、老朽化した建物を解体するため、入居者全てが退去したとお伺いしておりますが、詳細等につきましては特に把握していることはございません。
次に、ビル所有者等企業への依頼についてでございます。
繁華街活性化のために、ビル所有者等の企業に、本市から具体的に依頼していることは、現在のところございません。
次に、繁華街の活性化に対する施策についてでございます。
繁華街の活性化に対する施策につきましては、商店街振興組合やこれに準ずる団体が、街路灯やカラー舗装などの共同施設を新設、改修した際に補助する共同施設設置事業、昭和通り商店街や登り道商店街等の通りに面した場所の空き店舗を改装し、出店した際に補助する空き店舗活用事業、初めて創業した方に対し、創業に係る経費の一部を補助する創業促進補助金などの事業を実施しているところでございます。
○議長(小野辰夫) 伊藤謙司議員。
○22番(伊藤謙司)(登壇) 先ほど私が申し上げたんですが、耐震等も含めて、古いビルがたくさんあります。先ほど部長のほうから補助金のお話があったんですが、古いテナントから新しいテナントへの移転費用なんかも補助すると、繁華街の活性化に一役買うと思うんですが、そういう移転費用の補助というのは、今のところないんですかね。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。宮崎経済部長。
○経済部長(宮崎司)(登壇) 伊藤謙司議員さんの御質問にお答えいたします。
古いビルから新しいテナントに移動するための移転費用なんかの補助があるかないかというような御質問だったかと思います。
現状、今新居浜市で設置している補助金の中には、そういった移転費用を見るというような補助金はございません。
○議長(小野辰夫) 伊藤謙司議員。
○22番(伊藤謙司)(登壇) ABを閉めてからほかのテナントに変わるところが結構あったんですが、移転費用は結構かかるんですよね。その辺を見ていただくと、それでお店をやめた方とかも結構いらっしゃるんで、そういうところはぜひ補助なんかをしていただくと助かります。
飲食店にはいろいろな業種の方々、お酒屋さんとかおしぼり屋さん、ガス屋さん、多種多様な業種の方が携わっています。繁華街の発展、維持は、新居浜市の商業の原点でございます。先ほど言いましたけども、行政として密につながっていただきまして、多岐にわたり幅広い支援、先ほど言った移転費用なんかも含めてお願いしたいと思います。これは要望でございます。
次に行きます。
小中学校の統廃合について質問させていただきます。
この件については、前回の一般質問において、藤田誠一議員が質問していますが、再度詳細にお聞きしたいことがありますので、質問させていただきます。
統廃合の計画は、前期15年、後期15年と計画期間を策定しているとお聞きしています。特に、私の地域である北中学校は、統廃合の対象が、前期に新居浜小学校と宮西小学校を統合、北中学校と西中学校を統合し新中学校の設置、後期に新小学校、新中学校及び惣開小学校を統合し、小中一貫校の設置を検討すると前回の議会で答弁されています。なぜ私が統廃合について質問しているかと言うと、宮西小学校と新居浜小学校、どちらが残るのという質問が前回議会の答弁の後、多く聞かれるようになりました。15年スパンで考える中で、現在小学校に通われている保護者にすると、義務教育9年間の間に統廃合が行われるのではという疑問がついて回るのは分かります。15年間で行いますとは言われていますが、急に統廃合が進み、制服や体操服など費用がかかることを懸念する保護者がいることも容易に想像がつきます。また、現在、小中学校の統廃合が検討されているということは、前回の議会答弁を教育長が丁寧にされたことにより、市民に周知されて、逆にそのことにより、変なうわさだったり臆測が出回っているのも現実であります。教育委員会としては、5年ごとの見直しも踏まえ、各校区に説明すると言われていますが、ここまで学校名まで出しているのなら、せめて前期の対象の小中学校には、事前に説明をされてもいいのではと思いますが、いかがでしょうか。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。高橋教育長。
○教育長(高橋良光)(登壇) 小中学校の統廃合についてお答えいたします。
前期計画期間に対象となっている小中学校区への事前説明についてでございます。
現在、教育委員会では、令和5年4月に策定いたしました新居浜市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本計画に基づき、他校よりも小規模化が進んでおります浮島小学校において、校区説明会やアンケート調査を実施しております。年明けより計画期間前期において統合を検討している新居浜小学校、宮西小学校につきましても取組を始める予定といたしております。まずは、校区の学校運営協議会において、小中学校の現状や見込み、適正規模、適正配置の基本的な考え方や進め方など、基本計画について説明し、その後、保護者の方や地域住民の皆様にも、順次説明会を実施してまいります。
今後におきましても、先行して進めている取組を踏まえ、基本計画に沿って進めてまいりますが、基本計画策定時よりも想定以上に少子化が進んでおり、計画の見直しも念頭に取組を進めていくことが必要であると考えております。
教育委員会といたしましては、児童生徒にとってよりよい教育環境を整備し、教育の質のさらなる充実を図るため、保護者の方や地域住民の皆様が混乱することのないよう、丁寧な説明と十分な対話を通じ、共通理解を図りながら、規模適正化、適正配置の取組を進めてまいります。
○議長(小野辰夫) 伊藤謙司議員。
○22番(伊藤謙司)(登壇) 統廃合は、もう15年、前期は決定だと思ってもいいんかなと今御答弁の中で思ったんですが、統廃合した場合のいろんなシミュレーションがあると思います。特に、公民館の統合、廃止などももちろんシミュレーションに入っていると思うんですが、このことについて、公民館ですね、今の時点で事前に相談、説明が本当は必要であると思います。公民館についても、学校の統廃合のタイミングで校区へは同じように説明はされるのでしょうか。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。高橋教育長。
○教育長(高橋良光)(登壇) 伊藤謙司議員さんの御質問にお答えをいたします。
統廃合時、公民館の対応をどうするかということを、説明時にするのかという質問であったかと思いますが、次世代を担う子供たちが、将来にわたってよりよい教育環境で学びを続けることができるよう、望ましい学校の規模の見直し、その学校規模に沿った学校の配置を進める取組をしているところです。
そういうことで、公民館の統廃合については、現在のところ、検討はいたしておりません。
○議長(小野辰夫) 伊藤謙司議員。
○22番(伊藤謙司)(登壇) 教育長、もう一つだけ。
統廃合になると、生徒らの通学時間というのも変わってくると思うんです。そうなった場合、そのタイミングでよく言う校区の線引きというのを変えるとかというようなお考えはありますでしょうか。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。高橋教育長。
○教育長(高橋良光)(登壇) 伊藤謙司議員さんの御質問にお答えします。
統廃合のタイミングで、通学校区の線引きが行われるのかどうかということだったかと思いますけれども、統廃合という方針が決まりましたら、地域の各種団体等から成る協議会というのを立ち上げます。その中で、通学区域の見直し等も含めて、実施の時期や校区における課題などの協議も行ってまいりますので、その協議会の中で、様々な課題については議論していくという、そういう考えでおります。
○議長(小野辰夫) 伊藤謙司議員。
○22番(伊藤謙司)(登壇) 個別の案件で申し訳ないんですけども、新居浜小学校、宮西小学校の統廃合は、若宮小学校と惣開小学校の統廃合とは別次元の話になると思います。変な話、紛糾するのは確実かなと思っております。前回のような統廃合のスケジュールで考えるならば、ぜひリスケジュールをしないといけないかなと思います。学校は、毎年年度初めより早いスケジュールで動きますので、丁寧な説明はもちろん当たり前ですけれども、前倒しの早い段階での時間をかけた説明をお願いしたいと思います。これは要望でお願いします。
次に行きます。
小中学校のプール施設・授業について質問させていただきます。
この小中学校のプールの件については、私は前々から疑問、またそろそろ形態を変えていく案件ではないのかと思っておりましたので議論をさせていただきます。
先般、視察で東京都目黒区教育委員会にお邪魔させていただきました。視察項目として、目黒区立小中学校におけるプール施設整備の考え方を研修させていただきました。私が思っているプール施設、またプール授業というのが、先進地ではどのように議論され、どういった施策、また対策をしているのかが気になり研修をお願いいたしました。結論から申し上げると、プール施設、またプール授業を民間のプール施設を借用し、プールのインストラクターにも協力いただき授業をするといった施策を行っていました。東京都内とは立地条件はかなり違いますが、プール施設、プール授業の課題は、我が市と同じであると痛感しました。まず、プールという屋外の施設ですので、天候に影響される点について、水泳授業を実施する6月、7月、9月は、梅雨時期や台風シーズンと重なり、雨天も多い。また、近年の気候変動により、猛暑やゲリラ豪雨といったことが以前より多くなっているのは皆さん周知のことと思います。これにより、学校に設置されているのは、屋外プールであるため、計画的な授業実施が困難になり、予定されていた授業数確保が困難な点が懸念されるところです。
また、プール授業は、もちろん現在新居浜市内では、各校教員が行っていると思います。プール授業の際には、水泳指導と同時に、安全管理が重視されます。水泳の事故イコール重大な事故につながるのは、簡単に想像がつくところです。
また、水泳授業については、泳力の個人差も大きく、個別指導を行うにしても、学校内では限られた人員しか確保できず、授業としての効果が上がらないと思われます。
今現在、教員、また保護者に水泳授業の内容を聞いてみますと、1、2年生合同授業、また1年生、6年生合同といった変則的な授業形態を取らなければならないなど、教員の人員確保に支障を来すところであると聞いております。
そこで、質問したいのが、新居浜市内の小中学校の現状、プール授業を進めていくに当たり、どういった課題、問題点が挙げられているか、お尋ねします。
その観点から、民間のプール施設を使用して授業を進めていくことは、お考えにありますでしょうか。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。高橋教育長。
○教育長(高橋良光)(登壇) 小中学校のプール施設・授業についてお答えいたします。
本市における小中学校のプール施設に関しましては、老朽化による修繕に多額の費用を要することが大きな課題となっております。
この課題への対応策として、民間のプール施設を活用する方法や近隣の小中学校のプールを利用して授業を実施する方法が考えられますが、児童生徒の移動時間や移動手段、受入先となる施設の利用人数の上限や授業時間数の枠の取扱いなど、解決すべき課題が多くございます。伊藤謙司議員さんから御案内のありました民間のプール施設を活用した授業につきましては、計画的な授業の実施や児童生徒の安全の確保、また専門的な技術指導を受けられるといったメリットがあるものと認識しており、今後進行する少子化問題も考慮しながら、近隣の学校におけるプールとの共同利用と併せまして対応を考えてまいります。
○議長(小野辰夫) 伊藤謙司議員。
○22番(伊藤謙司)(登壇) 民間のプール施設も考えていただけるということなんですけども、もう一つお尋ねしたいのが、授業の疑問もさておきなんですが、プールの維持管理費というのも民間のプールを使用することで大分削減できると思います。最近のプールを建築した事例を見ますと、プールを造ると概算工事が1億2,000万円から2億2,000万円、平均するとプールを造ると2億円ぐらいかかると言われてます。これまた目黒区の教育委員会で聞いたんですが、年間の維持費が1校当たり180万円程度かかると聞いております。新居浜のプールの維持管理費というのは、どれぐらいかかっているんでしょうか。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。高橋教育長。
○教育長(高橋良光)(登壇) 伊藤謙司議員さんの御質問にお答えをいたします。
本市の小中学校におけるプールの維持管理費につきましては、水道料金、施設修繕料、ろ過器点検委託料のほか水質検査手数料、消毒剤など、1校当たり約85万円となっております。
○議長(小野辰夫) 伊藤謙司議員。
○22番(伊藤謙司)(登壇) その維持管理費も85万円と言われとんですが、維持管理費とかまた機能改善のための大規模改修工事を考えると、自校でプールをするよりも、授業の質も上がりますし、たちまち泳げる生徒を増やすんであれば、民間のプールの活用のほうがよいんじゃないかなと思いますので、その辺はまたいろいろと御検討していただけたらなと思います。よろしくお願いします。
それでは、次に行きます。
小学生の通学時の荷物について質問させていただきます。
私には、今年から小学校に入学した孫が新1年生にいます。しかも、双子の男の子です。学校帰りの通学路が、私の会社の前ということがあり、下校時には集団下校の班が3時頃に通ります。新1年生であり、まだまだ体も小さく、ランドセルが歩いている感じです。逆に、高学年は、さすがに体も大きく、ランドセルが似合わない感じすらします。孫たち新1年生は、入学から半年も過ぎ、現在は学校にも慣れ、元気に登下校しています。
しかしながら、今年の猛暑の中、下校する小学生を見て感じたことがあります。まあ荷物の多いこと。特に、週末、金曜日はとてつもない量の荷物を持って帰ってます。そう思い、少し調べさせていただいたことを述べさせていただきます。
資料、パネルの説明をさせていただきます。これです。(パネルを示す)
これは、あるめっちゃ暑い夏の日の入学間もない小学校1年生の下校時の荷物の写真です。民間調査会社が、2022年7月、小学生の子供を持つ保護者を対象に行った通学時の荷物の重さについての調査結果ですが、小学校の授業で使用する教材が増えたり、タブレットが導入されたりと、小学生の通学時のランドセルや荷物が重たくなっている。全国の小学生の子供を持つ保護者666人に聞いたところ、通学時の小学生の荷物の重さは、平均4キロであることが分かった。荷物が重くなった原因として、教材の増加に続いて水筒やタブレットを持っていくようになったことが上げられたそうです。保護者自身が小学生だった頃と比較すると、子供の通学時の荷物が重いと感じますかと聞いたところ、とても感じるが39.2%、少し感じるが33.9%と合わせると73.1%の保護者が今の小学生の荷物のほうが重いと感じていることが分かりました。私も実際に新1年生の荷物量を見て、持ってみて、ここにあるんですが(パネルを示す)、ランドセル、鍵盤ハーモニカ、体操服、手提げ袋2個、水筒、ちょっとびっくりするような荷物でした。真夏の午後3時の下校にこの荷物はさすがにないなと思える重さでした。私のイメージで申し訳ないんですが、タブレットを導入すれば、教科書やドリルが必要なくなり、登下校時の荷物も格段に減るイメージでしたが、実際に調べてみると、教科書はゆとり教育が始まった2002年からすると、約2倍の重量になっていると聞いております。
そこで、お尋ねしますが、教育現場で、小学生の登下校時の荷物の量ということを考えたことはありますでしょうか。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。高橋教育長。
○教育長(高橋良光)(登壇) 小学生の通学時の荷物についてお答えいたします。
教科書の大型化とタブレットの導入などにより、小学生の荷物の重量が増していることから、本市におきましても、文部科学省が平成30年9月に発出しました児童生徒の携行品に係る配慮についてに基づき、登下校時の荷物が、必要以上に重くならない配慮をするよう、各小中学校に周知しております。学校現場では、荷物が重くなりがちな週明け、週末、学期初めに集中しないよう、荷物を分散させたり、学期終わりには懇談会に来られた保護者にお持ち帰りいただくほか、毎日持ち帰る必要のない教科書や文具等につきましては、学校でも保管できるよう、配慮を行っております。
今後におきましても、家庭学習に支障の出ない範囲で、通学時の荷物の負担軽減に努めるよう、重ねて学校を指導してまいります。
○議長(小野辰夫) 再質問はありませんか。伊藤謙司議員。
○22番(伊藤謙司)(登壇) 先ほど文部科学省からの通達があったということで、置き勉という、私も初めて聞いたんですけども、置き勉強道具、略して置き勉と言われているそうなんですけども、新居浜の学校のほうでは、置き勉は認めているんですかね、その辺をちょっとお答えください。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。高橋教育長。
○教育長(高橋良光)(登壇) 伊藤謙司議員さんの再質問にお答えをいたします。
置き勉を認めているかということですが、いわゆる置き勉を認めております。各学校に調査も行っておりますが、それぞれの学校が置いて帰ってよいもの、教材等、細かく決めて、それぞれどの学校、小中学校全てで対応しているという状況を認識しております。
あと細かな点につきましては、それぞれの学校長の裁量の中で工夫ができるものと思っておりますが、全ての小中学校で、全部持ち帰らないといけないということはないということを確認しております。
○議長(小野辰夫) 再質問はありませんか。伊藤謙司議員。
○22番(伊藤謙司)(登壇) 先ほど来、今回のいろんな質問の中でもなんですけども、今は気温も低くなって、何とか子供らも頑張れているんですが、今後は一夏ごとに温暖化していくと。来年の夏までには、児童生徒の荷物の軽減策として、置き勉をもっと進めていって、できたら小学校低学年、1年生は、あれはもう無理なんで、その辺は1年生だけでもように見てあげてください。これは要望でお願いしておきます。
最後になりますが、古川新市長におかれましては、継続・新規事業と様々な施策を進めていかれると思いますが、ぜひ議会や市民へ丁寧な説明をしていただき、よりよいもの、よりよい施策を進めていただくことをお願いして、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
○議長(小野辰夫) この際、暫時休憩いたします。
午前11時56分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午後 1時00分再開
○議長(小野辰夫) 休憩前に引き続き会議を開きます。
河内優子議員。
○8番(河内優子)(登壇) 皆様こんにちは。
公明党議員団の河内優子でございます。
古川市長、市長御就任おめでとうございます。新しい新居浜市に向けて、力強いかじ取りに大きな期待をしています。
それでは、通告に従い質問させていただきます。
初めに、子育て支援について質問させていただきます。
古川市長におかれましては、四国で一番の子育て支援を訴えてこられました。今議会においても、同様の質問がございましたが、改めて四国で一番の子育て支援に向けて、お考えや決意をお聞かせください。
次に、具体的な項目についてお伺いします。
まず、子ども・子育て支援事業計画についてです。
昨年4月にこども家庭庁が発足し、今後中心となって推進していく少子化対策の方向性を示したこども未来戦略に基づき、2024年から3年間で集中的に取り組む加速化プランが決定しました。これは、公明党の子育て応援トータルプランがベースになっています。また、令和5年4月に施行されたこども基本法において、国が定めるこども大綱及び都道府県こども計画を勘案して、市町村こども計画を定めることが努力義務とされました。こども大綱が、少子化社会対策大綱、子供・若者育成支援推進大綱及び子供の貧困対策の推進に関する大綱を一元化したものとなりました。そのため、こども計画につきましても、子供施策に関する事項を一体として策定する必要があると考えます。
新居浜市では、現在、第3期子ども・子育て支援事業計画策定に当たり、就学前及び小学生のお子さんがいる世帯の方を対象に、子ども・子育て支援に関するニーズ調査を実施されていました。この調査により、どのようなニーズがあり、新居浜市の子育て施策の強みと弱み、その対策についてお伺いいたします。
また、計画を策定するに当たり、目指す方向性についてもお考えをお伺いいたします。
次に、命名書の発行についてお伺いします。
お子様の誕生は、御家族にとって最大の幸せであり、かけがえのない記念日となります。この記念すべきお子様の誕生を祝福する方法の一つとして、命名書を発行している自治体がございます。命名書とは、A4ほどの大きさの用紙に、赤ちゃんの名前と生年月日を記載した用紙のことです。出生届を自治体に提出するときに、希望すれば交付されるようです。出生届を受理する新居浜市にとっても、未来を担っていただける新市民の誕生は、大変うれしいことです。お子様の誕生を一緒にお祝いすることにつながり、出生の思い出となると思います。祝福の思いを形として、新居浜市オリジナルの命名書発行についてお考えをお伺いいたします。
次に、出産・子育て応援給付金についてお伺いします。
子育て応援給付金は、2023年1月からスタートし、子育て家庭から大きな喜びの声が届いております。事業開始までの限られた時間での準備のため、物価高騰への影響も考慮し、迅速性を優先し、新居浜市を含め、多くの自治体が現金給付としています。現金給付は、子育て家庭のニーズに合った支援となっていると考えられますが、厚生労働省は、現金給付はオプションとして排除されないが、いずれはクーポン、広域連携など、効率的な給付方法について検討いただきたいと示されていました。この事業は、必要な出産育児関連用品を手にしやすいだけでなく、支援サービスの利用にもつなげることが大きな目的です。新居浜市で様々なサービスが享受できるような仕組みづくりが必要と考えます。他市では、出産・子育て応援カタログギフトや地域通貨などの給付方法にして市内経済に好影響を与えているとお聞きしました。出産・子育て応援給付金事業の意義を踏まえ、現金給付から新居浜市の地域通貨であるあかがねポイントに活用することで、市内経済の活性化の効果が期待できます。
そこで、提案ですが、この給付金をあかがねポイントと現金給付が選択できるようにしてみてはいかがでしょうか。そして、新居浜市で様々なサービスが享受できるよう、さらなる仕組みが必要と考えますが、取組についてお伺いいたします。
また、出産・子育て応援給付金の名称についても、市町村の創意工夫により、親しみの持てる名称の検討を促しています。新居浜市にとって、愛着を持ってもらえる名称への検討をどのようにお考えでしょうか、お伺いいたします。
次に、誰でも通園制度についてお伺いします。
全ての子供、子育て世帯を対象とする支援の拡充で、切れ目なく全ての子育て世帯を支援するために、こども誰でも通園制度の創設がございます。ゼロ歳児から2歳児の約6割を占める未就園児を含み、子育て家庭の多くが、孤立した育児の中で不安や悩みを抱えています。保育所は、共働き家庭であることが入所要件となっており、原則専業主婦家庭は利用できません。しかし、育児で夫や親族の協力が得られずに、母親が孤立してしまう孤育てが深刻な社会問題となっています。母親の鬱病発症や子供への虐待につながる場合もございます。
そこで、全ての子供の育ちを応援し、良質な生育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、就労要件を問わず、柔軟に保育所を利用できるこども誰でも通園制度が創設されます。2025年度に子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業として制度化し、実施自治体の増加を図り、2026年度から全国の自治体において実施できるよう、進めていく予定です。
そこで、本市としてこども誰でも通園制度に今後どのように取り組まれていくのか、お伺いします。
また、課題と対策についてもお伺いいたします。
次に、ギャンブル依存症と児童手当についてお伺いします。
児童手当は、本年10月分から所得制限が撤廃され、支給額の大幅な増加、支給対象を高校生年代までに拡大されるなど、制度改正が実施されています。子育て世代にとっては、大変ありがたい制度になりました。しかし、その児童手当について、市民の方から、夫がギャンブルにのめり込み、児童手当もギャンブルにつぎ込んでしまい、大変困っている。病院に行くよう話をするが、本人に自覚がないため、話合いにならない。増額になることはうれしいが、子供のために使うことができないとお困りの声を聞かせていただきました。児童手当の受け取り口座は、基本的に世帯主になります。しかし、その世帯主が、ギャンブル依存症など何らかの要因により児童手当が本来の目的である子供のために使われず、ギャンブルや借金の返済などの別の用途に使われるという問題が発生しています。国では、2019年4月に、国のギャンブル等依存症対策推進基本計画が策定されました。基本法では、都道府県に対して、地域の実情に即したギャンブル等依存症対策の推進に関する計画を策定するよう努めなければならないとされています。市町村においては、計画策定の努力義務は求められていませんが、幾つかの取組は講じなければならないとされております。児童手当の受給に関しては、昨年5月にこども家庭庁から、受給者が自らの収入や児童手当を専らギャンブル等の児童の生計とは無関係なものに充て、家計や児童養育について省みないような場合には、児童手当Q&A集で示した取扱いを参考にすることとの事務連絡がありました。そして、この事務連絡等を受けて、他市では、ギャンブル依存症の夫が、児童手当を使い込んでしまう場合、実質的に養育している保護者等に受給者を変更できる方針を明確にし、市のホームページで公表しています。その後、幾つかの自治体でも、市ホームページでこの10月の制度改正によって新たに作成されるパンフレットにも記載して周知していく方針が出されて、既に実施している自治体もあります。
そこで、1点目に、新居浜市において、このような取組が必要と考えますが、今後の対策についてお伺いいたします。
ギャンブル依存症は、本人に自覚がないため、医療機関につなぐことができず、御家族の苦労は積もるばかりです。スマホを使えば、24時間いつでも簡単にオンラインギャンブルを興じることができ、ギャンブル利用者の低年齢化も懸念されます。
2点目に、新居浜市は、ギャンブル依存症に関してどのように対応されていますか、お伺いいたします。
社会人になって、職場の上司、先輩、同僚に誘われたことが、ギャンブルを始めたきっかけになったとのお話を伺ったこともあります。
3点目に、ギャンブル依存症に対する社会の健全化、普及啓発を推進する上で、企業内でのセミナーや成人式でのギャンブル依存に対するパンフレットの配布、小中高生に向けてさらなる予防教育の充実が必要と考えますが、新居浜市のお考えをお伺いいたします。
次に、防災・減災対策についてお伺いいたします。
今年元日の能登半島地震に続き、9月20日からの記録的豪雨が、復興半ばの能登半島を襲い、複合災害で被害が拡大しました。亡くなられた皆様に心より哀悼の意を表し、被災された皆様にお見舞いを申し上げます。
能登半島地震では、多くの集落が孤立し、ライフラインが寸断され、住民の方は水や電気がなく、携帯電話もつながらない不安な日々を過ごしたと新聞報道にて掲載されていました。
この教訓を生かして、孤立集落のリスクを減らすため、孤立のおそれがある集落の事前把握と備蓄の必要性が指摘されています。能登半島の各集落は、海や崖に囲まれて、孤立しやすい地形でありました。
そこで、新居浜市において、大きな災害が発生した場合、孤立するリスクのある集落は、何か所と想定されていますか。
また、孤立集落に対してどのように対応されるのか、本市の御所見をお伺いいたします。
輪島市では、孤立状態の集落に物資を届けるドローンの試験飛行が行われ、災害時のドローンの活用について調査したようです。
新居浜市の災害時のドローン活用や計画についてのお考えをお伺いいたします。
次に、感震ブレーカーについてお伺いします。
輪島市で発生した火災は、朝市通り南側の店舗付近が火元とされ、断水の影響で消火が難航し、約240棟が被害を受けました。総務省消防庁の調査では、この火災の原因として、地震後の停電復旧時に発生した通電火災の可能性が指摘されています。輪島市大規模火災を踏まえた消防火災対策のあり方に関する検討会報告書では、今後の対応策の中に、地元消防本部等の体制強化について、震災時の木造密集地域の活動や津波時の浸水想定地域での活動を勘案した計画書の策定が上げられています。
新居浜市では、木造密集市街地や津波想定区域の火災延焼危険性が高い地域は何か所と想定されていますか。
また、どのような計画策定が進められているのか、お伺いいたします。
この報告書では、消防庁次長通知にて、地震時の電気火災リスクを低減するため、感震ブレーカーの普及を積極的に推進することが記載されています。この取組の実効性を高めるために、木造密集市街地や津波浸水想定区域の火災延焼危険性が高い地域にて、感震ブレーカーの普及に向けた計画や普及率の目標値、設置の支援について通知がございました。
新居浜市は、大規模災害時、地震火災死亡リスクは、愛媛県下の20市町で第1位というデータもございます。今年8月に日向灘を震源とする地震により、南海トラフ地震臨時情報が発表されたことは強く記憶に残っております。このことから、地震による通電火災の危険性も、これまでより高まっていると思います。新居浜市は、防災センターに感震ブレーカーを常時展示されており、普及啓発に取り組んでいただいておりますが、まだまだ市民の皆様には、周知普及されていないと思います。
そこで、感震ブレーカーの普及に向けた計画や普及率の目標値、設置支援について本市の取組を含め御所見をお伺いいたします。
厳しい財政状況ではございますが、市民の皆様の命を守るため、高齢者世帯の方や低所得者の世帯に向けて、感震ブレーカー購入の一部補助についてお考えをお伺いいたします。
次に、災害時協力井戸登録制度についてお伺いいたします。
国土交通省では、災害発生時の井戸活用を促進するため、整備に関する留意点や先進事例を盛り込んだ自治体向けの指針を年度内に策定する予定があると伺っています。能登半島地震では、水源確保の代替手段として、井戸が有効に活用されており、防災力向上の一環として、普及を目指しているようです。指針には、設置場所の選定方法や整備手法、利用時のルール、既存の井戸を活用する際の水質検査や所有者との事前調整等を盛り込むようです。具体的に井戸を活用している自治体の中に宇和島市があります。宇和島市では、個人や事業者が所有する井戸を災害応急用井戸として登録し、近隣の方に生活用水が提供できるよう取組が進んでいます。現在631件の井戸が登録されて、市のホームページに掲載されております。また、災害時に井戸の提供者とその井戸を利用する人々が気持ちよく利用できるよう、災害応急用井戸の手引やルールを作成しております。災害応急用井戸の家が分かるよう、提供者のお宅には災害応急用井戸の家というシールが貼られており、自治会長には、自治会内の災害応急用井戸の地図が配られているようです。
そこで、災害時協力井戸登録制度に関する新居浜市のお考えをお伺いいたします。
次に、災害ケースマネジメントについてお伺いいたします。
国は、被災者一人一人に寄り添い、個別の状況に応じて支援をする災害ケースマネジメントを実施する方針を示しています。住宅被害を受けた方には、被災者生活再建支援制度や事業の再生であれば資金繰り支援があります。しかしながら、複合的な困難を抱える方や医療や介護等が必要な方には、これらの支援だけでは生活再建にはつながらないケースもございます。災害ケースマネジメントとは、それぞれの被災者に寄り添い、様々な制度を組み合わせたオーダーメード型の支援となります。東日本大震災の際、仙台市が取組を始めました。被災者世帯一件一件聞き取り調査を実施し、データベースを構築し、生活再建を進めた結果、他の自治体の仮設住宅を撤去する期間が約8年かかったところ、仙台市では5年で全世帯の撤去ができたなどの効果があったようです。
石川県は、1月19日から同意を得て県の公式LINEに登録すると、災害ケースマネジメントにまでつながる仕組みを構築とホームページに掲載されていました。
そこで、国が掲げる災害ケースマネジメントについて、新居浜市ではどのように取り組まれるのか、お伺いいたします。
災害ケースマネジメントの考え方に基づく取組について、平時からの関係機関との連携体制構築に取り組む必要があると思いますが、今後のお考えをお伺いいたします。
次に、停電時の対応についてお伺いいたします。
11月9日20時20分頃、四国の広い範囲で最大36万戸を超える大規模な停電が発生したニュースは、記憶に新しいところでございます。また、今年8月25日、新居浜市と四国中央市では、局所的に激しい豪雨により、最大で約4,800戸が停電しました。午後5時あたりから約180戸で停電が起こり、早期に停電が解消されたところはありましたが、長い時間停電したところでは、翌朝午前中まで停電が続いたそうです。停電のため、水道やエアコンが止まり、この夏の猛暑の折、御自宅が蒸し風呂状態になり、熱中症の危険がある中、ろうそくの明かりを頼りに一夜を過ごした方や冷蔵庫の食材が全部駄目になり廃棄する方等、停電時の対応を考える機会となりました。停電が起きた際には、高齢者の方より、この停電は新居浜市全域なのか、いつ復旧するのかと心配する電話をいただきました。停電により混乱し、不安が高まる可能性が高く、正しい情報発信が必要と思います。
四国電力送配電株式会社では、四国の停電に関する情報発信をLINEアプリにて発信しています。停電が発生した、復旧した、地域登録等を行えば、アプリから情報が発信されます。今治市では、停電情報プッシュ型配信サービスとして、防災危機管理課のホームページに四国電力送配電株式会社の公式LINEアカウントが掲載されています。このような情報発信は、市民の方に大変有益な情報であり、不安を軽減するものと考えます。
新居浜市もこのような情報発信の必要があると考えますが、お考えをお伺いいたします。
次に、落雷対策についてお伺いします。
近年は、地球温暖化の影響を受け、ゲリラ豪雨の増加とともに雷被害も増加しています。雷の増加は、日本の平均気温の上昇が大きく影響し、気温が上昇すると、発達した積乱雲が生じやすくなるため、落雷が増えるようです。
今年4月、宮崎市サッカーグラウンドに雷が落ち、遠征中だった熊本県立鹿本高校の部員18人が病院に搬送され、1人が意識不明の重体となった事故が起こりました。被害に遭われた生徒の方々、学校関係者、御家族の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
落雷事故を受け、熊本県では、学識経験者や医師、学校での事故対応の専門家など、外部の有識者でつくる調査委員会を設置し、落雷事故の原因を調査し、再発防止に努めるようです。子供たちの命に関わる可能性が高い重大な事故として対策を講じる必要があると思います。
そこで、公立小中学校の屋外での教育活動に、落雷事故防止に対してどのように対応されているのか、お伺いいたします。
気象庁では、雷ナウキャスト等のアプリによって情報を発信しています。この雷ナウキャストを部活動主催者及び関係者が情報共有し、雷を含めて安全対策を徹底して取り組んでいく必要があると考えます。このアプリの活用についてお考えをお伺いいたします。
次に、教育行政についてお伺いいたします。
新居浜市では、教職員、不登校等対策教員の方、ハートなんでも相談員やスクールカウンセラーを配置し、児童生徒の皆さんの心に寄り添った手厚い支援を行っていただいております。また、スクールソーシャルワーカー6名の配置には、高い評価をいただいていると認識しています。不登校児童生徒数は増加し、令和5年には347人と平成30年から比較すると2倍に増加しております。特に、低学年児童の増加が懸念されるところです。共働き世帯が増加する中、低学年の児童は、教育支援センターへ自力で通うことが不可能です。保護者の送迎が必要となる点から、学校や地域での受皿を充実させることが必要と考えます。コミュニティ・スクールの機能を生かして、公民館等に不登校傾向の子供たちを受け入れる部屋と人員を確保することで、教員や地域の方の声かけが期待でき、不登校児童生徒も幅広い年齢の方との触れ合いを通して自己が確立できるのではないかと考えます。地域の方が、空いている時間を利用して、地域の子供たちをみんなで育てる意識が醸成されると思います。
そこで、公民館等を活用した不登校児童生徒の居場所づくりについてお考えをお伺いいたします。
次に、不登校の予防策として、睡眠教育の導入についてお伺いします。
スマホやゲーム、学習塾などで就寝時間が遅くなり、原因不明の体調不良や無気力による不登校になる生徒が多いようです。熊本大学の三池名誉教授は、不登校の多い学校と少ない学校の違いは、睡眠時間の差が考えられると分析し、睡眠不足が続くと体内時間が乱れ、自律神経や脳機能の低下、無気力などが生じる。その結果、本来の力を発揮できず、自信喪失や人間関係の悪化など、睡眠不足が不登校に陥る原因を招くことを学び、生活を見直す睡眠教育を推進することを推奨しております。他市では、睡眠の重要性を学ぶ授業や面談などを通して子供の生活習慣の改善を図る睡眠教育を実施し、不登校の改善が図られたようです。教育と医療の連携、教医連携を軸として、幼稚園等では眠育絵本の読み聞かせ、小中学校では睡眠朝食調査やみんいく授業、みんいく面談などを実施しているようです。
そこで、新居浜市の睡眠教育の取組状況と睡眠教育の導入についてお考えをお伺いいたします。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) 河内議員さんの御質問にお答えいたします。
子育て支援についてのうち、四国で一番の子育て支援についてでございます。
四国で一番とは、新居浜に暮らす市民が、実感として自分たちの町に優しさがあり、たくさんのぬくもりを感じられること、それが四国で一番だと言えることだと考えます。
子育て支援とは、子供や子供を現在育てている方たちだけが恩恵を享受することではなく、時代のニーズに合った利用しやすい施設を考えていくこと、道路などのインフラを整えること、町全体に活気がみなぎるようなまちづくりをすること、これらはいずれも子供が真ん中の社会をつくるために必要であると同時に、どの世代の人たちにとっても大切な取組です。
また、オンライン窓口やスマートフォンなどのデジタルツールの活用などにより、実現できるものもあるのではないかと考えております。
今後におきましては、愛媛県の人口減少対策交付金をはじめとする子育て関連の補助金などを積極的に活用し、笑顔あふれる人に優しいまちづくりに取り組んでまいります。
次に、誰でも通園制度についてでございます。
子育て世帯のライフスタイルや働き方が多様化する中、未就園児のいる家庭が抱える様々な悩みやニーズに対応していくため、本市におきましても、令和8年度からの制度の本格実施を見据え、試行的事業の実施を含めた制度の導入を検討してまいりたいと考えております。
次に、課題と対策についてでございます。
本制度の導入に向けましては、需要見込みに応じた受皿の確保、特に保育士をいかに確保していくのかが課題であると考えております。また、他の類似サービスとのすみ分けについても検討する必要がございますことから、関係機関との調整や事業所等の理解を得ながら、ソフト面、ハード面双方の必要量を確保するなど、事業所、利用者、本市が混乱なく円滑に運用できるよう、本格導入に向けた体制整備に努めてまいります。
次に、防災・減災対策についてのうち、孤立集落についてでございます。
愛媛県が平成25年に公表した愛媛県地震被害想定調査では、本市の孤立集落は4か所想定されており、孤立集落の住民に対しましては、自衛隊や消防などのヘリコプターを活用して救援物資の搬送や救助活動などを行うこととしております。
次に、災害時のドローン活用や計画についてでございます。
本市では、消防本部に2機、消防団に1機のドローンを配備しているほか、株式会社セキド及び株式会社サイゼン愛媛支社の2社とドローンに関する協定を締結しており、災害時の孤立集落に対し、救援物資等の運搬や上空からの静止画、動画の撮影について御協力いただくこととなっております。
孤立集落が発生した際には、移動や流通が困難になるほか、断水や停電、長期化による精神的な負担などへの様々な対応が求められますことから、平時より関係機関と連携強化を図るとともに、孤立集落を想定した実効性のある訓練等を行ってまいります。
次に、災害ケースマネジメントについてでございます。
大規模災害発生後、誰も取り残すことなく、早期に被害者の生活再建を図るためには、災害ケースマネジメントの実施が非常に重要であると考えております。
災害ケースマネジメントについての本市独自の明確な取組はございませんが、本年、災害対策本部の各対策班の地震対応についての活動内容を再確認し、改めて職員間で情報共有を図ったところでございます。
また、愛媛県では、災害発生時の要配慮者の災害関連死を防ぎ、生活再建を支援することを目的として、平成30年度から愛媛県災害時要配慮者支援チームを派遣する体制を整えております。
今後におきましては、応急住宅の提供、融資や職業のあっせん等生活の早期再建に向けた官民挙げての取組ができるよう、庁内部局の連携を再確認するとともに、民間組織や団体との協定締結など、広範囲にわたる連携体制を構築し、被災者一人一人に寄り添い、切れ目のない支援ができるよう進めてまいります。
以上、申し上げましたが、他の点につきましては関係理事者からお答えさせていただきます。
○議長(小野辰夫) 高橋教育長。
○教育長(高橋良光)(登壇) 河内議員さんの御質問にお答えいたします。
落雷対策についてでございます。
まず、小中学校の屋外における教育活動中の落雷事故防止の対応についてでございます。
屋外での教育活動中に黒い雲が近づいてきたり、雷の音が聞こえたりした場合などは、速やかに屋外活動を中止し、児童生徒を屋内へ避難させるほか、樹木等から離れるなどの対応を取っております。
次に、雷ナウキャストの活用についてでございます。
気象庁の情報発信アプリ雷ナウキャストは、雷の激しさや雷が発生する可能性を1キロメートル格子単位で解析し、1時間後までを予測できる有効なアプリであると認識しております。
現在、部活動を行う際は、様々な自然現象から生徒を守るために、熱中症対策として暑さ指数WBGTを計測するセンサーや雷チェッカーなどを活用しておりますが、雷ナウキャストも含め、各種サイトからも適切な気象情報の収集に努め、生徒を自然災害から守り、部活動の安全対策に取り組むよう、主催者及び指導者に徹底を図ってまいります。
次に、教育行政についてお答えいたします。
まず、不登校支援についてでございます。
本市では、市内全ての小中学校がコミュニティ・スクールを導入しており、学校と家庭と地域が一体となり、学校や地域を取り巻く課題解決のため、それぞれの校区において特色のある取組を行っております。
公民館等を活用した不登校児童生徒の居場所づくりにつきましては、不登校の子供たちも利用できるよう、公民館の一室を平日と土曜日の昼間に開放している校区もあり、子供たちが安心して自分の時間を過ごし、リフレッシュできる場所となっております。
また、不登校対策として、スクノマの会では、学習に不安のある児童生徒への学習支援や体験活動を通じて、児童生徒の自立をサポートいただいております。
今後におきましても、市内全校区の学校運営協議会関係者で組織し、年2回開催するコミュニティ・スクール推進協議会において、各校区の特色ある取組の情報共有を図り、あすなろ教室とも連携しながら、不登校対策や子供の居場所づくりに関する取組が各校区へと広がっていくよう、働きかけてまいります。
次に、睡眠教育についてでございます。
睡眠教育に関する本市の取組といたしましては、庁内関係課が連携して設置いたしております健康づくり推進本部の活動の中で、睡眠不足は、日中の眠気や疲労に加え、心身の不調や学業の低下等多岐にわたり影響を及ぼすことを念頭に、睡眠習慣の改善指導に取り組んでおります。
去る11月15日には、愛媛大学大学院医学系研究科の河邉准教授を迎え、子供の眠りとデジタルメディアの関係と題し、眠育を含めたゲーム・スマホ世代の子供との向き合い方について講演をいただいたところです。
小中学生にとって、睡眠は心身の健康のために大変重要であり、睡眠時間の確保や生活リズムを整えることは、集中力の維持や情緒の安定、また不登校の未然防止にもつながると考えられます。
学校では、健康教育の中で眠育に積極的に取り組んでおりますが、家庭での教育、指導が非常に大きな役割を果たしますことから、今後におきましても、保護者の方に対して啓発を行うことで、子供たちの健康教育としての眠育を進めてまいりたいと考えております。
○議長(小野辰夫) 久枝福祉部長。
○福祉部長(久枝庄三)(登壇) 子育て支援についてのうち、ギャンブル依存症と児童手当についてお答えいたします。
まず、本市のギャンブル依存症に関する対応についてでございます。
本市では、ギャンブル等の依存症も含め、心の悩みや不安を抱えている人を対象に、保健師や専門家による健康や心の相談を実施し、必要に応じて医療機関を紹介するなどの支援を行っております。特に、依存症や多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等の問題がある場合は、より専門的な支援を要するため、愛媛県心と体の健康センターの紹介や保健師等による継続的な相談支援を行っております。
次に、企業内でのセミナーや成人式でのギャンブル依存に対するパンフレットの配布、小中高校生に向けての予防教育の充実についてでございます。
本市では、気づいてくださいこころのSOSと題し、企業職員のメンタルヘルス等に関する出前講座を実施いたしております。また、市内の小学校では、家庭科の消費生活の授業で、物や金銭の大切さと計画的な使い方について、中学校では、金銭の管理と購入に関することや自立した消費者としての責任ある消費行動について学んでいるほか、中学1年生を対象にこころのサポートブックを、高校3年生を対象に独り立ちサポートブックを配布し、高額課金等のインターネットトラブルやSNSの不適切な利用、ゲーム依存による健康への悪影響等を掲載し、対策や相談窓口の周知啓発を行っております。
今後もあらゆる機会を通じ、ギャンブル依存症等の予防について啓発を図ってまいります。
○議長(小野辰夫) 後田消防長。
○消防長(後田武)(登壇) 防災・減災対策についてのうち、感震ブレーカーについてお答えいたします。
まず、木造密集市街地や津波想定区域の火災延焼危険性が高い地域は、何か所想定されているかにつきましては、市内の木造密集地区は、延焼拡大する危険性が高い11か所を指定しております。
また、津波想定区域の計画につきましては、策定に至っておりませんが、現在、総務省消防庁において、津波時の浸水想定区域での活動を勘案した消防活動計画等に関する意見聴取会を開催し、検討が進められているところでございます。今後は、その結果を踏まえた国の動向に注視してまいりたいと考えております。
次に、計画書策定につきましては、木造密集地区を対象として、出動車両の選定、利用可能な水利、火災防ぎょ戦術、消防団との連携等について計画するとともに、定期的に現地調査を行い、それぞれの特性を考慮した警防体制の充実、強化を図っております。
○議長(小野辰夫) 小澤市民環境部危機管理監。
○市民環境部危機管理監(小澤昇)(登壇) 防災・減災対策についてのうち、感震ブレーカーについてお答えをいたします。
まず、感震ブレーカーの普及につきましては、新居浜市地域防災計画において、火災予防運動等のあらゆる機会を捉えて普及啓発を行うこととしております。
また、消防庁から令和6年度中に感震ブレーカーの取組を推進するためのモデル計画が通知されることとなっておりますことから、国の計画に基づき、今後本市の計画策定を進めてまいります。
普及率の目標値につきましては、国が平成27年に延焼のおそれのある密集市街地における普及率25%を目指すこととしておりますが、令和4年9月時点で全国の設置率が5.2%となっており、本市も含め、普及は進んでいないものと考えております。
現在、普及啓発の取組として、防災センターに実物を展示し、震災時の出火防止の有効な対策の一つであること等を来館者等に周知しておりますが、今後はチラシなどを活用して、さらなる周知を図ってまいります。
次に、感震ブレーカーの設置に対する一部補助につきましては、一部の自治体が補助制度を導入しておりますが、高齢者世帯や低所得世帯に限らず、通電火災による延焼の防止には、木造住宅密集地などにおける面的な設置が効果的であるとともに、夜間に地震が発生した際には、避難のために照明の確保が必要などのデメリットもございます。このため、現在は導入の予定はございませんが、他市の状況や今年の能登半島地震での通電火災の状況を受けての国の動向等も注視しつつ、調査を進めてまいります。
なお、通電火災の発生を防止することは重要でありますことから、地震発生後、避難所等へ避難する際にはブレーカーを落として避難することを引き続き周知してまいります。
次に、災害時協力井戸登録制度についてでございます。
災害時に飲料用以外の洗濯やトイレ等に使用する生活用水として、個人や事業者の井戸を活用することは有効な手段であると認識をしております。
登録制度におきましては、井戸所有者からの同意を得ることが必要でありますことから、まずは災害時に断水が起きた場合には、住民の方々に井戸を開放し、生活用水の提供に協力していただくことができるよう、呼びかけを行ってまいります。
次に、停電時の対応についてでございます。
近年、気候変動や異常気象により停電の発生する頻度が多くなっております。停電は、自然災害と同様に、いつ発生し、いつ復旧するのか分かりません。先行きの見えない停電は、生活に支障を来すのみならず、誰しも不安に感じるものであります。
河内議員さん御案内の四国電力送配電株式会社のLINE公式アカウントにつきましては、停電に関する情報について市民の皆さんが正しい情報を確認することができるものと考えられますことから、本市のホームページにも掲載し、広く普及を進めてまいります。
○議長(小野辰夫) 沢田福祉部こども局長。
○福祉部こども局長(沢田友子)(登壇) 子育て支援についてお答えいたします。
まず、子ども・子育て支援事業計画についてでございます。
ニーズ調査につきましては、市内の未就学児の保護者1,500人、小学生の保護者500人の計2,000人を無作為に抽出し、令和6年7月に実施いたしました。そのうち、未就学児の保護者738人、小学生の保護者233人からの回答がございました。
どのようなニーズがあったかにつきましては、子供の遊び場、特に雨の日に過ごせる場所についてのニーズが高く、制度や各種手当、子育てに関する情報を知りたいという回答も多くありました。
次に、本市の子育て施策の強みといたしましては、県内でも早い段階で高校生の医療の無償化を実施するなど、医療にかかりやすく、安心して子育てできることであると考えております。
一方、弱みといたしましては、ニーズ調査において地域子育て支援拠点等の子育て支援施設の利用希望が、実際の利用者に比べて低くなっており、子育て施設で実施している内容等の情報が、市民の皆様に十分に届いていないことがうかがえます。また、地域との交流がない保護者は、子育てに不安を覚える割合が多いとの結果でございました。
これらの課題の対策として、こども家庭センターや地域子育て支援拠点施設等の充実を図り、情報発信の取組強化だけでなく、地域で孤立する家庭が気軽に悩みを共有できる環境の整備に取り組む必要があると考えております。
また、次期計画の目指す方向性についてでございますが、第2期計画の点検、評価結果やニーズ調査から課題が確認できたことから、本計画の基本理念であります子どもがまんなか家庭と地域を笑顔でつなぎみんなが育つあかがねのまちの施策を継承し、近年の法改正やこども未来戦略などで示された事業など、新規施策の掲載を検討し、より一層の子育て支援の充実を図ってまいります。
次に、命名書の発行についてでございます。
出生届を提出された御家族に対し、本市からの祝福と思い出を形に残していただく趣旨として、新居浜らしさを表現した命名書の発行について、導入市町の事例等を参考にしながら、調査研究を行ってまいりたいと考えております。
次に、出産・子育て応援給付金についてでございます。
あかがねポイントと現金給付の選択制についてでございますが、昨年愛媛県においてカタログギフト方式での広域連携システムの構築が検討されましたが、現金給付を希望する市町が多く、見送られたという経緯がございました。
また、妊娠届出時面談と赤ちゃん訪問時に、申請や御案内をしておりますが、現金での給付が大変助かるとのお声が多いという現状もございますことから、本事業においては、現金給付を継続したいと考えております。
一方で、地域通貨を利用することで、地域全体で妊娠や出産、子育てを支えていくという社会機運を高めることにもつながりますことから、今後地域通貨の活用についても選択肢の一つとして考えてまいります。
また、本市で様々なサービスが享受できるようなさらなる仕組みづくりにつきましては、給付と伴走型相談支援事業を効果的に組み合わせて行うことにより、妊産婦や配偶者の個々の状態に応じた支援サービスの利用の促進や案内のほか、子育て支援につながる地域資源の情報提供などに取り組むことで、妊娠、出産期の心身の負担の軽減を図りたいと考えております。
次に、新居浜市にとって愛着を持ってもらえる名称の検討については、出産・子育て応援給付金は、子ども・子育て支援法の改正により、令和7年4月から制度化され、妊婦のための支援給付に名称が変更される予定でございます。妊婦やその配偶者に対し、切れ目のない包括的な相談支援事業と効果的に組み合わせて行うこととされておりますことから、まずはこの事業の浸透を図った上で、親しみがあり、分かりやすい愛称について考えてまいります。
次に、ギャンブル依存症と児童手当についてでございます。
河内議員さん御指摘のとおり、児童手当の受給者にギャンブル等の依存症があり、受給者が養育要件を満たしていないことが明らかであるときは、受給者が変更できる場合があります。
本市においては、受給者変更に関する個別の相談の中で対応を行ってまいりましたが、今後御家族のギャンブル依存等でお困りの方の目に留まりやすいよう、市のホームページに掲載するなどの周知を行ってまいります。
以上で答弁を終わります。
○議長(小野辰夫) 再質問はありませんか。河内優子議員。
○8番(河内優子)(登壇) 丁寧な答弁ありがとうございます。
感震ブレーカーについて質問させていただきます。
総務省消防庁から感震ブレーカーの普及に関して言及がございましたが、消防本部として普及に向けたさらなる取組をお伺いします。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。後田消防長。
○消防長(後田武)(登壇) 河内議員さんの再質問にお答えいたします。
感震ブレーカーの普及啓発についてでございます。
大規模地震発生時における火災の発生を抑制するためにも、感震ブレーカーの設置促進は大変重要であると考えます。
今後におきましては、市政だよりやホームページを活用した広報に加え、SNS等を積極的に活用し、さらなる普及啓発に努めてまいります。
○議長(小野辰夫) 再質問はありませんか。河内優子議員。
○8番(河内優子)(登壇) 不登校支援について、こども家庭庁では、不登校対策の新規事業を今年度計画しているようです。こども局として、不登校支援についてどのような取組が考えられますでしょうか、お願いいたします。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。沢田福祉部こども局長。
○福祉部こども局長(沢田友子)(登壇) 河内議員さんの再質問にお答えいたします。
現在、こども家庭センターでは、市内の各小中高等学校を定期的に訪問し、不登校を含めた課題を抱えている子供や家庭についての情報共有を行っており、学校やスクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー等と役割を分担し、その家庭とつながり、適切な支援につながることができるよう取り組んでいるところでございます。
国においては、令和7年度にモデル事業を実施するというふうなことでございますので、このモデル事業における好事例も参考にしてまいりたいと考えております。
○議長(小野辰夫) 再質問はありませんか。河内優子議員。
○8番(河内優子)(登壇) 丁寧な答弁ありがとうございました。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
○議長(小野辰夫) これにて一般質問並びに議案第77号から議案第80号までに対する質疑を終結いたします。
議案第77号から議案第80号までの4件は、いずれも議事日程に記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
この際、暫時休憩いたします。
午後 1時58分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午後 2時08分再開
○議長(小野辰夫) 休憩前に引き続き会議を開きます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第3 報告第25号
○議長(小野辰夫) 次に、日程第3、報告第25号を議題といたします。
説明を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) ただいま上程されました報告第25号につきまして御説明申し上げます。
報告第25号、専決処分の報告につきましては、損害賠償の額の決定についてでございまして、消防ポンプ自動車の交通事故に係る損害賠償の額を15万500円と決定し、専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
なお、詳細につきましては補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(小野辰夫) 補足説明を求めます。後田消防長。
○消防長(後田武)(登壇) 報告第25号、専決処分の報告につきまして補足を申し上げます。
議案書の3ページ及び4ページを御覧ください。
本件は、損害賠償の額の決定についてでございまして、令和6年11月10日午前9時35分頃、市道三軒屋南通り線、篠場町504番2地先路上において、南進していた角野分団消防ポンプ自動車が、右折しようと交差点に進入したところ、車両が東進してきており、その進行を妨げないよう後進した際、後方で停車中の相手方の軽自動車に接触し、車両を損傷させた交通事故に係る損害賠償の額の決定について、令和6年12月5日専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
損害賠償の額につきましては、当事者との協議及びえひめ未来農業協同組合の査定によりまして、相手方車両の修理に要する費用15万500円と決定いたしたものでございます。
なお、損害賠償の額につきましては、全額JA共済から支払われる予定となっております。
日頃から消防職、団員に対して、交通事故防止について注意喚起をしているところではございますが、安全運転については、さらに指導の徹底を図ってまいります。
以上で補足を終わります。
○議長(小野辰夫) これより質疑に入ります。
報告第25号に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小野辰夫) 質疑なしと認めます。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第4 議案第81号、議案第82号
○議長(小野辰夫) 次に、日程第4、議案第81号及び議案第82号の2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) ただいま上程されました議案第81号及び議案第82号につきまして提案理由の説明を申し上げます。
まず、議案第81号、新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定につきましては、人事院勧告等を勘案し、議会議員、特別職の職員及び教育長の期末手当の支給割合を改めるため、本案を提出いたしました。
次に、議案第82号、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定につきましては、一般職の職員等について、人事院勧告等を勘案して、給料等の改定を行うとともに、所要の条文整備を行うため、本案を提出いたしました。
なお、詳細につきましては担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(小野辰夫) 補足説明を求めます。髙橋総務部長。
○総務部長(髙橋聡)(登壇) 議案第81号及び議案第82号につきまして補足を申し上げます。
まず、議案第81号、新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案書の5ページから7ページまでを御覧ください。
なお、新旧対照表につきましては、参考資料の2ページから4ページまでに掲載しております。
本議案は、議会議員並びに市長、副市長、監査委員及び教育長につきまして、いずれも人事院勧告等を勘案して、令和6年12月に支給する期末手当の支給割合を0.05月分引き上げることとし、令和7年6月以降に支給する期末手当の支給割合を6月と12月で平準化しようとするものでございます。
次に、議案第82号、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定につきまして補足を申し上げます。
議案書の8ページから15ページまでを御覧ください。
なお、新旧対照表につきましては、参考資料の5ページから17ページまでに掲載しております。
まず、第1条、新居浜市職員の給与に関する条例の一部改正についてでございます。
令和6年12月に支給する期末手当の支給割合及び勤勉手当の支給限度額の算出割合を、定年前再任用短時間勤務職員について0.025月分を、それ以外の職員について0.05月分をそれぞれ引き上げようとするものでございます。
次に、別表第1、行政職給料表の改正につきましては、民間給与との較差を埋めるため、若年層に重点を置き、給料月額を3,300円から2万6,300円の範囲で増額改定し、令和6年4月1日から適用しようとするものでございます。
次に、第2条、同じく新居浜市職員の給与に関する条例の一部改正についてでございます。
令和7年6月以降に支給する期末手当の支給割合及び勤勉手当の支給限度額の算出割合を6月と12月で平準化しようとするものでございます。
次に、第3条及び第4条、新居浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正についてでございます。
いずれも特定任期付職員に支給する給料月額及び期末手当の支給割合を、国家公務員の給与改定に準じて改めようとするものでございます。
次に、第5条及び第6条、新居浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正についてでございます。
新居浜市職員の給与に関する条例を準用する規定を一部改め、会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規定を整備するとともに、令和7年6月以降に支給する期末手当の支給割合を0.025月分、勤勉手当の支給限度額の算出割合を0.0125月分それぞれ引き上げようとするものでございます。
以上のほか、附則におきまして、改正前の条例の規定に基づき支給された給与を改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす経過措置等を規定しております。
議案第81号及び議案第82号の改正について、要約し、対比等をいたしましたものが、参考資料の18ページから20ページまでにございますので、お目通しをお願いいたします。
以上で補足を終わります。
○議長(小野辰夫) これより質疑に入ります。
議案第81号及び議案第82号の2件に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小野辰夫) 質疑なしと認めます。
議案第81号及び議案第82号の2件は、いずれも議事日程に記載のとおり、企画教育委員会に付託いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第5 議案第83号~議案第87号
○議長(小野辰夫) 次に、日程第5、議案第83号から議案第87号までの5件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) ただいま上程されました議案第83号から議案第87号までの5件につきまして一括して提案理由の説明を申し上げます。
議案第83号、令和6年度新居浜市一般会計補正予算(第6号)、議案第84号、令和6年度新居浜市渡海船事業特別会計補正予算(第1号)、議案第85号、令和6年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)、議案第86号、令和6年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)及び議案第87号、令和6年度新居浜市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、いずれも給与改定及び人事異動に伴う人件費につきまして予算措置いたすものでございます。
なお、詳細につきましては担当部長から補足説明をいたします。御審議よろしくお願い申し上げます。
○議長(小野辰夫) 補足説明を求めます。加地企画部長。
○企画部長(加地和弘)(登壇) 議案第83号から議案第87号までの予算議案につきまして一括して補足を申し上げます。
まず、議案第83号、令和6年度新居浜市一般会計補正予算(第6号)についてでございます。
補正予算書の3ページを御覧ください。
今回の補正予算は、7億4,357万7,000円を追加し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ562億5,456万円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと、2,223万1,000円、0.1%の減となっております。
4ページを御覧ください。
第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入といたしまして、第19款繰入金7億4,357万7,000円を追加し、5ページ、6ページの歳出をそれぞれ追加、減額いたすものでございます。
次に、歳出についてでございます。
人事院勧告による給与改定及び人事異動に伴う人件費について、23ページの議会費247万1,000円の減額のほか、24ページから30ページまでの総務費6億4,840万1,000円の追加、30ページから35ページまでの民生費936万1,000円の追加、35ページから37ページまでの衛生費1,403万1,000円の減額、38ページから41ページまでの農林水産業費1,563万8,000円の減額、41ページから42ページまでの商工費664万1,000円の減額、42ページから46ページまでの土木費246万4,000円の追加、46ページから47ページまでの消防費2,962万2,000円の追加、47ページから51ページまでの教育費9,374万2,000円の追加、その他30ページの民生費、国民健康保険事業特別会計繰出金381万4,000円の追加、31ページの民生費、介護保険事業特別会計繰出金653万9,000円の減額、32ページの民生費、後期高齢者医療事業特別会計繰出金13万5,000円の追加、43ページの土木費、渡海船事業特別会計繰出金135万8,000円の追加、合計7億4,357万7,000円を追加いたすものでございます。
次に、特別会計補正予算についてでございます。
7ページを御覧ください。
議案第84号、令和6年度新居浜市渡海船事業特別会計補正予算(第1号)についてでございます。
今回の補正予算は、人事院勧告による給与改定及び人事異動に伴う人件費について、135万8,000円を追加し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ1億8,915万7,000円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと、153万3,000円、0.8%の増となっております。
内容につきましては、8ページを御覧ください。
歳入につきましては、第5款繰入金135万8,000円を追加し、9ページの歳出に充当いたすものでございます。
次に、10ページを御覧ください。
議案第85号、令和6年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)についてでございます。
今回の補正予算は、人事院勧告による給与改定及び人事異動に伴う人件費について、381万4,000円を追加し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ118億5,655万9,000円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと、4億5,250万9,000円、3.7%の減となっております。
内容につきましては、11ページを御覧ください。
歳入につきましては、第4款繰入金381万4,000円を追加し、12ページの歳出に充当いたすものでございます。
次に、13ページを御覧ください。
議案第86号、令和6年度新居浜市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)についてでございます。
今回の補正予算は、人事院勧告による給与改定及び人事異動に伴う人件費について、457万円を減額し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ142億2,819万6,000円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと、2億1,886万4,000円、1.5%の減となっております。
内容につきましては、14ページを御覧ください。
歳入につきましては、第1款保険料56万2,000円、第3款国庫支出金93万8,000円、第5款県支出金46万9,000円を追加するとともに、第6款繰入金653万9,000円を減額いたしております。
次に、15ページを御覧ください。
歳出につきましては、第1款総務費700万8,000円を減額し、第4款地域支援事業費243万8,000円を追加いたしております。
次に、16ページを御覧ください。
議案第87号、令和6年度新居浜市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)についてでございます。
今回の補正予算は、人事院勧告による給与改定及び人事異動に伴う人件費について、13万5,000円を追加し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ23億3,445万4,000円といたすものでございます。これを前年度同期と比較いたしますと、3億6,820万7,000円、18.7%の増となっております。
内容につきましては、17ページを御覧ください。
歳入につきましては、第3款繰入金13万5,000円を追加し、18ページの歳出に充当いたすものでございます。
以上で補足を終わります。
○議長(小野辰夫) これより質疑に入ります。
議案第83号から議案第87号までの5件に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小野辰夫) 質疑なしと認めます。
議案第83号から議案第87号までの5件は、いずれも議事日程に記載のとおり、企画教育委員会に付託いたします。
以上で本日の日程は全部終了いたしました。
お諮りいたします。議事の都合により、12月13日から12月18日までの6日間、休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(小野辰夫) 御異議なしと認めます。よって、12月13日から12月18日までの6日間、休会することに決しました。
12月19日は午前10時から会議を開きます。
本日はこれにて散会いたします。
午後 2時29分散会