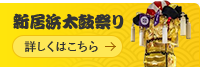サイト内検索
本文
令和6年第5回新居浜市議会定例会会議録 第3号
目次
議事日程
本日の会議に付した事件
出席議員
欠席議員
説明のため出席した者
議会事務局職員出席者
開議(午前10時00分)
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 一般質問 議案第77号~議案第80号
小野志保議員の質問(1)
1 夜間中学について
2 動物愛護について
(1) 飼い主のいない猫の不妊去勢手術補助事業
古川市長の答弁
2 動物愛護について
(1) 飼い主のいない猫の不妊去勢手術補助事業
高橋教育長の答弁
1 夜間中学について
小野志保議員の質問(2)
1 夜間中学について
高橋教育長の答弁
1 夜間中学について
小野志保議員の質問(3)
1 夜間中学について
古川市長の答弁
1 夜間中学について
小野志保議員の質問(4)
1 夜間中学について
2 動物愛護について
渡辺高博議員の質問(1)
1 MaaSシティのこれからについて
古川市長の答弁
1 MaaSシティのこれからについて
渡辺高博議員の質問(2)
1 MaaSシティのこれからについて
2 仮称にいはま文化スポーツクラブについて
古川市長の答弁
2 仮称にいはま文化スポーツクラブについて
渡辺高博議員の質問(3)
2 仮称にいはま文化スポーツクラブについて
3 多目的アリーナについて
古川市長の答弁
3 多目的アリーナについて
渡辺高博議員の質問(4)
3 多目的アリーナについて
4 企業版ふるさと納税について
古川市長の答弁
4 企業版ふるさと納税について
渡辺高博議員の質問(5)
4 企業版ふるさと納税について
休憩(午前10時54分)
再開(午前11時05分)
片平恵美議員の質問(1)
1 学校給食の無償化について
(1) 市長の思い
(2) 実現への課題と手だて
古川市長の答弁
1 学校給食の無償化について
(1) 市長の思い
(2) 実現への課題と手だて
片平恵美議員の質問(2)
1 学校給食の無償化について
古川市長の答弁
1 学校給食の無償化について
片平恵美議員の質問(3)
1 学校給食の無償化について
2 職員の配置について
髙橋総務部長の答弁
2 職員の配置について
片平恵美議員の質問(4)
2 職員の配置について
髙橋総務部長の答弁
2 職員の配置について
片平恵美議員の質問(5)
2 職員の配置について
髙橋総務部長の答弁
2 職員の配置について
片平恵美議員の質問(6)
2 職員の配置について
髙橋総務部長の答弁
2 職員の配置について
片平恵美議員の質問(7)
2 職員の配置について
髙橋総務部長の答弁
2 職員の配置について
片平恵美議員の質問(8)
2 職員の配置について
髙橋総務部長の答弁
2 職員の配置について
片平恵美議員の質問(9)
2 職員の配置について
井谷幸恵議員の質問(1)
1 次期ごみ処理施設の整備方針について
(1) 本市単独での整備
(2) 2市広域化
(3) 公民連携処理
近藤市民環境部環境エネルギー局長の答弁
1 次期ごみ処理施設の整備方針について
(1) 本市単独での整備
(2) 2市広域化
(3) 公民連携処理
井谷幸恵議員の質問(2)
1 次期ごみ処理施設の整備方針について
近藤市民環境部環境エネルギー局長の答弁
1 次期ごみ処理施設の整備方針について
井谷幸恵議員の質問(3)
1 次期ごみ処理施設の整備方針について
2 教育現場の願いについて
(1) 長時間労働の是正
(2) 特別支援教育に携わる先生の増員
高橋教育長の答弁
2 教育現場の願いについて
(1) 長時間労働の是正
(2) 特別支援教育に携わる先生の増員
井谷幸恵議員の質問(4)
2 教育現場の願いについて
高橋教育長の答弁
2 教育現場の願いについて
井谷幸恵議員の質問(5)
2 教育現場の願いについて
休憩(午前11時57分)
再開(午後 1時00分)
髙橋総務部長の発言
神野恭多議員の質問(1)
1 アーティスト石村嘉成氏について
古川市長の答弁
1 アーティスト石村嘉成氏について
神野恭多議員の質問(2)
1 アーティスト石村嘉成氏について
2 運転免許証新規交付窓口の誘致について
加地企画部長の答弁
2 運転免許証新規交付窓口の誘致について
神野恭多議員の質問(3)
2 運転免許証新規交付窓口の誘致について
白川誉議員の質問(1)
1 投票率の低下と原因分析について
藤田選挙管理委員会事務局長の答弁
1 投票率の低下と原因分析について
白川誉議員の質問(2)
1 投票率の低下と原因分析について
2 市長選挙における公約について
(1) 財政再建
古川市長の答弁
2 市長選挙における公約について
(1) 財政再建
白川誉議員の質問(3)
2 市長選挙における公約について
(1) 財政再建
古川市長の答弁
2 市長選挙における公約について
(1) 財政再建
白川誉議員の質問(4)
2 市長選挙における公約について
(1) 財政再建
古川市長の答弁
2 市長選挙における公約について
(1) 財政再建
白川誉議員の質問(5)
2 市長選挙における公約について
(1) 財政再建
(2) 子育て支援
古川市長の答弁
2 市長選挙における公約について
(2) 子育て支援
白川誉議員の質問(6)
2 市長選挙における公約について
(2) 子育て支援
古川市長の答弁
2 市長選挙における公約について
(2) 子育て支援
白川誉議員の質問(7)
2 市長選挙における公約について
(2) 子育て支援
古川市長の答弁
2 市長選挙における公約について
(2) 子育て支援
白川誉議員の質問(8)
2 市長選挙における公約について
(2) 子育て支援
古川市長の答弁
2 市長選挙における公約について
(2) 子育て支援
白川誉議員の質問(9)
2 市長選挙における公約について
(3) 地域経済の活性化とふるさと納税
古川市長の答弁
2 市長選挙における公約について
(3) 地域経済の活性化とふるさと納税
休憩(午後 1時56分)
再開(午後 2時05分)
白川誉議員の質問(10)
2 市長選挙における公約について
(3) 地域経済の活性化とふるさと納税
古川市長の答弁
2 市長選挙における公約について
(3) 地域経済の活性化とふるさと納税
白川誉議員の質問(11)
2 市長選挙における公約について
(3) 地域経済の活性化とふるさと納税
3 ワクリエ新居浜について
加地企画部長の答弁
3 ワクリエ新居浜について
小澤市民環境部危機管理監の答弁
3 ワクリエ新居浜について
白川誉議員の質問(12)
3 ワクリエ新居浜について
散会(午後 2時20分)
本文
令和6年12月11日(水曜日)
議事日程 第3号
第1 会議録署名議員の指名
第2 一般質問
議案第77号 令和6年度新居浜市一般会計補正予算(第5号)
議案第78号 令和6年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
議案第79号 令和6年度新居浜市水道事業会計補正予算(第1号)
議案第80号 令和6年度新居浜市公共下水道事業会計補正予算(第1号)
――――――――――――――――――――――
本日の会議に付した事件
議事日程のとおり
――――――――――――――――――――――
出席議員(26名)
1番 小野 志保
2番 伊藤 義男
3番 渡辺 高博
4番 野田 明里
5番 加藤 昌延
6番 片平 恵美
7番 井谷 幸恵
8番 河内 優子
9番 黒田 真徳
10番 合田 晋一郎
11番 神野 恭多
12番 白川 誉
13番 伊藤 嘉秀
14番 越智 克範
15番 藤田 誠一
16番 田窪 秀道
17番 小野 辰夫
18番 山本 健十郎
19番 高塚 広義
20番 藤原 雅彦
21番 篠原 茂
22番 伊藤 謙司
23番 大條 雅久
24番 伊藤 優子
25番 仙波 憲一
26番 近藤 司
――――――――――――――――――――――
欠席議員
なし
――――――――――――――――――――――
説明のため出席した者
市長 古川 拓哉
副市長 原 一之
企画部長 加地 和弘
総務部長 髙橋 聡
福祉部長 久枝 庄三
市民環境部長 長井 秀旗
経済部長 宮崎 司
建設部長 高橋 宣行
消防長 後田 武
上下水道局長 玉井 和彦
教育長 高橋 良光
教育委員会事務局長 竹林 栄一
監査委員 鴻上 浩宣
選挙管理委員会事務局長 藤田 和久
企画部文化スポーツ局長 守谷 典隆
福祉部こども局長 沢田 友子
市民環境部環境エネルギー局長 近藤 淳司
市民環境部危機管理監 小澤 昇
――――――――――――――――――――――
議会事務局職員出席者
事務局長 山本 知輝
議事課長 德永 易丈
議事課副課長 鴨田 優子
議事課副課長 岡田 洋志
議事課調査係長 伊藤 博徳
議事課議事係長 村上 佳史
議事課主事 田辺 和之
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前10時00分開議
○議長(小野辰夫) これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程につきましては、議事日程第3号のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(小野辰夫) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において伊藤謙司議員及び大條雅久議員を指名いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第2 一般質問 議案第77号~議案第80号
○議長(小野辰夫) 次に、日程第2、議案第77号から議案第80号までを議題とし、昨日に引き続き一般質問並びに質疑を行います。
順次発言を許します。まず、小野志保議員。
○1番(小野志保)(登壇) おはようございます。
立憲民主党の小野志保です。
古川拓哉市長、市長御就任おめでとうございます。笑顔あふれる人に優しいまちづくり、新しい新居浜の実現に向け、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、過去何度か御質問させていただきました夜間中学についてお尋ねをいたします。
夜間中学とは、様々な理由で義務教育を修了できなかった方や、学校に行きづらく十分に通うことができなかった方々の学び直しの場としての役割を持ち、夜の時間帯に授業が行われる公立中学校の夜間学級のことです。令和6年10月時点では、32都道府県に53校設置をされ、今後3年間では、さらに13校が設置予定です。しかし、四国ではいまだに愛媛県のみ設置をされていません。昼間の学校同様、週に5日間、教員免許を持った公立中学校の教員が授業をし、授業料や教科書代は不要、全ての課程を修了すれば、中学校卒業となります。今年6月28日に、愛媛県教育委員会による夜間中学の設置検討に係る勉強会が開催され、設置検討に向けた夜間中学校の概要や全国の設置状況及び動向、設置に係る補助金等についての情報提供、本市教育委員会も勉強会に出席をされたとお聞きをしております。この中で、全国で夜間中学の設立に携わり、三豊市で夜間中学校設置にも御尽力をされ、岡山自主夜間中学校代表の城之内庸仁先生の講演があったかと思います。講演をお聞きし、お感じになったことは何か、また何を得られましたでしょうか、どのようなお話だったかもお教えください。
また、国の方針と補助事業、設置までの流れ等の御説明があったかとお聞きをしております。新設準備として、2年間は3分の1の補助、上限400万円、開設後3年間は3分の1補助、上限250万円、国から最大5年間の補助があります。昨年の6月議会では、多額の経費が必要との御答弁がありましたが、本市で設置の運びとなった場合、金額、市費の想定は幾らでしょうか。積算根拠も併せてお願いをいたします。
三豊市教育委員会にお尋ねをしたところ、夜間中学に関わる人員は16名、うち1名は校長先生。校長先生は、昼と夜の勤務、10名の先生方は夜間中学専属で週5日勤務。校長先生を含む11名の先生方の人件費は、県費で賄われており、市費としては音楽、保健体育、家庭科、美術、技術の非常勤の先生方が5名で、時給1,313円、4時間、週1回の勤務、養護教諭、学校事務の方は、半日勤務の週5日の勤務。運営費として今年度予算額250万円、内訳としては電話代、コピー代、備品購入、指導書、消耗品など。令和5年度は330万円。3年目となり備品購入が減ったこと、また既存の高瀬中学校の教室を利用するため、光熱水費がかからない、また先生の人手不足と言われますが、定年退職された先生方が、夜間中学で再任用されているとお聞きし、なるほど、教育の機会の確保としてお取組をされており、大変すばらしいと感じました。
次に、強く要望をさせていただいている特例校についてお尋ねをいたします。
先月11月1日の愛媛新聞では、全国小中学校不登校最多34万人、愛媛では27.4%の増、3,475人と大きな見出しで報じられておりました。これは、昨年度の文部科学省の調査によるものです。本市も同様に、年々増加をしております。文部科学省の対策として、学びの多様化学校、いわゆる不登校特例校の設置を促しており、全国に300校の設置を目指しております。夜間中学に入学するには、16歳以上が原則で、学齢期の生徒は入学ができません。夜間中学に学齢期の児童生徒が通学するためには、学びの多様化学校の認可が必要です。今現在は、三豊市と福岡県大牟田市の2校のみです。学校に通えると思ってなかった、高校に進学したいので勉強を頑張る、三豊市の夜間中学に通う学齢期の生徒さんの言葉です。
また、起立性調節障害を御存じかと思います。朝起き上がれない、学校に登校できないという症状があります。夜間中学は、起立性調節障害の生徒もしっかりと学習できる時間帯の学校です。
このように、学校に行きづらい学齢期の生徒において、もう一つ選択肢が増えると考えます。御所見を伺います。
次に、動物愛護について、飼い主のいない猫の不妊去勢手術補助事業について伺います。
10月1日から12月31日まで、目標額100万円のガバメントクラウドファンディングが実施をされております。本日現在62万9,000円、達成率62.9%、9月議会で全額予算措置をしており、目標額に達しない場合でも、補助金額を減額することは考えておりませんとの御答弁をいただきましたが、しかしながら目標額は達成をしたい。市では、様々な周知をしていただいておりますが、自ら先頭に立つトップセールス古川市長、ラストスパート、達成に向けた取組をお示しください。
飼い主のいない猫の不妊・去勢手術補助事業費は、前年度予算額50万円は9月に終了、今年度は倍の100万円の予算枠ながら、11月に終了をいたしました。猫の望まれない繁殖を防ぎ、良好な生活環境の保持と限られた予算を有効に活用するため、昨年、にじのはしスペイクリニック獣医師高橋葵先生の下に担当課と伺い、新居浜市でも不妊去勢手術移動式手術車が来てくださるようになりました。今では本市愛護団体と市民の方が、募集や受付、申請や当日の補助、また御高齢の方で御自分で捕獲が難しい場合はそのサポート、会場や先生との打合せなどしてくださるようになりました。この流れを止めないよう、飼い主のいない猫の不妊去勢手術補助事業を継続していただきたいと思いますが、本市の方向性をお示しください。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) 小野志保議員さんの御質問にお答えいたします。
動物愛護についてでございます。
飼い主のいない猫の不妊去勢手術補助事業についてお答えいたします。
まず、達成に向けた取組についてでございます。
10月1日にスタートいたしましたガバメントクラウドファンディングにつきましては、本市の殺処分される猫をなくしたいとの趣旨に共感いただいた皆様から、現在目標額の6割を超える寄附をいただいているところです。目標金額100万円の達成に向けましては、全国にいはま倶楽部の会員の皆様へチラシを送付し、寄附の御依頼をさせていただいたほか、私自身もチラシを持参し、各方面へ御依頼させていただいておりますが、期間終了まで多くの方々から御寄附いただけるよう、積極的に取り組んでまいります。
次に、飼い主のいない猫に対する不妊去勢手術補助事業の継続についてでございます。
今年度は、昨年度の倍となる予算で実施いたしましたが、11月19日時点で予算額に達し、補助事業が終了いたしました。本市の飼い主のいない猫への対策は、スタートしたばかりであり、また何より市民や本市動物愛護団体の皆様が連携し、移動手術車を活用した不妊去勢手術の取組が行われるなど、飼い主のいない猫問題への取組が根差しつつあることからも、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
○議長(小野辰夫) 高橋教育長。
○教育長(高橋良光)(登壇) 小野志保議員さんの御質問にお答えいたします。
夜間中学についてでございます。
まず、講演会に参加し感じたこと等についてでございます。
講演会に参加した職員からは、夜間中学での学びを必要とする人がおり、夜間中学の設置の必要性を改めて感じることができた。夜間中学の設置、運営は、愛媛県全体の取組と捉え、他市町と連携して進めていく必要性があると感じた。また、講演の内容としましては、設置までのスケジュール、組織体制をはじめ、通学等に関する事例が紹介されたとの報告を受けております。
次に、本市に設置するとなった場合の経費についてでございます。
現在のところ、まだニーズ調査を実施している段階であり、具体的な金額の積算までは行っておりませんが、先進事例の状況から推察いたしますと、教育環境の施設整備費用や市で雇用する人材の人件費、また新たに必要となる備品購入に要する経費など、多額の費用が必要になると見込んでおります。
次に、夜間中学を学びの多様化学校、いわゆる不登校認定校にすることにつきましては、令和4年度に開校しました三豊市立高瀬中学校におきましても、3年間で学齢期の生徒が4人入学していると伺っており、学校に行きづらい生徒にとって、選択肢の一つになっていると認識しております。
しかしながら、現在のところ、夜間中学の設置に関しましては、教員不足や財源に関する課題などもありますことから、愛媛県や他市町と連携した取組を進めていく必要があるものと考えております。
○議長(小野辰夫) 再質問はありませんか。小野志保議員。
○1番(小野志保)(登壇) 夜間中学について3つ再質問をいたします。
先ほど積算根拠が出てきてたと思うんですけども、結局幾らかかるかというのは計算はしていないんでしょうか。
2つ目、夜間中学は、その時代を映す鏡です。戦後の混乱期は経済的理由、1970年代から1980年代は十分に授業を受けられないまま卒業した形式卒業、1990年代は外国にルーツを持つ方々、近年は不登校が年々増加、文部科学省も学びの多様化学校、いわゆる不登校特例校の設置を促しています。教育長は、この学びの多様化学校について、どのようなお考えがありますでしょうか。また、これらは必要だと思われますか。
3つ目、本市でも対策を講じていますが、学校に行きづらい児童生徒が増えることをどう分析をしていますか。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。高橋教育長。
○教育長(高橋良光)(登壇) 小野志保議員さんの再質問にお答えをいたします。
まず、多額の費用についての計算をしていないのかという再質問でございますけれども、先ほども答弁申し上げたとおり、現在のところはまだニーズ調査を実施している段階であり、具体的な金額の積算までは行っておりません。そして、先進事例の状況から推察をしたというのが再質問に対するお答えでございます。
2つ目の夜間中学の中で、学びの多様化学校についてどのような考えであるかということですけれども、これも先ほど答弁申し上げました中で、学校に行きづらい生徒にとっては、選択肢の一つになっているという認識を持っております。
3つ目、学校に行きづらい児童生徒が増えていることをどう分析しているかということですけれども、新居浜市だけでなく、これは全国的に増えておりますし、先ほどの御質問の中にもありましたが、愛媛県でも同様でございます。新居浜市においても、それぞれの学校できめ細かに丁寧な対応をしておるところですけれども、なかなか不登校が止まらないというのが現実でございます。
そうした中で、それぞれの学校では、別室における対応を行ったり、場合によってはそこに授業をリモートで提供したりというようなことで対応しているところです。様々な要因があって、不登校になっているものと思っております。なかなか原因を一つに特定してというところは、分析はしておるんですけれども、一つの理由を出していくということはなかなか難しいところでございます。増えている不登校に対して、対応を先ほど申し上げたようにしているというのが現状でございます。
○議長(小野辰夫) 再質問はありませんか。小野志保議員。
○1番(小野志保)(登壇) 計算をしていないのに、多額の経費がかかるというのは、納得できないんですけれども、次回に続くということで、ぜひとも計算をしていただきたいと思います。
それでは、市長に伺います。
1つ目、所信表明では、むしろ他市に先んじるチャンスが来た瞬間だと捉え、常に挑戦する町へ、たゆまぬ変革を行いとおっしゃっておりました。夢や希望を持てる新居浜市、まさにこの夜間中学はそうではないでしょうか。
2つ目、市長の公約にも、四国で一番の子育て支援とし、その中に夜間中学が含まれております。どのようなお気持ちで公約にされたのでしょうか。
3つ目、学ぶことは生きること、学校に行きづらい児童生徒のこの先の進学、就職、生活に大きく影響をいたします。夜間中学設立に向けての市長御自身の御所見を伺います。
以上、3点お願いします。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) 小野志保議員さんの再質問にお答えいたします。
まず、1つ目でありますが、私自身、所信表明にて、時期尚早であるとか、前例踏襲という言葉を使わないように、挑戦する町にしたいということをお伝えしてきました。まさに、夜間中学も含めて、様々なことに対して、もちろん過去の経緯、経過は大切にしながらも、新しいスタートと思って状況をしっかりと確認していきたいというふうに思います。
2つ目、3つ目、これは共通することでありますが、私自身、やはり学びの多様化というものは、これからも進めるべきであるというふうに思いますし、多様な選択肢、受皿というものの確保ということにも努めていきたいというふうに考えています。
そのような中で、今後のことも考えていきたいと思っておりますが、やはりまずは教育長からの御答弁のとおり、愛媛県や他市町の連携や取組も鑑みながら、これから検討していきたいと思います。
○議長(小野辰夫) 再質問はありませんか。小野志保議員。
○1番(小野志保)(登壇) 学びの機会の確保、これは本当に大切だと思っております。だからこそ、夢や希望を持てるっていうこともあるかと私は考えております。この新居浜市で学びの多様化学校、夜間中学ができますように強く要望したいと思っております。
また、動物愛護については、市長自ら率先して動いてくださることは知っておりましたので、引き続き共に頑張ってまいりましょう。
以上で私の質問を終わります。
○議長(小野辰夫) 渡辺高博議員。
○3番(渡辺高博)(登壇) 自参改革クラブの渡辺高博でございます。
まずは、古川市長、御就任おめでとうございます。二元代表制の下、市政を担う両輪として、愛媛ナンバーワンにとどまらず、日本で唯一の町を目指す気概を持って、お互いベクトルを定めて、緊張感のある議会運営を行ってまいりましょう。
さて、近年の価値観の多様化、少子高齢化と人口減少の影響による働き手の不足は、これまでの前例主義を否定し、新たな価値基準の下で市民生活をつくり上げていくことになります。今の行政に求められるのは、時代の流れを読み取る感性とそれを速やかに実行に移すスピード感です。市長が再生と挑戦、その先へ、新しいにいはまのスローガンの下、選挙のときにうたわれた約束と公開討論会での発言も踏まえ、通告に従って4点質問させていただきます。
まずは、資料1を御覧ください。
これは、市長選挙を控えた今年の10月上旬に、市内のフリーペーパーに折り込まれた古川氏の新居浜に対する思いの籠もったチラシの抜粋です。2項目めの誰も取り残さないやさしいコミュニティづくりの3番目で、自動運転バスなど地域公共交通の拡充検討や買物弱者のための次世代買物支援を掲げていらっしゃることに関連して、MaaSシティのこれからについてお伺いいたします。
今回の市長選挙の期間中に市民の皆さんから多く聞かれたのが、公共交通機関の整備に対する切実な願いと提案に対する関心の高さでした。現状、自動車免許を返納した方の移動手段は、乗り合いのデマンドタクシーになりますが、川西、川東、上部西、上部東の4エリアに分かれていて、例えば船木から住友別子病院やイオンに行こうとした場合は、新居浜駅まで行ったら、その後はせとうちバスやタクシーを乗り継いで向かうことになります。また、目的地以外で下車することができないので、外出ついでに用事を済ませることが制限されます。現在、国土交通省において、地域住民や旅行者一人一人のトリップ単位での移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索、予約、決済等を一括で行うサービスの検討が行われ、移動の利便性向上や地域の課題解決にも資する重要な手段として全国各地で実証実験の支援が拡充されています。
先日、杉並区が行っているグリーンスローモビリティの条件付自動運転に乗車させていただきました。ハイエース程度の大きさの車両で、乗車人数は7名、実験中ですから、運転手がいて、危険と判断した場合には、自動から手動に切り替えて対応を取るのですが、20分程度の乗車の間に自動で走っていたのは5分ぐらいだったでしょうか。道路を線路のように認識して、線をたどるように走るのですが、結局歩行者の不規則な動きや自転車の逆走、路上駐車などが原因で急ブレーキになったりします。まだまだ課題はたくさんありますが、道路幅3メートルを切るような狭い場所を走行したり、松山市では伊予鉄バスが今月25日から特定条件下においてドライバーが介入しない完全自動運転の営業運転を始めることになっており、今後見込まれる高齢化によるバス需要の高まりと運転士不足などの理由で路線の維持が厳しい状況を解決する手段として期待できるものだと思います。
このように、2019年から日本版MaaSとして全国各地で地域課題の解決のために検証を行い、本市も2022年からMaaSシティーとして取り組んでいる移動が難しい住民に継続的なサービスが受けられる環境を実現するために、本市として今後どのように輸送サービスなどのデジタル化を推し進めていくおつもりか、お伺いいたします。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) 渡辺議員さんの御質問にお答えいたします。
MaaSシティのこれからについてでございます。
高齢化や免許の返納が進むことにより、自宅からの移動が難しい方にも継続的にサービスを受けられる環境の構築は重要であり、そのためのツールとして、デジタル技術の導入は、今後ますます重要になってくるものと認識いたしております。
本市の取組といたしましては、新居浜市公式LINEの基本メニュータブに交通情報のアイコンを追加し、おでかけタクシー、路線バス、渡海船、JRなどの交通情報を集約し、各交通情報にアクセスしやすくしているほか、路線バスにおきましては、瀬戸内運輸株式会社等で構成する愛媛デジタル推進グループが、本年6月に愛媛県のトライアングルエヒメ推進事業デジタル実装加速化プロジェクトの支援を受けて、LACバスシステムを稼働しており、バスの位置情報のリアルタイム表示や遅延情報などを簡単に見ることができ、利用者からも好評をいただいております。
また、川西地区のデマンドタクシーにおきましては、スマートフォンでの予約やAIによる配車が可能なシステムを用いた実証運行を行っておりますが、登録者の9割が70歳以上の方ということもあり、スマートフォンを使っての予約は5%程度にとどまるなど、まだまだ課題も多く、導入方法も含めた見直し、再構築が必要な状況でございます。
今後におきましても、運転手不足を解消する手段として期待されている自動運転技術の進捗状況等に注視し、地域公共交通のデジタル化に向けて調査研究を行ってまいります。
○議長(小野辰夫) 渡辺高博議員。
○3番(渡辺高博)(登壇) 御答弁ありがとうございました。
昨日の大條議員の質問にもありましたが、公共交通は既に逼迫しております。先ほど小野志保議員からもお話がありましたけれども、前例がない、時期尚早などと言っている場合ではありません。現状維持ではなくて、チャンスが来た瞬間だと捉えて、たゆまぬ変革を行いとお話しいただいておりますが、この件に関してもぜひ積極的な取組をお願いしたいなと思っております。実際に自動運転バスに取り組んでいる松山市があるわけですから、ぜひしっかりと見ていただいて、早急に取り組んでいくような検討もいただきたいなと思っております。
今年度の公募実績から推察すると、日本版のMaaS推進・支援事業の公募は、毎年年度初めになるんだと思います。MaaSシティーに地域公共交通確保維持改善事業の新型輸送サービス導入の支援を加えて検討していただくことをお願いして、次の質問に移らせていただきます。
改めて、資料1の1の項目を御覧ください。
四国で一番の子育て支援の最後に掲げてありますスポーツ・文化活動の充実を目指した仮称にいはま文化スポーツクラブについてお伺いいたします。
私は、2年前の市議会議員選挙の際に、スポーツと文化のまち新居浜をスローガンに、文化スポーツ活動が日常化するように、総合型地域スポーツクラブの支援をうたわせていただきました。その根底には、今後見込まれる核家族化を通り越した独り世帯の増大を踏まえ、地域、家庭や学校、職場などのこれまでのコミュニティーを補完する仕組みとして、新たに趣味や嗜好を共有できる仲間づくりのお手伝いがあります。総合型スポーツクラブとは、1990年代に文部省が地域住民が主体となって、地域社会全体でスポーツ環境を支えるヨーロッパ型のスポーツクラブの概念を取り入れて、生涯を通じてスポーツを楽しむことを重要視し、子供から高齢者まで誰もが参加できる多様なプログラムが用意されて、競技志向のスポーツだけでなく、健康維持やレクリエーション活動も対象で、住民の健康維持増進や社会的孤立の防止に役立てることを目的にしています。
しかし、日本のスポーツ活動と言えば、主に学校の部活動に依存しており、地域全体で支える仕組みが十分に整っているとは言えません。そのため、卒業後にスポーツを継続する人が少なく、生涯スポーツとしての文化が育ちにくいと言われています。そんな状況でも、急速な高齢化が進む中で、高齢者が健康を維持し、社会参加できる場としてのスポーツや文化環境の早急な整備が求められています。
これまで、私は、プログラムを提供する事業者として全国各地の総合型地域スポーツクラブの運営状況をつぶさに見てまいりました。ヨーロッパで成功しているモデルを日本の自治体に取り入れようとしたときの弊害は、結局既存の仕組みだというのが私がこの20年関わってきて出した結論です。私は、中学校部活動の地域移行は、生涯スポーツの一部に中学生を組み入れるチャンスだと考えています。これまでも度々関連した内容を議会で質問させていただいておりますが、活動実績があって、問題意識を共有し、変革意欲に満ちた団体を核に、総合型地域スポーツクラブを整備することが必要だと思っています。市長もPTA会長として、改革推進の会議に参加し、この2年間、中学校部活動の地域移行について検討を重ねてこられたことと思いますが、スポーツ庁や文化庁が推進している内容を踏まえ、市長の思い描くにいはま文化スポーツクラブとはどのようなものなのか、お伺いいたします。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) 仮称にいはま文化スポーツクラブについてお答えいたします。
議会初日に私の所信の一端として申し上げさせていただきました公約の柱に、子育て支援の充実を掲げており、その中でスポーツ・文化活動の充実を図り、四国で一番の子育て支援の実現を目指したいとお約束させていただきました。中学校部活動の地域移行につきましては、現在教育委員会の新居浜市部活動のあり方及び地域移行に関する検討委員会において議論され、部活動の在り方や段階的な地域移行に関すること、また市の推進計画の策定に関することが検討されているものと認識いたしております。
私が思い描くにいはま文化スポーツクラブは、地域の指導者や活躍している人材、プロスポーツなどの力を借り、子供たちが全国を目指せる競技力を習得するものと、楽しく参加できる生涯スポーツや文化活動が両輪となって、子供たちが自ら進んでスポーツ・文化活動に継続して取り組めるような拠点となるクラブを創出し、部活動の地域移行の受皿となるほか、将来的には小学生から中学生、中学卒業後もこのクラブでスポーツ・文化活動に親しんでもらい、生涯にわたって、自分のライフスタイルを見いだすきっかけに寄与するクラブを目指したいと考えております。実現には、クラブ設立に係る人員や運営費の確保など、多くの課題があり、直ちに取り組むことは難しいかもしれませんが、四国で一番の子育て支援の一つとして、子供たちのニーズを的確に捉えながら、教育委員会で検討されている内容も踏まえ、本市に最適なクラブの在り方につきまして、子供ファーストで模索してまいりたいと考えております。
○議長(小野辰夫) 渡辺高博議員。
○3番(渡辺高博)(登壇) 御答弁ありがとうございます。総合型地域スポーツクラブと言われて、何となく民間のフィットネスクラブと重ねて考えられる方がいらっしゃるんですけども、これとは一線を画してまして、地域のコミュニティーの醸成から始まって、住民の心身の健康を補ったり、町の活力を引き出す、こんなことを期待されていろんなところで展開しておるものです。今市長からも言っていただいたとおりで、そういう形でしっかり仕上げていきたいなと思うんですけれども、そういう意味で言うと、先日の市民福祉委員会で国民健康保険料の料率アップが話題になって、本市でも健康寿命延伸のための健康づくり推進には、庁内関係課所の組織横断的な取組が必要という見解で一致しているところだと思います。より踏み込んで言えば、行政の範囲を超えて、クラブと一体になった施策の推進が理想だったりするわけで、施設の指定管理や運営の業務委託など、それぞれを担わせるぐらいまで踏み込んで、その結果として総合型地域クラブに全てを任せるような、そのぐらいの振り切った考え方も必要なのかなと思ったりしております。いろんな自治体を見ていく中で、やはり自治体さんの協力を得ながら、総合型地域スポーツクラブをつくっていくような、私自身が葛飾区とは良好な関係を築いていただいていたんですけども、そこなんかは葛飾区がほぼスポーツ行政の仕事をクラブに渡しておくというようなことで進めていくことで、その中に私なんかが講師として呼ばれたとき、非常に心地よくクラブとして仕上がっていたなと思っております。私の経験も踏まえて、ぜひともそういう形に実現できるように、協力をお願いして、次の質問に移らせていただきます。
多目的アリーナについてお伺いいたします。
市長は、公開討論会の場で、市民文化センターの建て替えに異議を唱え、防災の観点からも例えばイオンの周辺に多目的アリーナを建設するとかと御発言しております。私は、9月の議会で、文化スポーツ施設の考え方について質問させていただき、これから人口が減少していく中で、新しい文化スポーツ施設がどんどん造られることはなくなり、既存施設を上手にリニューアルして長寿命化しつつ、その時代の動向を見極めて、新たに現状に合った機能を付け加えながら、時代のニーズを補完してほしいとお願いしました。いずれ総合運動公園構想が動き始めた際には、その積み上げが功を奏して、市民に愛される施設を造るために役立ち、利用することに喜びと誇りを持てる施設は、市外からの訪問者にも気持ちよく利用して、充実した時間を過ごしていただけるものになると申し上げました。
資料2を御覧ください。
先ほどから引用しているチラシの別のページ、新居浜市の課題の抜粋になりますが、タスク5で、現在基本計画を策定して、事業手法の検討を行っている市民文化センターの建て替えについて、現在の文センでも利用者が少なく、固定椅子など構造上、避難所として活用できないばかりか、市民ニーズに応えれる多目的な使用もできません。既にある総合文化施設あかがねミュージアムも、市民の利用が少ない中で、新居浜市に本当に必要な施設かどうかの再検討や本市の活性化につながる別事業への転換が必要とうたわれております。
話は少々飛躍しますが、東京オリンピック・パラリンピックのために、総工費約1,569億円をかけて2019年11月に完成した国立競技場は、本稼働を開始した2022年度支出が、維持管理費など約17億円に対して、収入は約9億円、2023年度、2024年度もそれぞれ10億円程度の赤字が見込まれていて、2025年4月から事業期間30年の民営化の際には、事業者に対して年間10億円を限度に維持管理費を穴埋めする方針を表明しております。
今回の市民文化センター建て替えの基本計画でも、高度な専門性や市民との協働が求められることから、PPPやPFIなどの官民連携による運営体制も含めて、今後官民連携手法導入可能性調査の実施などを通して、適切な管理・運営主体の在り方を検討するとありますが、施設のランニングコストを未来永劫税金で補填しなくてはいけないようなことになっては本末転倒です。これからの文化スポーツ施設は、造ることが目的ではなく、財政的な持続可能性を確保することが長期的な利用を支える鍵となります。
今年の4月に国立競技場で東京六大学陸上が開催されたときの1日の使用料は200万円でした。これはまだ安い設定で、プロスポーツ大会や商業イベントでは、1日で1,000万円を超えると言われています。今の公共施設は、市民や県民だけのものではなく、訪れる利用者も含めて、受益者が応分の負担をしながら支えるものだと考えます。アリーナに限定した話ではありませんが、市長の思い描く今の本市に求められる文化スポーツ施設とは、どのような役割で、いかに管理運営されるものなのか、検討されている多目的アリーナを例に御説明ください。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) 多目的アリーナについてお答えいたします。
私が思い描く現在の本市に求められる文化スポーツ施設につきましては、第一義に、市民が気軽に文化スポーツ活動をする、見る、支えることができること、さらには高度な文化スポーツに触れることができることが大切であると考えております。
そのため、今ある限られた資源を安心、安全に利用できることを最優先に、長期にわたり利用できるような管理と、いつでも、どこでも、誰でも利用できるといった市民に寄り添った運営がなされなければならないと考えております。
そこで、私が公約と掲げさせていただいております近隣にはないアリーナの建設につきましては、プロスポーツやライブなどのエンターテインメント、幼稚園や保育園の運動会、市内一斉就職相談会などができ、近隣にはない独自性を持ち、日頃から市民が使える稼働率の高い、また災害時など緊急時に力を発揮する施設建設の可能性を求めるものでございます。
また、現在の文化スポーツ施設も、多くの市民が利用していただいておりますが、より多目的に利用できれば、プロスポーツや人気のエンターテインメント、高度な芸術文化に市民が触れられる機会の創出につながり、これまで以上の効果的な活用が図られるものと考えております。
いずれにいたしましても、文化スポーツ施設は、これまでも、これからも、文化スポーツ活動を通じた市民の心豊かな生活に貢献することが大きな役割であると思っておりますので、市民のニーズに応えつつ、より一層安心、安全に利用できる環境づくりに努めてまいります。
○議長(小野辰夫) 渡辺高博議員。
○3番(渡辺高博)(登壇) 御答弁ありがとうございました。今、市長の思い、非常にしっかり受け止めさせていただきました。文化センターの話が進んでいる中で、あえてアリーナの構想を提案されたというようなことで、ぜひともその方向で御検討をしていただけたらと思うんですけれども、そのためにも、収益を上げて幾らといいますか、永続性を必要とするようなことを、やはり採算が取れるかどうかということがまず大事になっていくと思うので、今ある施設もそうなんですけれども、随時変更しながら、今までみたいに文化体育施設は採算度外視でというよりも、とにかく採算が取れるというか、少し商業的な思いを持って検討していただきたいなと思っております。
先日、人口減少対策特別委員会で富山市を訪れたときに、市内の中心部に小学校の跡地をPPP手法によって民間のリース会社が公共施設と民間施設を一体的に整備して、公共施設は完成後に市が買い取った事例の説明を受けました。民間で運用しているフィットネスクラブと立体駐車場やコンビニは、どれも非常に潤っているようだとの担当者のコメントもありまして、行政と民間が連携して、公共施設の建設や維持管理、運営などを行う際には、企業と共にウィン・ウィンになれる落としどころが必要なのだと感じております。今後の公共施設の整備に当たっては、企業のやる気を引き出す仕組みを視野に入れながら、交渉して進めていただくことをお願いして、次の質問に移らせていただきます。
最後に、企業版ふるさと納税についてお伺いいたします。
地方自治体が実現する地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行うと、企業は寄附額の最大約9割の税額軽減の優遇措置が受けられる仕組みです。まずは、地域課題を明確にし、その解決に資する事業計画を策定するところから始まります。その後、内閣府に対して、地方創生プロジェクトの認定申請を行い、承認を受け、寄附金の用途や期待される成果を明確化して、企業との関係構築を図るわけです。
さきの決算特別委員会で、企業版ふるさと納税促進事業費の支出先は、寄附を仲介した県内金融機関に対する手数料だと伺いました。また、令和5年度の予算は100万円でしたが、今年度は50万円と半減しており、予算額だけではかれるものではありませんが、支払った実績から見ても意欲的に取り組んでいるとは思えない状況です。しかし、日本全体で見た寄附額は、右肩上がりで増大しており、内閣府も来年度の税制改正要望で、地方創生応援税制として、新たに5年間の期間延長を求めており、寄附額が今後より拡大することは、容易に想像できます。
さきの3つの質問で掲げた施策の実現に当たっても、市税収入に替わる新たな財源の確保が求められます。
さて、制度の立てつけ上、本社が所在する地方公共団体への寄附については認められていませんから、県内の金融機関に仲介を依頼しても限界があります。簡単に言えば、首都圏に本社のある法人から選ばれて寄附してもらう必要があるわけです。企業としては、返礼品のような経済的な見返りがあるわけでもないので、その自治体の事業に共感して寄附をすることになりますが、1,700を超える地方自治体の中から選ばれるのは至難の業です。民間企業であれば、まず本市にゆかりのある首都圏の企業経営者をリストアップしてローラー作戦するとか、コンサルタントを雇って決め打ちで企業に対して本市がどのような貢献ができるか提案するなんてことを考えると思います。9割を税額軽減されるとしても、残りの1割は持ち出しになるわけですし、税額控除されるのが、法人住民税や法人事業税ということは、企業が所在する自治体は、その分減収になるわけですから、寄附によって流出する金額が増大していけば、企業立地促進対策費のような自治体が用意する奨励措置に影響が出て、所在する自治体と企業との間にあつれきが発生しないとも言えません。それら障壁を越えて、協力企業と良好な関係を築き、本市の新たな安定財源として確保するためには、明確な戦略が必要です。
財政は非常事態との認識で、新居浜版営業本部を設置し、自らのトップセールスにより市税収入アップを掲げている市長の企業版ふるさと納税に取り組む姿勢についてお伺いいたします。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) 企業版ふるさと納税についてお答えいたします。
企業版ふるさと納税は、企業が地方公共団体の地方創生プロジェクトに寄附を行った場合、法人関係税の軽減措置を受けられる制度であり、新居浜市総合戦略の着実な推進と新たな財源確保につながる重要な制度であると認識しており、私自身が積極的にトップセールスに取り組んでまいります。
また、これまでの県内金融機関との連携実績も踏まえ、本市の施策や魅力、さらには制度のメリット等に関し、計画的かつ効果的に企業へPR展開することが重要だとの認識の下、新たな民間企業との連携を進めていきたいと考えております。
この新たな連携を通じ、本市独自の営業ツールや寄附対象としてPRする施策の戦略的な絞り込み、また営業先企業の選定等を図り、企業版ふるさと納税のさらなる活用を推進しながら、新しい新居浜の実現に向けた財源確保に取り組んでまいります。
○議長(小野辰夫) 再質問はありませんか。渡辺高博議員。
○3番(渡辺高博)(登壇) 御答弁ありがとうございました。市長の気構え、しかと伺わせていただきました。愛南町の城辺中学校体育館にこの夏導入された空調設備は、企業版ふるさと納税の寄附とのことです。ぜひとも営業マインドを持って邁進していただきたいと思います。
最後に、市長には、定例会開会の挨拶にありました3つのテーマに沿って市政を運営し、夢や希望を実現することのできる、市民誰もがこの町で生まれ育ってよかったと思えるまちづくりを目指していただきたいと思います。私も本市をよくしたいと思う熱量は同じくらい大きいと思っていますから、今後の活発な議論と献身的な対話を経て、お互いに力を合わせて変革していくことを……。(ブザー鳴る)
○議長(小野辰夫) この際、暫時休憩いたします。
午前10時54分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前11時05分再開
○議長(小野辰夫) 休憩前に引き続き会議を開きます。
片平恵美議員。
○6番(片平恵美)(登壇) 日本共産党の片平恵美です。
古川市長、御就任おめでとうございます。市民との対話の重視というのは、本当に新しい新居浜をつくる力になると期待しております。よろしくお願いいたします。
まず、学校給食の無償化について質問します。
この一年、本市議会でも学校給食費の無償化に関する質問が繰り返しされてきました。市は財源の確保が難しいこと、学校給食法第11条第2項で、学校給食費は保護者の負担とされていることなどを理由に困難であるとの答弁を繰り返してきました。また、経済的に配慮が必要な方々については免除制度があるとも答弁されています。
9月議会でも申し述べましたが、生活保護を受けていない、要保護と認定されていない児童生徒のいる御家庭も決して楽ではない。学校給食法が保護者負担と言っているのは原則であり、実際、日本で義務教育を受けている子供たちの半数は、給食費が無償になっている状況で、本市で実現できない本当の理由は何なのか、甚だ疑問に感じております。
古川市長の県議時代の市民へのお手紙にはこうありました。新しい新居浜を共につくりませんか。テレビや新聞、インターネットでは、全国の自治体の給食費無償化や高齢者への医療ケアなどの先進的取組が報道されています。西条市や四国中央市ではできている政策を、なぜ私たちが暮らしている新居浜ではできないのか、そんな疑問を感じたことはありませんか。こうした政策はできないのではなくやっていない、やろうとしていないのが現状です。
逆に言えば、やろうとする姿勢が大事ということかと思います。私もそう思っておりまして、9月議会では、必要性に対する認識を質問しましたが、そのときはお答えがありませんでした。
そこでまず、給食費の無償化やおいしくておなかいっぱいになれるメニューを検討することを公約に掲げ当選された市長にお伺いいたします。
この公約を掲げたお気持ち、何のためにこの政策が必要であるとお考えになったのか、必要性に対する認識をお聞かせください。
2つ目に、実現への課題と手だてについて質問します。
給食費を無償化するに当たり、現在既に経済的配慮が必要な世帯や多子世帯へ補助をしている5,000万円を除き、新たに4億3,000万円の財源が必要となると伺っています。出費が増える中学生だけを対象とすれば1億7,000万円、受験や進学を控えさらに出費が増える中学3年生だけを対象とすれば6,000万円弱です。
実現に当たっては、様々な方法が考えられると思いますが、認識されている課題と解決の見通し、目標としていつ頃からスタートさせたいとお考えなのか、お伺いいたします。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) 片平議員さんの御質問にお答えいたします。
学校給食の無償化についてでございます。
まず、私の思いについてお答えいたします。
私が市長選挙に出馬を決意するに当たり、本市を四国一子育てしやすい町にしたいという強い思いから、子供たちの健やかな心と体の発達を願う保護者の皆様の負担軽減を考え、学校給食費の無償化を検討したいと考えました。
また、学校給食の中で果たすべき重要な役割とは、おいしくて栄養バランスの取れたメニューづくりと子供たちの好き嫌いがなくなるような食育への取組であると考えております。まずは、学校給食センターにおける給食の取組について、保護者の方を含め、市民の皆さんに知ってもらい、今後も多くの食材を使用した多種多様な献立を考えて、学校給食の充実を図ってまいりたいと考えております。
次に、実現への課題と手だてについてでございます。
学校給食の無償化実現のためには、多額の財源が必要となり、ほかにも様々な重要施策もありますことから、優先順位や実施スケジュールを踏まえ、今後検討してまいりたいと考えております。
○議長(小野辰夫) 片平恵美議員。
○6番(片平恵美)(登壇) 優先順位、実施スケジュール、考えなくてはいけない課題というのはたくさんあると思いますけれども、任期中に実現したいというお考えはあるんですよね、ちょっと確認させてください。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) 片平議員さんの御質問にお答えします。
任期中に可能な限り実現したいという思いで、公約に書かせていただきました。
○議長(小野辰夫) 片平恵美議員。
○6番(片平恵美)(登壇) 四国中央市ではできている政策を、なぜ私たちが暮らしている新居浜ではできないのかというところを出発点に、どうすれば可能になるのかというところをこれからしっかりと検討していかれるんだというふうに思います。ぜひ可能にしていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
本来的には、国がやるべき仕事であるというふうに私たちは考えておりまして、また県も補助するべきものだというふうにも思います。私たち日本共産党は、給食費無償化を求める市民の皆さんと御一緒に、国に対してもしっかりと求めていく、そして市に対しても、県に対しても、今後も求め続けていきたいと思います。ぜひ熱意を持ってやっていかれる、実現する手腕に期待をしたいと思います。よろしくお願いします。
2問目、職員の配置について質問します。
自治体の役割は、市民福祉の増進で、それを担うのが市の職員です。職員の働き方は、市民サービスに直結します。働きがいを感じ、働き続けたいと思える職場であってほしいと思います。
本年6月議会で伊藤優子議員の質問に対し、新居浜市でも年々定年前の退職者が増えているとの御答弁がありました。理由は様々ですが、全国的にも自治体職員の定年前退職は増えており、その主な要因の一つに、長時間過密労働があるとされています。
そこで、お伺いします。
現在と5年前、10年前、20年前の正規職員と非正規職員の人数、事業数の増減と必要な人員数、年休取得率、時間外・休日労働の時間数、精神的な原因で休職をしている職員の人数を教えてください。
また、労働安全衛生法の産業医の面接指導の基準である時間外・休日労働時間が月80時間を超え、職員に情報を提供した数を一般職、管理職、それぞれ直近5年間について教えてください。
また、ストレスチェックをされていると伺っていますが、チェックを開始した当時と現在とでどのような変化がありますか、それをどう受け止めていらっしゃいますか、お願いします。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。髙橋総務部長。
○総務部長(髙橋聡)(登壇) 職員の配置についてお答えいたします。
まず、正規職員と非正規職員の人数についてでございます。
なお、各年度4月1日現在、また非正規職員については週20時間以上勤務がある者の人数で申し上げます。
令和6年度は、正規職員915人、非正規職員578人、5年前の令和元年度は、正規職員918人、非正規職員652人、10年前の平成26年度は、正規職員892人、非正規職員638人、20年前の平成16年度は、正規職員963人、非正規職員584人でございます。
次に、事業数の増減と必要な人員数についてでございます。
事業数については、一般会計及び特別会計の合計で申し上げます。
令和6年度は、9月補正までで741事業、令和元年度807事業、平成26年度797事業、平成16年度774事業でございます。
必要な人員数につきましては、毎年度定員管理調査の結果を踏まえて配置しており、必要な人員は確保されているものと考えております。
次に、年休取得率につきましては、令和5年35.1%、令和元年29.9%、平成26年27.3%、平成16年24.3%でございます。
次に、時間外・休日労働の時間数につきましては、令和5年度の時間外勤務の総時間数が8万6,060時間、令和元年度9万3,967時間、平成26年度10万4,104時間、平成16年度15万274時間でございます。
次に、精神的な原因で休職している職員の人数につきましては、令和5年度13人、令和元年度5人、平成26年度7人、平成16年度7人でございます。
次に、労働安全衛生法上の産業医面接指導の対象となる時間外勤務や休日勤務が月80時間以上及び直近2か月から6か月の時間外勤務時間の平均が80時間以上あった職員の合計人数は、令和5年度は、係長以下の一般職で111人、管理職203人、令和4年度一般職124人、管理職145人、令和3年度一般職130人、管理職148人、令和2年度一般職138人、管理職103人、令和元年度一般職101人、管理職55人となっております。
次に、ストレスチェックを開始した平成28年度当時と現在との変化につきましては、全体的な傾向として、仕事のストレスによる健康問題の発生リスクはほぼ横ばいとなっており、全国平均と比較しても良好であるという結果になっております。
ストレスチェックの結果の受け止めにつきましては、本市の結果は全体としてはおおむね良好と言えますが、高ストレスを抱えた職員に対しては、個々の状況に応じ、十分な注意を持って対応していく必要があるものと考えております。
○議長(小野辰夫) 再質問はありませんか。片平恵美議員。
○6番(片平恵美)(登壇) すみません、時間外のことでちょっとお伺いしたいんですけど、今は時間外で働こうと思ったら、先に申告をして、許可を受けないと時間外のお仕事はできないことが原則になっているかと思うんです。本当に仕事がたまりまくって、もう申告してる以上に働かないかんっていう方もおられて、時間外ではこれだけ申告しとるけど、実際はもっとたくさん働いているという、実態と申告してる時間の乖離がある場合があるかなというふうに思うんですが、そこのところはどんなでしょうか。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。髙橋総務部長。
○総務部長(髙橋聡)(登壇) 片平議員さんの再質問にお答えいたします。
時間外の申告の方法や申告よりも長時間に及んだ場合の対応というようなことだったかと思います。
時間外勤務命令をデジタル上で申告をする仕組みになっておりまして、時間外の必要があったときに、上司が認めて、命令をするという形で、例えば今日は20時までとか21時までとかということを事前に命令して、その時間内で仕事をするというのが原則になっております。ただ、片平議員さんもおっしゃったように、場合によるとちょっと長引いたとか、ちょっと早く終わったとかということがある可能性がゼロとは言えないと思うんですけども、そうした場合は、上司がいればその場で修正すればいいですし、翌日に実はちょっと1時間余分にかかったんだということを申し出れば後ほど修正というような対応をしておるものと承知しております。
○議長(小野辰夫) 再質問はありませんか。片平恵美議員。
○6番(片平恵美)(登壇) やっぱり議員としてというよりも、一人の市民として、職員さんには本当に生き生きと仕事をしてほしいというふうに思ってるんですよね。市民サービスっていうのは、そこに住んでいる人の住みやすさに直結するわけで、この公園は俺が手がけたとか、高齢になっても元気で暮らせるお手伝いができたとか、困っていたあの人が自分で生活できるようになったとか、そういう損得抜きに人のために何かをなすって、そんなのすばらしくやりがいのある仕事じゃないですか。そこにやりがいを感じられる職員こそ、住民福祉の増進に欠くことのできない戦力だというふうに思うんですよね。でも、一方、働きがいどころか、もうストレスがたまって余裕がないという状況もあるんじゃないんかなと思います。市民のためにと思っとんのに窓口ではカスタマーハラスメントされてしまう、大きなストレスの要因になります。また、仕事が忙しいとか責任が重たい、頭の整理が追いつかないなど働きがいを感じにくい状況もあるんじゃないでしょうか。先ほど時間外労働が、実態に即した数字ですかっていうふうなことをお伺いしたんですけれども、人事院も実態に即した労働時間、時間外労働の把握を行うようにと言ってます。パソコンのログとか、目視とかで確認する方法はあると思いますけれども、そこら辺の対策、今後何か変えていこうというお考えはあるんでしょうか。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。髙橋総務部長。
○総務部長(髙橋聡)(登壇) 片平議員さんの再質問にお答えいたします。
やり方を変えていくつもりがあるのかということなんですけども、今現在も既に今御指摘いただいたようなことは対応しておりまして、特に変える必要があるとは考えておりません。
○議長(小野辰夫) 再質問はありませんか。片平恵美議員。
○6番(片平恵美)(登壇) 申告と実態との乖離について本当にないのかどうかっていうのはきちんと、ないと思うということではなく、ないかどうかっていうのをパソコンのログをしっかり確認する必要はあるかなというふうに思います。申告上のということになりますけれども、年間を通して見たときに、時間外労働が多い部署と少ない部署がありますでしょうか。その傾向は、長いこと続いているのかということをお聞かせください。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。髙橋総務部長。
○総務部長(髙橋聡)(登壇) 片平議員さんの再質問にお答えいたします。
申告と実態の乖離がないのか、そういう部署はないのかということですけども、先ほど答弁いたしましたように、パソコンでログインをした、出勤をした、帰るときのログアウトの時間というのは、自動的に記録されていっておりますので、それと実際の時間外の勤務命令を受けて実際に仕事をした勤務時間との乖離というのは、デジタル的に把握できるようになっております。そういうものはないように努めておるところでございます。
部署によってそういうところが多いか少ないかというのは、同じシステムを使っておりますので。ただ、庶務事務システムが使えておる部署だけ、例えば外の機関とか、いわゆる出勤、退勤がデジタル的に管理し切れてないところは確かに幾つかはありますので、そういうところは少し難しい状況はございます。
○議長(小野辰夫) 再質問はありませんか。片平恵美議員。
○6番(片平恵美)(登壇) ちょっと私の聞き方が悪かったようで申し訳ありません。時間外労働が多い部署、遅くまで残って仕事をしているところと、定時になったらさっと帰れる部署と、そういうところのばらつきがないんかっていうことをお伺いしたかったのと、あとそれに関して、人員配置の工夫なんかで改善できないものなのかということをお聞きいたします。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。髙橋総務部長。
○総務部長(髙橋聡)(登壇) 片平議員さんの再質問にお答えいたします。
時間外勤務が多い部署、少ない部署、その偏りがないのかということ、それからもう一点が、人員配置によってその辺の平準化を図れないのかという御質問だったかと思います。
確かに、多いところ、少ないところというのは、事業のボリュームにもよりますし、例えばその年度年度で大きな事業があったりする場合に変動はありますけども、若干部署によっての差異はあろうかとは思います。ただ、人員配置につきましては、各年度、各部局からの定員管理の申出といいますか、来年度こういう事業があるので、これだけの人数が必要なんだという申出を受けて、それを限られた人数の中ではありますが、適正に配置をすることによって、その事業を職員がそれぞれ業務を平準化して持てるような努力はしておりますので、結果的に全てが平準化されるかというと難しいところはありますが、そういう努力は続けておるところでございます。
○議長(小野辰夫) 再質問はありませんか。片平恵美議員。
○6番(片平恵美)(登壇) 情報提供数からお伺いをいたします。
管理職の情報提供数が、令和元年度55人だったのが令和5年度には203人になっているっていう、管理職って時間外労働としてはされてないから、仕事があったらあるだけ仕事をやってしまうということがあるんかなと思うんですけども、管理職の時間外労働が多いっていうことは本当に気になります。残業とか休日出勤をせざるを得ない状況というのは、御本人の健康はもちろんですけれども、今後管理職になっていただかなければいけない若い方とか、子育てと仕事を両立させたい女性たちが、管理職になることを決意する大きなハードルになっているんじゃないかなというふうに思います。
管理職の時間外労働についてどのように考えられているのか、特に兼務の問題、管理業務に集中できない、課長であって次長でもあるけど係長でもあるみたいな、そういう管理業務に集中できない状況というのがあると思いますが、どのようにお考えでしょうか。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。髙橋総務部長。
○総務部長(髙橋聡)(登壇) 片平議員さんの再質問にお答えいたします。
管理職が兼務等の状況により管理業務に集中できない、管理職の時間外についてどういうふうに考えているかというふうな御質問だったかと思います。
職員の年齢構成のいびつさがある程度ございまして、今現在、職員全体のバランスに比して、管理職が少し多くなっている状況ということは言えるかなと思います。そういう中で、副課長あるいは場合によったら、課長はあまりないんですけども、管理職が係長を兼務しておる状況というのが問題であるという認識はございます。今後、職員の年齢構成を平準化していくことに伴って、管理職と一般職員とのバランスをうまく取っていくことによって改善を図っていきたいというふうに考えております。
○議長(小野辰夫) 再質問はありませんか。片平恵美議員。
○6番(片平恵美)(登壇) 御答弁ありがとうございました。本当に職員さんの業務の内容は、複雑化、高度化していってテンポも速くなっているというふうにお伺いしております。責任も重いし、正規職員が減ってきた中で、日中は窓口業務に追われて残業しなければ仕事がこなせないが、子供や家庭のこともある。人が増えれば解決できることってたくさんあると思うんですよね……。(ブザー鳴る)
○議長(小野辰夫) 井谷幸恵議員。
○7番(井谷幸恵)(登壇) 日本共産党の井谷幸恵です。
古川市長、おめでとうございます。福祉の増進のため、よろしくお願いします。
通告に従って質問します。
次期ごみ処理施設の整備方針についてお尋ねします。
国の地球温暖化対策、2050年温室効果ガス実質ゼロ、カーボンニュートラル、プラスチック資源循環促進法2021年によって、日本の廃棄物行政、廃棄物処理の在り方は、焼却中心からごみの減量、資源化優先へと大きな転機が訪れております。しかしながら、ごみ処理施設の広域化を国や県が強力に推し進めてくる中、四国中央市、新居浜市、西条市で広域化の検討が始まっておりました。四国中央市は、令和5年、単独整備方針を決定したので、現在は西条市と本市で検討をされております。本市単独での整備か、2市広域化か、公民連携処理か、今年度末の3月までに決める予定とお聞きしました。9月議会で渡辺議員に対し、本市は焼却ごみゼロではなく、焼却、埋立方式を取るとの御答弁がありました。
以下、3点お尋ねします。
1点目、本市単独での整備についてです。
広域化が適当な地域もあるかとは思いますが、西条と新居浜は大変面積が広く、端から端までかなり距離がありますので、広域化には向かないのではと思います。自分の家にトイレがあるので、隣にトイレを借りに行く必要はありません。それと同じように、地域内のごみは地域内で処理するのが基本です。御所見を伺います。
2点目、2市広域化についてです。
例えば、西条市に建設する場合について3つお尋ねします。
1つ目、周辺地域の環境悪化などについてです。
新居浜からトラックで運ぶのは大変遠く、ごみ搬入車両の混雑や待ち時間の増など、搬出入車両の利便性について悪化するのではありませんか。
また、搬入車両が集中することによって、排気ガスが増えると思われますが、周辺地域における環境悪化についてはどのように考えていますか。
また、ごみステーションに残されたごみを自治会長さんなんかがボランティアでごみ処理センターまで運ぶ場合や自治会の清掃活動などで草やごみを持っていくときなどがあります。年末の持込みごみが多いときなどにも、近くにあるほうがよいのではないでしょうか。
2つ目、中継施設をつくる場合です。
中継施設とは、どのようなものなのでしょうか。建設費はどのくらいになりますか。
一旦新居浜市内の燃えるごみを中継施設まで運び、そこで下ろして、大きな10トントラックへ移し替え、そして西条の処理施設まで運ぶと言います。大きなトラックが排気ガスをまき、空気を汚します。環境に負荷がかかり、また土地代や建設費など余分な出費となるのではないでしょうか。
3つ目、災害のときについてです。
地震や豪雨などの災害のとき、大量の廃棄物が出ます。道路が寸断されると、運ぶこともままなりません。2市の災害ごみを処理できる能力はあるのでしょうか。やはり、それぞれの市に処理施設があったほうが、柔軟に対応できるのではないでしょうか。
最後の3点目です。
公民連携処理についてです。
これは民間委託です。焼却炉建設費用が高騰しており、この20年間に2倍以上になっている。自治体はメーカーの言いなりの価格で買わざるを得ず、地方財政の圧迫にさらに追い打ちをかけている。より複雑になった施設を管理するには、専門管理職員を抱えた管理会社に委ねるしかない。委託料の増大も財政を圧迫する。焼却炉メーカーが炉を販売し、同時に20年以上も自治体から維持管理費を通して莫大な利益を得る構造になっている。
以上が一般的であるというふうに承知しております。民間は、利益が出ないと撤退するおそれがあります。民間委託は、高コストになりませんか。今回、市が考えている公民連携処理とは、どのようなものでしょうか、お尋ねします。
古川市長は、市民に寄り添った市政づくりを公約されております。11月に本市で開催された自治研愛媛集会へのメッセージの中で、本市は大規模な植林事業など現在のSDGsにもつながる環境対策を100年以上も前から取り組んできたというふうに市長は述べられました。今回のごみ処理施設の整備も持続可能な社会に向けての観点が大事であると考えます。答弁よろしくお願いいたします。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。近藤市民環境部環境エネルギー局長。
○市民環境部環境エネルギー局長(近藤淳司)(登壇) 井谷議員さんの御質問にお答えいたします。
次期ごみ処理施設の整備方針についてでございます。
まず、本市単独での整備についてお答えいたします。
現在、人口減少、少子高齢化の社会を迎え、全国でごみ処理の非効率化が自治体の負担増となることが懸念されており、将来にわたって持続可能な廃棄物の適正処理を確保するためには、より一層のごみ処理の広域化及びごみ処理施設の集約化の取組が必要との考え方が趨勢となっており、本市と西条市の間においても、ごみ処理広域化について検討、協議を行っているところでございます。
ごみ処理施設の集約化は、これまでの調査においても処理の効率化が図られるなどのメリットがあり、実現の可能性がある手法と考えておりますが、各市単独での整備が優れている面もございますことから、2市の地域性等を含め、様々な視点からの評価を整理の上、今後の検討、協議において整備方針を決定してまいりたいと考えております。
次に、2市広域化についてでございます。
現在、新たなごみ処理施設整備についての方向性は決定しておりませんが、仮に西条市に広域施設を建設した場合には、本市に中継施設を整備することにより、利用される市民の皆様の利便性を確保するとともに、搬入車両の集中を分散し、施設建設地周辺地域への環境悪化についても防止することができるものと考えております。
中継施設とは、本市のごみ収集車や一般家庭等の直接持込み車両からのごみを受け入れ、大型車両に積替えを行う施設を想定しており、具体的事項が決定していないため、建設費はお答えできませんが、御指摘のとおり、一定の費用負担と環境負荷が生じるものと考えております。しかしながら、費用や環境負荷の面におきましては、施設を集約することにより得られる効果は非常に高く、総合的には中継施設整備によるデメリットを十分にカバーできるものと考えております。
また、災害時の災害廃棄物処理につきましては、災害の規模によっては大量の災害廃棄物の処理を被災自治体のみで行うことには限界があり、国や県、民間廃棄物処理業界など、広域的な連携協力体制の構築が必要となります。市の施設は、集約整備、単独整備にかかわらず、災害時に稼働不能とならないように強靱化を図るほか、災害廃棄物の処理も考慮した施設の整備を図らなければいけないと考えており、現在災害時の対応の観点も踏まえ、整備方針の検討、協議を行っているところでございます。
次に、公民連携処理についてでございます。
今回の検討において、選択肢の一つとなっております公民連携処理につきましては、新居浜市、西条市が行うべき一般廃棄物の処理に併せ、地域の産業廃棄物を処理する施設を一体的に整備することにより、大幅なスケールメリットを狙い、低コスト化、高効率熱回収を実現させ、一般廃棄物、産業廃棄物双方にメリットを生み出そうとするもので、施設の整備、運営は両市も関与する民間企業によるSPC、特別目的会社が行い、各市のごみ処理を委託する方式を想定しております。この方式においては、効率化による市の負担減、ごみ処理費用の平準化が図られるとともに、高効率エネルギー回収による地域還元のほか、本市民間事業者の産業廃棄物処理についても効率化が期待されるなどのメリットが考えられます。しかしながら、民間事業者の撤退リスクなど、懸念される事項もございますことから、引き続き慎重に検討を進めてまいりたいと考えております。
○議長(小野辰夫) 井谷幸恵議員。
○7番(井谷幸恵)(登壇) 質問1点。
この計画策定のスケジュールの中で、市民の声を聞くのはどのタイミングですか。
また、市民と共に計画を進めることが大切だと思いますが、御所見を伺います。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。近藤市民環境部環境エネルギー局長。
○市民環境部環境エネルギー局長(近藤淳司)(登壇) 井谷議員さんの御質問にお答えいたします。
施設整備に当たって、市民の皆様の声をお聞きするということについてでございます。
今現在、西条市とごみ処理施設の広域化について協議を進めておりますが、一定の方針が決定した段階で、市議会への報告の後、西条市と協議いたしまして、市民の皆様の御意見をお伺いする手法等について決定することになるというふうに考えております。
○議長(小野辰夫) 井谷幸恵議員。
○7番(井谷幸恵)(登壇) 御答弁ありがとうございます。
要望です。
市民の協力によってごみの減量、資源化を進めて、燃やすごみの量を減らせば小さくコンパクトな施設にでき、建設費用などを削減することができます。大いに市民への協力を訴えてください。例えば、家庭ごみの3割が水分を多く含んだ生ごみ。ぎゅっと絞るだけでもかなりの効果があるなどです。地球環境を守るという視点から計画を進めてください。
次に行きます。
2点目、教育現場の願いについてです。
長時間労働の是正について。
今全国で先生が足りません。教職を希望する人も減っております。平日は1日平均11時間半勤務し、土、日の勤務も当たり前、残業代は出ないとなれば無理もありません。教員の健康と家庭生活に大きな影響を与えているだけでなく、子供の教育にも深刻な影響を与えています。教材研究の時間が取れない、子供の話を親身に聞き、受け止める余裕がない、不登校やいじめなどへの対応の時間がないなどなど、長時間労働是正のために何をすべきでしょうか。
1つは、クラスの人数を欧米並みに25人から30人学級にする。2つは、きちんと残業代を払う。3つ、これが大事だと思うのですが、先生の授業を1日に4時間、すなわち4こま以下にすることです。週20時間以下です。以前は8時間のうち、4時間は授業と休憩に充て、あとの4時間は授業準備など授業以外の全ての仕事を終わらせるという計算で定数配置をしたとのことです。1992年の週休2日制からそれが崩れ、1日5こま、6こまが当たり前の体制になってしまいました。長時間労働にならざるを得ません。この3つの実現は、すぐには難しいですが、今の学校にとっては、ぜひとも実現すべきと考えます。教職希望者を増やすためにも必要です。
本市で週に1日だけ4こま、あと全て5こま、週24こま以上の先生はどのくらいいますか、お尋ねします。
長くPTAの活動などをされてこられ、教育に関して特別の思いを持っていらっしゃる市長の御所見を伺います。
次に、特別支援教育に携わる先生の増員についてです。
新居浜市は、以前から特別支援教育に関して手厚く手を差し伸べてきました。全国からたくさんの人が視察に訪れたとお聞きしました。特別支援教室は、各学校にあります。本市ではどのような種類の教室が幾つあり、何人の子供が学んでいるのか、教えてください。
情緒障害のクラスの定数は、以前は6人であったのが8人になったとお聞きしました。この背景についてお答えください。
定数が2人増えただけで、全く大変さが違うとお聞きしました。学年も違う、子供の特性もそれぞれ違う子供たち、通常のクラスとはまた違う大変さです。
情緒のクラスで7人あるいは8人のクラスは市内に幾つありますか。定数を6人に戻すことはできるでしょうか。
教室を歩き回る子、気持ちのコントロールが難しい子、不安が強く、集団に入りづらい子、こういった子供さんが増えてきたと言います。子供たちの安全のため、介助員の先生がクラスにいます。
配置基準はどうなっていますか。市内で何人いますか。大変なクラスには、介助員の先生を増やすことは可能でしょうか、お尋ねします。
通常学級にも発達など気になる子供さんはいます。クラスに8%以上いると言われております。本市では、学校支援員の先生が16人、通常のクラスで支援をしています。2つの学校を掛け持ちしている人もいます。
どういう配置になっていますか。長い年月をかけて少しずつ増やしてくださいました。今また一人一人に行き届いた教育のために、学校支援員の増員が必要です。先生たちの御要望、お聞きになっていますか、御所見を伺います。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。高橋教育長。
○教育長(高橋良光)(登壇) 教育現場の願いについてお答えいたします。
まず、長時間労働の是正についてでございます。
本市に勤務している教職員の週当たりの授業時数について、週24こま以上を受け持っている教職員の数は、小学校におきましては管理職を除くフルタイム勤務の常勤講師も含めて281人中137人、中学校におきましては、210人中8人となっております。教職員の長時間労働の背景には、授業時数に限らず、様々な要因が考えられますことから、引き続き働き方改革を推進し、教職員が働きがいのある学校現場の実現に向けて取り組んでまいります。
次に、特別支援教育に携わる先生の増員につい てでございます。
平成6年5月1日現在の市内小中学校における特別支援学級の種類、学級数、在籍児童生徒数につきましては、知的障害特別支援学級が31学級、142名、自閉症・情緒障害特別支援学級が47学級、279名、難聴特別支援学級が5学級、5名、肢体不自由特別支援学級が4学級、4名でございます。
次に、自閉症・情緒障害特別支援学級の編制については、本市においては、不登校やいじめなど、生徒指導上の課題や学力向上等各学校で抱える教育課題が様々であることから、義務標準法どおりの8人とし、これまで同様、支援の必要な子供たちに対し、手厚い対応を行いつつ、各学校で教員を柔軟に配置できるようにしております。
次に、自閉症・情緒障害特別支援学級において、1学級の児童生徒数が7人または8人の学級数は、合計19学級ありますが、先ほど申し上げました理由から、学級の編制の基準を6人に戻すことにつきましては、現在のところ考えておりません。
次に、学校生活介助員の配置基準につきましては、在籍幼児、児童生徒数や障害の特性、各学校の状況を勘案して、個別に判断しており、配置基準に基づく人員117名に対し、令和6年10月1日現在、110名を配置しております。
なお、不足数につきましては、今後も継続的に募集をしてまいります。
学校支援員につきましても、学校訪問や聞き取り等により、支援の内容や各学校の状況を勘案して配置しております。
先生方の要望につきましては、毎月学校支援員連絡会を開催し、各学校の状況を把握しております。
また、研修を重ねることで、一人一人のスキルアップを図るとともに、面談を実施しており、引き続き小学校の通常の学級に在籍する発達に課題のある児童の支援に努めてまいります。
なお、先ほどの答弁冒頭で、市内小中学校における特別支援学級の種類のところで、「令和6年5月1日現在」と申し上げるところ、「平成6年5月1日現在」と申し上げました。訂正しておわびを申し上げます。
○議長(小野辰夫) 再質問はありませんか。井谷幸恵議員。
○7番(井谷幸恵)(登壇) 先生たちの授業のこま数を減らすことについては、どのようにお考えでしょうか、お尋ねします。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。高橋教育長。
○教育長(高橋良光)(登壇) 井谷議員さんの再質問にお答えをいたします。
先生方の授業のこま数を減らすことについてどう考えるかということでございますけれども、これは学校に配置される教職員の数というのは、義務標準法という法律によって決められておりますので、こま数についてそれを減らしていくということについては限界があると。配置される先生の数によって決定されるものですので、市の教育委員会としては、それについて対策というものは打てない、要望していくというところになるかと思います。
○議長(小野辰夫) 再質問はありませんか。井谷幸恵議員。
○7番(井谷幸恵)(登壇) 御答弁ありがとうございました。
こま数を減らすことはなかなかまだすぐには実現はできないものとは思っております。かなり先生の数を増やさないとできないですね。だけども、そのことによって、物すごく先生たちの業務内容が軽くなると思います。
定数が6人から8人になって一番影響を受けたのは子供と先生たちです。ぜひ粘り強く何度も県へと要望を上げていただきたいと思います。
介助員の先生がいると、子供たちは落ち着くという声も聞いております。支援員の先生もぜひ増やしていただきたいと思います。
以上、要望いたしまして、終わりにします。ありがとうございました。
○議長(小野辰夫) この際、暫時休憩いたします。
午前11時57分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午後 1時00分再開
○副議長(伊藤嘉秀) 休憩前に引き続き会議を開きます。
理事者から発言を求められておりますので、これを許します。髙橋総務部長。
○総務部長(髙橋聡)(登壇) 片平議員さんの質問に対する答弁につきまして訂正をさせていただきます。
2番目、職員の配置についての再質問に対する答弁において、「時間外勤務命令は、紙ベースで所属長が行う」と言うべきところを「時間外勤務命令をデジタル上で申告をする」と申し上げました。訂正しておわびを申し上げます。
○副議長(伊藤嘉秀) 引き続き、一般質問並びに質疑を行います。神野恭多議員。
○11番(神野恭多)(登壇) みらい新居浜の神野恭多です。
本議会の初日、開会挨拶の中で、古川市長の思いを所信の一端という形でお聞かせいただきました。新しいにいはまに向け、常に挑戦する町、目指せ愛媛ナンバーワンのまちづくり、笑顔あふれる人に優しいまちづくりの3つのテーマには、18年間いちずに政治の道を歩んでこられた全てが込められているように感じ、本市の明るい未来に大きな希望を抱かせていただきました。さらには、公約の柱に、子育て支援の充実、地域経済の活性化、防災能力の強化の3つを据えて積極的に取り組んでいかれるとのことでしたが、とりわけ子育て支援の充実においては、四国で一番の子育て支援を掲げられ、見識の深さと覚悟を感じ取れます。
しかしながら、明るい未来への展望とは裏腹に、本市の財政状況は、財政構造が健全性と脆弱性という相反する2面性を持つ中で、貯金が少なく、借金も少ない異質な状況となっています。財政力指数や実質公債費比率、また将来負担比率、それらの各種指標は、健全であると思われます。また、近隣他市に比べると、市債残高や公債費負担が小さいので、将来世代の負担は小さく、持続力は持ち合わせていると思います。しかし、一方で、財政調整基金が極めて少ないことから、災害対策は言うまでもなく、新規事業展開などの対応に必要な瞬発力に欠けていると感じます。
このような状態や経過に対して、二元代表制の一翼を担う議決機関である議会の責任は非常に大きく、私を含めたここにいる議員一人一人が、この状況を真摯に受け止め、その上で今後の財政再建に積極的に、また協力的に取り組んでいかなければなりません。膨らみ続ける市民サービスに対し、効果効率性を改めて求められるタイミングであり、合併特例債が極めて少なかった本市が、近隣他市に先駆けて陥った危機として、歳入準拠の徹底により乗り切らなければなりません。
また、人口減少の深刻化とともに、人口動態の変化の現れ方は、自治体や地域ごとに異なりますが、老朽化により更新時期を迎えるインフラ、公共施設が一斉に増加するとともに、人口減少のさらなる進展に伴って、担い手不足や1人当たりで見た公共サービス維持のコスト増が顕在化する時代において、これまでどおりのかじ取りではなく、時代に即応し、大きな変化に対して消極的な方々に対し、変わらないために変わらなければならないもの、アップデートしていかなければならないものを強力に推し進めていかれると認識いたしますし、選挙戦においても、それが新居浜市民の大きな民意であると感じました。次の世代に自信を持って引き継げるよう、古川市長を先頭に推し進めていくことにより、市民の夢に市長の夢を重ね、さらに我々議員の夢も重ねることができるように願い、通告に従い質問をいたします。
今回は、市長に関わり合いの深い内容についてお伺いいたします。
初めに、アーティスト石村嘉成氏についてです。
石村さんは、本市在住の画家、版画家であり、現在はアクリル画をメインに、動物から昆虫、花まで命の輝きを描き続け、今にもキャンバスから飛び出してきそうな躍動感あふれる中に優しさを感じる作品を制作されています。2019年にはあかがねミュージアムにて個展「生き物たちも一生懸命」を開催され、期間中には公開制作も実施されました。この展示会には、累計2万人を超える来場者が訪れ、市内外から注目を集めました。また、昨年は、愛媛県美術館において、「いきものだいすき」が開催され、多くの方に感動を届けてくださいました。さらには、石村さんの半生を描いた映画「新居浜ひかり物語青いライオン」が公開され、生きる力を描く感動的な作品として高い評価を受けています。私も鑑賞させていただきましたが、涙が止まらない、本当に心温まる作品でありました。
このように、石村さんの活動は、新居浜市の誇りであり、また市の文化的な価値を高めるものです。
しかし、この活躍が全国的に広がる一方で、市として彼をどのように支援し、伴走していくのかが課題と考えます。
そこで、お伺いいたします。
古川市長は、議員の時代から石村さんの活動を深く理解し、伴走されてこられましたが、今後新居浜市長として、また新居浜市としてどのように歩みを重ねていくのか、御所見をお伺いいたします。
あかがねミュージアムでの個展をはじめ、多くの展覧会で大成功を収められておりますが、今後も市内で石村さんの作品を広く紹介する場を継続的に提供する計画はあるのでしょうか。例えば、彼の作品を学校や公共施設に展示する取組などが考えられると思います。さらには、新居浜駅を降りて本市を訪れた方が目にすることができるよう、駅周辺にアート作品を展示することなどにより、本市の誇るアーティストを強く応援するとともに、市民の方の理解の促進へとつなげていくことができると考えます。石村嘉成さんの活動は、個人の枠を超え、新居浜市全体の文化的価値を高めるものです。市として伴走支援を行う中で、今後新たな取組などがありましたらお聞かせください。
○副議長(伊藤嘉秀) 答弁を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) 神野議員さんの御質問にお答えいたします。
アーティスト石村嘉成氏についてでございます。
まず、今後石村氏の活動に市長として、市としてどのような歩みを重ねていくのかについてお答えいたします。
石村氏の活動は、年を追うごとに幅を広げられ、展覧会だけでなく、ライブペインティングやトークイベントの同時開催など、彼自身の魅力が伝わる取組が積極的になされています。私もこれまでの活動で石村氏を応援してまいりましたが、石村氏や作品から逆に励まされるなど、言葉では表すことのできない魅力や限りない可能性を感じているところであり、彼の魅力を多くの方にお伝えするとともに、本市のさらなる発展と重ね合わせ、共に歩んでまいりたいと考えております。
次に、今後も市内で石村氏の作品を広く紹介する場を継続的に提供する計画はあるかについてでございます。
これまであかがねミュージアムでの個展の開催、新居浜駅前シンボルロードでのアートフラッグ掲示、ワクリエ新居浜でのライブドローイング開催により、石村氏の作品を紹介してまいりました。現段階では、継続的な取組の計画はございませんが、神野議員さん御提案の学校や公共施設への展示等も含めまして、様々な皆様との連携を深めながら、石村氏の作品を広く紹介してまいりたいと考えております。
次に、市として伴走支援を行う中での今後の新たな取組等についてでございます。
石村氏の活動は、今や展覧会だけにとどまらず、アーティストと観客がライブ感や一体感を感じられ、リアルタイムで芸術と人がつながり共感できる場になっています。また、石村氏は、子供たちに大変人気があり、子供たちが芸術に直接触れることができる場にもなっています。
市といたしましても、そのような場がさらに広がるよう、石村氏のみならず、応援されている皆様と共に将来芸術家を目指す子供たちの夢への一助となる石村氏の芸術活動を後押ししてまいりたいと考えております。
○副議長(伊藤嘉秀) 神野恭多議員。
○11番(神野恭多)(登壇) 本市では、新居浜ふるさと観光大使である近藤勝也氏デザインの原付用オリジナルナンバープレートを選択制で交付していますが、石村さんの作品を取り入れたものも作製し、オリジナルナンバーは有料にするなど、財政面を考えた取組も可能かと考えます。
今後は、さらに様々な場面で様々な方が彼の作品に触れる機会が増えるとともに、これまで築き上げてきた市長と石村さんとの深い信頼関係の下、本市を代表するアーティストとして、世界に羽ばたき続けていただけることを期待し、次に行きます。
現在、愛媛県で自動車運転免許を新規取得する場合、試験を受けるために松山市の運転免許センターに行く必要があります。本市で免許を取得するには、この地理的条件は大きな負担となっています。特に、公共交通機関を利用して松山市まで行く場合、移動時間が数時間に及び、交通費も高額になります。少子高齢化が進む中、地方において自動車は日常生活を支える重要な交通手段です。そのため市民の免許取得をより容易にする環境整備が求められます。現在、市長が議員時代に深く関わってこられた新居浜警察署建て替えの設計が行われていますが、この機会に新施設内に免許試験会場を設置することができればと考えます。新居浜警察署、今治、八幡浜、宇和島では、免許の更新が即日交付できる機能を有していますが、この機能をもう一段階向上するための議論が必要と考えます。
さらには、近年、運転免許証とマイナンバーカードを一体化する取組が進められています。これにより、手続がオンライン化され、運転免許関連業務の効率化が期待されています。本市に試験会場を設け、こうした最新のデジタル技術を活用することで、市民の利便性向上に加え、行政の効率化も図れると思います。市としてこのような可能性について検討し、県へと要望できればと考えますが、御所見をお伺いいたします。
○副議長(伊藤嘉秀) 答弁を求めます。加地企画部長。
○企画部長(加地和弘)(登壇) 運転免許証新規交付窓口の誘致についてお答えいたします。
運転免許証の新規交付を行っている運転免許試験場につきましては、北海道や東京都のように、面積や人口規模が大きい一部の都道府県では、圏域内に複数のセンターが設置されている事例もある一方で、多くの県では、県庁所在地等に1か所のみセンターが設置されている状況であると認識いたしております。
神野議員さんの御質問を踏まえ、愛媛県運転免許センターに照会をいたしましたところ、運転免許学科試験については、学科試験予約システムによる事前予約となっており、受験生の利便性を図りながら、運転免許センターに集約して実施しており、現時点では新居浜警察署を含めた警察署において学科試験を実施する予定はないとの回答がございました。
このことを踏まえますと、残念ながら、今回いただいた御提案内容を実現することは難しいと考えておりますが、今後におきましても、国や県と連携、協議することで、市民の利便性向上や負担軽減につながる手続等がないか、調査、情報収集に努めてまいります。
○副議長(伊藤嘉秀) 再質問はありませんか。神野恭多議員。
○11番(神野恭多)(登壇) 免許の取得だけでなく、そこでしかできないという先入観により、それが当たり前になっているものが多々あると感じます。市長が関わり続けている共通テストも同様であります。気づかないうちに市民の方が不利益を被っていることが多々あるのかもしれません。このようなものも含め、新しい新居浜においては、過去からの延長線上ではない、人に優しいまちづくりを共に歩んでいきたいと考えますので、よろしく申し上げ、私の質問を終わります。
○副議長(伊藤嘉秀) 白川誉議員。
○12番(白川誉)(登壇) 自民クラブの白川誉です。
本議会は、古川新市長になられて初めての議会であります。私は、新市長とは、対立候補の方を支持させていただいた一人であります。今回の選挙結果、すなわち民意というものを私も真摯に受け止め、新居浜市のために今私にできることに尽力させていただきたいと改めて感じております。
新市長のキャッチフレーズは、はっきりイエス、はっきりノーとされており、対話を大切にすると強調されています。私も共感いたしますし、我々の共通の目的は、新居浜市を今以上によくする、発展していくことだと思います。また、選挙結果は、ゴールではなく、スタートだからこそ、これからの4年間、新市長の思いやお考えをしっかりとお聞かせいただきながら、よいものはよい、悪いものは悪いと是々非々で議論を深めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
選挙で支持してくれた方々へも、よくないものにはノーと言える市長、そうでなかった方々でも、よいものにはイエスと言っていただける市長であることを信じて、通告に従い質問させていただきます。
まず最初に、投票率の低下と原因分析について質問いたします。
今回の市長選挙においての投票率は45.48%でした。先ほど述べたように、民意は示されたということは間違いないのですが、有権者の半分以上が投票に行っていないという現実についても考える必要があると思います。ちなみに、投票権を持たない未来の新居浜市を担う子供たちの数を入れる、すなわち新居浜市民全体として換算した場合、市民全体の約38%の方々で市のトップ、新居浜市のかじ取り役を決めたとも言えます。約11万2,000人の市民のために働こうとしている古川市長のことを考えると、そうした意味では市民の現在の投票行動が及ぼす効果についても啓発する必要があると思います。これまでも投票率を上げるために、選挙に関心を持っていただくために、選挙クイズの実施や国領祭での模擬選挙の開催、さらには生徒会役員選挙の手引作成、夏の思い出総選挙の開催など、選挙管理委員会として様々な取組をされています。また、今回の市長選挙では、大型商業施設での期日前投票所設置も実施されました。選挙に行かないという選択肢も確かにありますが、関心がないから選挙に行かないのか、誰がなっても同じと思っているから行かないのか、市民生活において実感がない、影響がないから行かないのか、少し乱暴な言い方をすると、日常生活で困っていない方が、最大公約数的に多いから行かないのかなど、投票率の低下についての議論もずっと続けられています。
一方、選挙があることすら知らなかったという方が一体どの程度いたのか、選挙があることは認識できていたが、投票には行かなかったとしたら、その理由は一体何なのかなど、選挙では明確にされません。以前投票率向上についての市政モニターアンケートを実施されたことがあると思いますが、その結果を拝見しても、回答者の9割が投票に行っているという内容で、投票に行っている人目線でのアンケート結果となっています。マスコミの報道などによると、政治に対する無関心、行政に対する不信感、そしてそれらに対する諦めなどを理由に投票率が低下しているとされています。ただ、それらが全て臆測で今議論されているようにも感じます。答えは一つではないとは思いますが、今日は別の切り口で考えてみたいと思います。
それは、選挙に関わりたくないと思う人が増えてきているから投票率が上がらないという仮説です。例えば、自分の意思とは別にグループLINEを作られ、期日前投票の報告をさせられたり、候補者本人以外のところで行き過ぎた行動があったり、仮想の敵を作ってSNSで発信したりと、投票の自由、言論の自由はあるとはいえ、そこに直接的、間接的に関わった人たちが嫌気が差したり、恐怖を覚えたり、今回の市長選挙においても、私宛てにそんな感想やメールもいただきました。お子さんが困っていると親御さんからそんなやり取りが分かるLINEのスクリーンショットを見せていただきながら相談を受けたりもしました。これは、ほんの一部の方なのかもしれません。もしくは、ほかにもこのような話が多いのかもしれません。
そこで、選挙管理委員会として、匿名性を担保した上で、そのような選挙に関わりたくなくなった出来事や選挙に行きたくなくなったエピソードを市民の方から募集して、内容を公開してみてはどうでしょうか。情報の信用性や公開の方法など、実行するためのハードルが高いことは理解しておりますが、選挙に行かなかった理由や選挙に関わりたくない理由を市民の方へ幅広く公開することで、一定の抑止力になったり、一人で抱え込むことを防げるかもしれません。もし先ほど述べたようなことが理由で選挙に関わりたくない方々がいたとするならば、その方々は、これからも関わらない可能性が高いことは容易に想像できますし、市政に対しても興味を持っていただくどころか、余計に離れていくのではないかと危惧しています。新居浜市の地域課題や社会課題を市民みんなで考え、解決していくためにも、これまでの投票率を上げる取組に加えて、このような切り口を変えた取組を追加してみてはいかがでしょうか、御見解をお聞かせください。
○副議長(伊藤嘉秀) 答弁を求めます。藤田選挙管理委員会事務局長。
○選挙管理委員会事務局長(藤田和久)(登壇) 白川議員さんの御質問にお答えいたします。
投票率の低下と原因分析についてでございます。
全国的に投票率の低下が続いている厳しい状況の中、これまで高等学校等における啓発講座や模擬投票などの主権者教育、さらにはSNSなどを活用した積極的な情報発信、また買物に併せて投票ができる期日前投票所の開設など、政治、選挙に対する意識醸成や投票率向上の取組を進めてまいりました。
先月の新居浜市長選挙では、前回投票率を上回る結果とはなりましたが、有権者の半数以上の方が投票に来ていただけていないことにつきまして、選挙管理委員会としても危惧しているところでございます。
白川議員さん御提案の選挙に関わりたくなくなった出来事や選挙に行きたくなくなったエピソードの募集及び公開につきましては、匿名性や信用性が確実に担保できるのかなどの問題を考慮いたしますと、実施することについては慎重な判断が必要であり、現時点では困難であると考えております。
しかしながら、投票率の向上には、半数を超える有権者の投票行動に結びつかない要因について十分に分析を行い、その結果に基づいた対策を講じていくことがますます重要になってくるものと認識いたしておりますので、有権者の政治、選挙に関する意識、投票行動の実態と選挙に行かない具体的な理由など、まずは要因分析のためのアンケート調査の実施方法、分析結果の公表等について検討を進めてまいりたいと考えております。
○副議長(伊藤嘉秀) 白川誉議員。
○12番(白川誉)(登壇) ありがとうございます。投票率を上げる取組の答えは一つではないと思います。
一方、上げよう、上げようとするだけではなく、なぜ下がるのかの原因を探しつつ、下げないようにする取組も必要だと思います。
また、我々市議会議員選挙の投票率低下の現実も考えると、議員の質の向上もさることながら、市議会での議論や活動が、市民生活に影響を及ぼしているという実感を持ってもらう必要があるとも思います。できない理由を考えることなく、できる方法を考え、選挙に関するきめ細やかな市民の意識調査について実施していただくことを要望して、次の質問に入ります。
次に、市長選挙における公約について質問いたします。
古川市長は、さきの市長選で、人口減少や財政調整基金の減少、文化センターの建て替え問題などを新居浜市の課題として挙げられ、新しい新居浜を目指して幾つかの公約を掲げられ、多くの市民からの賛同を得て当選されました。
しかしながら、公約の具体的な中身がよく見えないまま選挙戦が終わったと感じている市民も多くおられますので、そのことを中心に質問いたします。
配付資料1と2を御覧ください。
こちらの資料は、古川市長が選挙のときに配布されました選挙運動用ビラの一部をそのまま転記したものであります。何事も最初が肝腎ですし、市民の皆様の疑問や不安を解消するために必要であり、古川市長の真意を市民の皆様へお示しするよい機会だと思いますので、あえて深掘りしてお聞きします。
まず最初に、財政再建について質問します。
市長は、選挙戦を通じて、一貫して新居浜市の財政調整基金、いわゆる貯金が減少しており、このままでは財政が破綻すると市民に危機感をあおっておられました。しかしながら、新居浜市の財政状況は、財政力指数をはじめとして、将来負担比率、実質公債費比率など愛媛県内でもトップクラスの健全性を維持しております。
このような状況下にもかかわらず、選挙公報には、市財政の危機、県議4期、市議1期の経験で再建と掲載されておりました。
まず最初に、古川市長の財政に対する考え方、価値観を教えていただいた上ではないと議論が深まらないと思いますので、大枠、土台の部分について質問します。
そもそも財政調整基金が少ないことと財政の危機、財政再建は根本的に異なるものであると私は考えますが、市長の御所見をお伺いします。
○副議長(伊藤嘉秀) 答弁を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) 白川議員さんの御質問にお答えします。
市長選挙における公約についてお答えいたします。
財政再建についてでございます。
財政調整基金の減少と財政危機、財政再建についてお答えいたします。
本市は、5年間にわたる実質単年度収支の赤字が示しておりますとおり、財政調整基金に依存した財政運営が続いていた結果として、当基金の残高が著しく減少した状態にあります。将来負担となる借金は少ない状況ではございますが、小中学校など老朽化した公共施設の更新費用や大規模災害等の不測の事態への迅速な対応、今後の社会情勢の変動による歳出の増加及び歳入の減少に対応できる十分な残高が確保できている状況ではありません。
このことから、健全化判断比率等の各種指標上は健全性を維持しておりますが、財政調整基金の確保という面では、財政状況は大変厳しく、財政基盤の脆弱性を内包しており、危機的な状態であると認識しております。そのため、歳入の確保と歳出の抑制に努め、持続可能な財政状況を維持できるよう、財政再建に取り組むことで、一定の財政調整基金残高の確保に努めてまいる所存でございます。
○副議長(伊藤嘉秀) 白川誉議員。
○12番(白川誉)(登壇) ありがとうございます。大枠の話をお聞かせいただきましたが、少し私の認識とは違いますので、幾つか質問させていただきます。
自治体の運営というのは、入るを量っていずるを制す、すなわち収入に合わせて支出を考えるという地方財政の運用の基本原則であり、明治維新後、西郷隆盛もその遺訓の中に書き留められている有名な教えであります。そもそも財政再建とは、地方自治体の財政において債務、いわゆる借金を返済し、収支のバランスを取って、赤字財政を健全な状態に戻すことと定義されています。また、財政の危機とは、行政が税収を大幅に超える支出を続けることによって、財政赤字が累増、増えていくことだと私は認識しています。私はこれまでの新居浜市の行政運営は、未来の新居浜市を担う子供たちへのしわ寄せとならないよう、極力借金をせず、貯金を取り崩しながらバランスを取って運営していたものだと認識しています。財政調整基金、いわゆる市の貯金が少ないことだけが注目されていますが、市の財政状況を現状分析するためには、財政調整基金を把握し、合併特例債を含めて議論するべきだと考えます。
合併特例債とは、約20年前、平成の大合併で合併した市町村が新しいまちづくりのために事業費に対し95%まで借り入れることができる地方債で、70%が普通交付税の基準財政需要額に算入することができる制度です。つまり、1億円の事業が3,300万円余りで実施できる有利なものです。ちなみに、合併特例債の発行可能額は、合併の規模に応じて額が決まりますので、小規模の合併であった新居浜市の合併特例債は約116億円、人口規模が近いお隣の西条市は約440億円、四国中央市は約422億円でした。ということは、合併特例債の70%は、市の財産に入ったと考えたとき、新居浜市は約77億円の貯金上乗せからスタート、西条市と四国中央市は、約280億円から約290億円の貯金上乗せからスタートしたことになります。この視点に加えて、ここでは数字を控えますが、西条市と四国中央市の現在の財政調整基金、いわゆる貯金や借金の残高、さらには市税収入を合わせて多面的に考えたとき、新居浜市はこの20年間、健全財政を維持するために、借金の残高を抑制し、借金の代わりに貯金の取崩しを行ってきた結果、愛媛県内でもトップクラスであり、全国的に見ても優良な財政状況につながったと私は考えます。
また、これからの人口減少を考えたとき、備えあれば憂いなしの精神で、財政運営していく必要があるとは思いますが、だからこそ、財政状況の一部を切り取るのではなく、危機的な状況であると否定から入るのでもなく、多面的に考え、新居浜市をこれまで築き上げてくれたことに対して、この状況、この土台をつくってくれたことに対する感謝の気持ちが必要であると私は考えます。
そこで、改めてお伺いしますが、新居浜市は、本当に財政の危機なのでしょうか、御所見をお伺いします。
○副議長(伊藤嘉秀) 答弁を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) 白川議員さんの御質問にお答えをいたします。
議員さんがお伝えしていただいたとおり、財政運営の基本は、入るを量りいずるを制すということが大切だと思い、やはり入るものの拡大と出ていくものの縮小というものを考えていかなければならないというふうに私も思っています。
そんな中で、私は財政調整基金に着目をしていったわけでありますけれども、財政調整基金が減っている現状というのは、社会情勢ということもありますが、やはり出ていくものが今大変多い状況になっている。新居浜市の収支のバランスが崩れているから、切り崩さなければならない現状があるというふうに私は認識をしております。そのことが、実質単年度収支の赤字ということにつながっておりますし、実際に平成16年の台風のときよりも財政調整基金が少ないといった状況だというふうに認識しておりますので、そういったことも含めて、財政状況は大変厳しいというふうな思いであります。
○副議長(伊藤嘉秀) 白川誉議員。
○12番(白川誉)(登壇) ありがとうございます。ということを踏まえた上で質問させていただくんですけども、選挙のチラシのほうを拝見させていただきますと、その場しのぎの財政再建が課題であり、多くの補助金がカットされたことが書かれています。これは、その補助金をカットしたことがその場しのぎの財政再建ということなのでしょうか、お伺いします。
そして、2点目、こんなことを申し上げるのは釈迦に説法とは存じますが、予算については、財政課が担当課に対して全事業のヒアリングを行い、その必要性や成果等を評価し、最終的には市長以下で査定し、予算編成されています。その後、予算案が市議会に提案され、議会では予算特別委員会で何日もかけて審議し、賛成多数で予算が成立しております。そもそも補助金というものは、義務的な補助金を除き、公募補助金の場合であれば、期間は3年までとなっており、その間に自立し、終了するのが原則となっています。また、団体への運営補助については、団体の財政状況等を考慮して、減額する場合もあると認識しています。
そのような中での適正かつ現実的な予算提案だったと私は予算特別委員会でも賛成をさせていただいたのですが、めり張りのないばらまき行政とか、その場しのぎの財政再建などと言われるのは、石川前市長や市の職員、さらには予算を通した市議会議員に対しても古川市長が大切にすると言われてます優しさが足りない言い方と思いますが、どの事業がばらまきだったのかも含め、そのことに対する御所見をお聞かせください。
○副議長(伊藤嘉秀) 答弁を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) 御質問にお答えいたします。
その場しのぎの財政再建に関することだというふうに思いますが、やはり私自身は、財政が苦しくなってきて、大きくシーリングをかけて、予算そのものを減らしたということに関しては賛成をしかねるものであります。やはり、政策としてめり張りをつける、必要なものと必要でないものをしっかりと考えていくということが重要だろうというふうに思っていますので、そういった意味では、やはり私から見るとその場しのぎであったのかなと、数字合わせのカットになってしまったんではないかなというふうに思っています。
そして、どのような部分がばらまきかという御質問に関しましては、まさに今、私自身も市長になって間もないですが、いろんな各部署からお話を聞きながら、当初予算に向けて今後考えていきたいというふうに思っております。
○副議長(伊藤嘉秀) 白川誉議員。
○12番(白川誉)(登壇) ありがとうございます。まずは、古川市長の財政に対する考え方、そして価値観をお聞かせいただきました。
次は、公約の中身について個別に質問させていただきます。
最初に、子育て支援についての公約について質問します。
先ほどお伺いした新居浜市の財政と市民サービスというのは直結していると思います。当たり前の話ではありますが、市民サービスには全てお金がかかります。要は、市民の皆様へお約束する公約というものは、市の財政状況、お財布事情というものを一面的ではなく多面的に理解、把握した上で、財源の根拠ある説明が必要であると考えます。
古川市長の公約では、四国で一番の子育て支援を一番に掲げ、給食の無償化や新生児スクリーニング検査の補助、学習室がある図書館の設立と書かれています。また、子育て支援センターの設置や独り親世帯への支援など、財政の危機と財政再建を公約としながら、歳出、いわゆる出ていくお金が増加する公約内容となっています。
市長は、就任式で市の職員さんに対して、財政健全化や財政調整基金の確保などに努めた上で、子育て環境の充実などに取り組みたいと語られたと新聞に出ておりましたが、この公約を実現するためには、かなりの財源が必要となり、矛盾するのではないかとも思います。新居浜市が四国で一番の子育て支援の町となることは、私も願っていますし共感もします。ただ、これらの実現性についてどのように考えているのか、どのようにして公約の実現と基金の確保をされるおつもりなのか、具体的に教えてください。
また、魅力的な図書館の設立とありますが、現在の別子銅山記念図書館は、1992年に別子銅山開坑300周年を記念に住友グループから寄贈されたものであります。新居浜市と住友グループの共存共栄のあかしであるこのすばらしい図書館とは別に新たに設立するというお考えでしょうか、御所見をお伺いします。
○副議長(伊藤嘉秀) 答弁を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) 子育て支援についてお答えいたします。
まず、四国で一番の子育て支援の町の実現についてでございます。
四国で一番の子育て支援の町の実現は、私の市長公約の中でも重要な柱の一つであり、教育環境の充実や子育て世代が安心して暮らせる施策に取り組んでいきたいと考えております。
これらの実現性につきましては、新たな予算措置が必要となる施策もあることから、まずはこれまでの関連事業の取組実績を踏まえ、本市に必要と考える施策に関する枠組みや実施規模、優先順位等の精査を進めていきたいと考えております。
また、公約の実現と財政調整基金の確保につきましては、各施策の実施に向けた検討において、充当可能な財源を幅広く求めることで、過剰な基金への依存を抑え、基金を確保しつつ、めり張りのある行財政運営を図ってまいります。
こうした考え方を基本とし、実現可能なものから順次、取組を進め、公約に掲げる四国で一番の子育て支援の町の実現に向け、市民の皆様の意見や議会の皆様の御助言も踏まえ、一歩一歩取組を進めてまいりたいと考えております。
次に、魅力的な図書館の設立についてでございます。
私は、今年の夏、高知県と高知市が共同運営するオーテピア高知図書館に行ってまいりました。この図書館は、声と点字の図書館、高知みらい科学館も備えた複合施設オーテピアに入っており、にぎわいの拠点施設になっています。また、館内は、様々な工夫が凝らされ、サービスもきめ細かく、図書館に足を運んだことのない人でも楽しめる施設であると感じました。
本市にも、住友グループから御寄贈いただいた別子銅山記念図書館がございます。すばらしい建物、充実した蔵書により、市民の皆様に読書に親しんでいただくことはもちろんのこと、本市発展の歴史も後世へとつなぐ役割のある図書館であると認識しております。
こうしたことから、市民の皆さんにより身近に感じてもらい、子供たちも気軽に利用できる、誰もが訪れたくなる魅力的な図書館を目指し、利用しやすい環境を整えてまいりたいと考えております。
○副議長(伊藤嘉秀) 白川誉議員。
○12番(白川誉)(登壇) ありがとうございます。ちょっと質問をお願いします。
古川市長の公約を実現するためには、新たな予算措置が必要であるという御認識があることは理解しました。先ほどの答弁の中で、本市に必要と考える施策に関する枠組みというのがあったんですけども、この施策に関する枠組みというのはどういうことでしょうか。もう少し具体的に教えてください。
また、その充当可能な財源を幅広く求めるというふうにありましたが、これはその子育て支援の公約を実現するために、ほかの部局、例えば経済対策予算や福祉予算からも財源の捻出を求めていくということでしょうか、お聞かせください。
○副議長(伊藤嘉秀) 答弁を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) 白川議員さんの御質問にお答えをいたします。
本市に必要と考える施策に関する枠組みということですが、もちろんそれはこれまで行ってきたものも含めて、どのような予算の大枠を決めていくのかということになろうかというふうに思っております。
そのような中で、その枠組みを広げるのかとか、現状維持するのか、またもしくは狭めていくのか、そういったことを考えていきたいと思います。
また、充当可能な財源を幅広く求めるということに関しては、それは今ある予算だけではなくって、国や県が持っているメニューなども使いながら、活用しながら行ってまいりたいというふうに思っています。
○副議長(伊藤嘉秀) 白川誉議員。
○12番(白川誉)(登壇) ありがとうございます。
先ほどオーテピア高知というお話あったんですけど、すごくすてきな施設だと認識しているんですが、古川市長の公約に、魅力的な図書館を設立とありましたので、別子銅山記念図書館とは別に新たに設立するお考えなのかというのを伺ったつもりだったんですけど、曖昧な答弁だったので、再度確認のため伺います。
オーテピア高知のような図書館を複合化するなど、ハードとソフト両面を充実させて魅力を出そうとされているのか、図書館単体としてソフト面を充実させて魅力を出そうとされているのか。要は、これらを新たに設立するっていうお考えなのか、もしよろしければお聞かせください。
○副議長(伊藤嘉秀) 答弁を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) 図書館の設立という部分だろうというふうに思います。
私自身、オーテピアに行って、多くの方が来場する様子、利用する様子やまたその来場者数というものを見て、図書館が本当に集客施設になり得るんだという可能性について感じさせていただきました。
そのような中で、新居浜市の現状は、今別子銅山記念図書館があります。それを新たに別に造るというイメージよりは、その設立というのはもっと広義な意味で、みんなが使いやすく、言葉にするとすごく難しいですが、広義な意味での設立と捉えていってほしいと思います。なので、デジタル化であったりとか、もっと幅広く皆さんが借りやすい仕組みづくりというものも含めたものであると理解していただけたらというふうに思います。
○副議長(伊藤嘉秀) 白川誉議員。
○12番(白川誉)(登壇) あと一点、すみません。
御答弁にありました四国で一番の子育て支援の町としてその公約の目玉でありました仮称子育て支援センターについて少し詳しくお聞きしたいんですけど、今後の急患センターについて、今年の2月に担当部局から説明を受けた際には、新文化センター建設に伴う市役所周辺施設の整備と併せて、現在の急患センターの土地を先行取得するというふうに説明を受けてました。これは、新文化センターの計画に入っていないあすなろ教室や発達支援センターを含めた子育て支援施設との複合施設だと私は理解してたんですけども、そんな中、今回の補正予算で再度上げられている債務負担の土地、その現急患センター東側の土地というふうにお聞きしているんですけども、同様に、急患センターの建て替え等に伴う先行取得との説明でした。この等とは、あすなろ教室や発達支援センターということでいいんでしょうか。公約の子育て支援センターがここに建てられるという理解でいいのか、土地を先行取得するということは、当然利子も発生しますので、もし違うのであれば、この等というのは何を意味するのか、教えてください。
○副議長(伊藤嘉秀) 答弁を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) 私もその件についてはお話を伺ったばかりであり、等というのは、もちろん検討中という意味であるというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
○副議長(伊藤嘉秀) 白川誉議員。
○12番(白川誉)(登壇) ありがとうございます。
それでは、地域経済の活性化と新たな財源確保について質問します。
古川市長は、公約の中で、新居浜版営業本部の設置と市長が本部長となりトップセールスを行い、新たな地域経済の活性化を図るとあります。このことについても私は共感しますが、具体的にどのようなものをトップセールスするおつもりなのでしょうか。
また、この市長任期4年間で目標金額、いわゆる成約金額は、どのぐらいを目標とされていますでしょうか、御所見をお聞かせください。
また、新たな財源確保という意味では、市長がトップセールスを行い、ふるさと納税を獲得することも重要な取組の一つだと考えます。現在の新居浜市のふるさと納税は、市内事業者の皆様の御尽力もあり、制度が開始された2008年の初年度176万5,000円から現在では約5億5,000万円で推移しております。
一方、新居浜市は、大型の加工品が多く、最終製品が少ないことや農産物などの1次産品も少ない特徴があり、ふるさと納税の返礼品にも苦慮している現状もあります。地域経済の活性化、そして営業は数字、結果が全てとまでは言いませんが、トップセールスとうたわれている以上、成果は数字として評価されると思います。古川市長のふるさと納税の返礼品についてのお考えとふるさと納税の目標金額を併せてお聞かせください。
○副議長(伊藤嘉秀) 答弁を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) 地域経済の活性化とふるさと納税についてお答えいたします。
具体的にどのようなものをトップセールスするのかにつきましては、別子銅山の開坑から今日まで、綿々とつながり発展してきた産業、歴史、生活文化、行政施策など、新居浜市独自の町の魅力を国内外へと営業活動してまいりたいと考えておりますが、中でも税収の増加に直結する企業版ふるさと納税や企業誘致、ふるさと納税に係るものを喫緊の課題としてトップセールスに努めてまいります。
市長任期中の成約金額の目標につきましては、まずは現状分析を行うところから始め、町のブランドコンセプトを明確にしていく中で、数値目標についても定めてまいりたいと考えております。
ふるさと納税の返礼品につきましては、地元事業者を支援することにより、既存商品のブラッシュアップや複数商品の組合せによるラインナップの充実、ものづくりのまちの技術や高校生など若い世代のアイデアを生かした新規返礼品の開発、宿泊、飲食、サービス等を組み合わせた体験型返礼品の造成などに努めてまいります。
目標金額につきましては、刻々と変化するふるさと納税市場の状況分析やトレンドに対応していく中で、適切な目標数値を定め、寄附額向上に取り組んでまいります。
○副議長(伊藤嘉秀) この際、暫時休憩いたします。
午後 1時56分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午後 2時05分再開
○副議長(伊藤嘉秀) 休憩前に引き続き会議を開きます。
白川誉議員。
○12番(白川誉)(登壇) ありがとうございます。
成約金額の目標金額もふるさと納税の返礼品の目標金額についても具体的な答弁がありませんでしたので、すいません、質問させていただきます。
私は、これからの時代は、行政にも民間の感覚を入れていただきたいと願っておりますが、民間の感覚からすると、経営者を替えようとするとき、経営者が替わる前には、既に現状分析は終えて、経営者が替わったときには、具体的なアクションプランと数値目標を示し、従業員や協力業者の理解を得ながら一丸となって取り組むものだと思います。しかしながら、その現状分析はこれからということですが、例えば国が提供している地域経済分析システムのRESASを活用して、製造品出荷額や産業別の付加価値額をどうするかとか、新居浜市の観光入り込み客数の約80%と言われている200万人のビジネス客に対してのアプローチをどうするかとか、具体的にどのように現状分析をされるイメージでしょうか。
そして、具体的にいつまでにトップセールスによる金額の目標を決められる御予定でしょうか、お聞かせください。
○副議長(伊藤嘉秀) 答弁を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) 数値目標を具体的にというお話であろうかというふうに思います。
私自身、勉強不足ということもありましたので、実際に中に入ってみて想定と違っていたということも多々あります。そのような中で、今職員の皆様と対話をしながら、ある一定の時期、できれば春までには数値目標をしっかりとお示ししたいというふうに思っております。
○副議長(伊藤嘉秀) 白川誉議員。
○12番(白川誉)(登壇) ありがとうございます。春までにということがありました。公約にもあります新居浜版営業本部を設置することは、私も共感いたしますし、行政も民間の感覚を持って、民間事業者の方にもうけてもらって税収を増やしていくというマインドの下、早期の設置とそれに合った施策というものを進めていただくことをお願いして、次の質問に入ります。
最後は、ワクリエ新居浜について質問します。
ワクリエ新居浜は、感性を育みわくわくを創造するをコンセプトに、歴史を活かし記憶をつなぐゾーン、感性をはぐくむゾーン、学びを深め創造するゾーン、新たな出会いと発見を生み出すゾーンの4つのゾーンを設け、人生100年時代を見据えて、子供から大人まで、自分にとってのわくわくを発見し、関わり、創造することができる多目的複合施設です。2018年3月に閉校となった私の母校でもあります旧若宮小学校を利活用した施設として、2021年6月1日にワクリエ新居浜としてオープンしてから約3年半が経過しました。オープン前の地域での検討委員会の開催を含めて、様々な方々のお力をいただき、地域の宝であった旧若宮小学校を生まれ変わらせていただき、改めて感謝いたします。
ここで、この3年間を簡単に振り返ってみたいと思います。
配付資料3を御覧ください。
利用者数については、初年度はコロナ禍もありましたが、5万5,379人の利用者、2年目は目標6万人に対して10万2,316人の利用者に、3年目は目標10万人に対して11万3,774人の利用者となりました。
リカレント事業としての講座開催については、毎月開催され、自主事業についても共催事業と合わせて年間70を超える事業が展開されるようになりました。
また、有料のコワーキングルームの利用者は、年間約3,000人と目標値を達成し、レンタルオフィスのKPI指標についても、入居者売上げが500万円を超えるなど、順調に成果が出始めています。
ちなみに、新居浜市の公共施設白書の施設概要書から公共施設の利用者の多いものを調べてみますと、マイントピア別子と別子銅山記念図書館は年間約23万人、あかがねミュージアムは約21万人、市民文化センターが約14万人、新居浜マリーナが約13万人、市民体育館が約10万人となっています。このことからも分かるように、ワクリエ新居浜は、市民の皆様から愛されている市民体育館と同規模の利用者となっており、この結果は、指定管理者である株式会社ハートネットワークが中心となり、市民の方や個人事業主、企業や団体、大学など、多くのステークホルダーとの関わりを持ち、連携、協業による新たな取組や相乗効果が発揮された結果であると感じています。と同時に、地域との関係性も良好で、地元自治会との定期ミーティングの開催や公民館の運営審議会にも毎回参加していただいており、合同文化祭の開催や太鼓台の展示、旧若宮小学校時代から地域の課題であった落ち葉問題を自治会と一緒に解決することにつながるなど、地域との触れ合い活動も大切にしていただいており、地域にはなくてはならない存在になっています。
事業の評価というのは、利用者数や予算額など目に見えるものは当然大切ですが、人生の先輩方が培ってくれた若宮小学校の文化継承や近隣住民の皆様との日々の関わり度など、目に見えにくいものも併せて評価することが大切であると考えます。
そこで、質問します。
オープンしてから約3年半が経過したワクリエ新居浜について、これまでの3年間を行政としてどのように評価されていますでしょうか。目に見えるもの、目に見えにくいものも併せてお聞かせください。
また、今年度の進捗状況はいかがでしょうか。今年度から定期開催のワクリエわくわくマルシェも始まり、さらににぎわいの創出となっていると感じていますが、こちらの効果と事業評価も併せて教えてください。
一方、グラウンドの水はけが悪い課題や今年の決算特別委員会でもお約束させていただきましたが、現在、学校給食のセンター化に伴い、市内全校で進めている地域防災施設整備事業との平等性の担保など途中段階の案件もありますが、こちらの進捗状況もお聞かせください。
○副議長(伊藤嘉秀) 答弁を求めます。加地企画部長。
○企画部長(加地和弘)(登壇) ワクリエ新居浜についてお答えいたします。
まず、3年間の評価と今年度の進捗状況についてでございます。
ワクリエ新居浜につきましては、生涯活躍のまち拠点施設として、令和3年6月に供用開始以来、貸し館事業のほか、資格取得に向けた講座やセミナーの開催など、生涯活躍に向かってチャレンジする方を支援するとともに、市や地元企業、周辺施設と連携したイベントの開催など、多岐にわたる事業展開により、市内外の多世代の多くの方に御利用いただいております。
そのほか、地域との良好な関係性の構築にも努めており、地域からも愛されている施設であると考えております。
今年度の進捗状況につきましては、これまでと同様の事業のほか、新たにビジネスアイデアコンテストや異業種交流会を開催するなど、10月末時点で約9万人の方に御利用いただいております。
次に、ワクリエわくわくマルシェの効果と事業評価についてでございます。
今年度から開催しておりますマルシェにつきましては、キッチンカーや各種体験コーナーのほか、コンサートやマジックショーを企画するなど、多くの皆様に来場していただいており、新規利用者の獲得や市民の方の活躍の場の創出にもつながっているものと考えております。
次に、グラウンドの水はけの対応状況につきましては、指定管理者において、利用者に対し利用後の整備の徹底を呼びかけるとともに、定期的に土を入れてならすなどの対応をいたしております。
○副議長(伊藤嘉秀) 小澤市民環境部危機管理監。
○市民環境部危機管理監(小澤昇)(登壇) ワクリエ新居浜の地域防災施設整備事業との平等性の担保についての進捗状況についてお答えいたします。
地域防災施設整備事業は、小学校の給食室を防災備蓄倉庫と給食配膳室に改修する事業であり、ワクリエ新居浜への防災備蓄倉庫の整備につきましては、まずは現在の倉庫へ引き続き物資を備蓄してまいります。
しかしながら、スペースの関係上、物資の拡充によって物資の収納が難しくなることが考えられますことから、今後整備に向けての協議を行ってまいります。
○副議長(伊藤嘉秀) 再質問はありませんか。白川誉議員。
○12番(白川誉)(登壇) ありがとうございます。若宮小学校が閉校になったときは、卒業生として残念な気持ちにもなりましたが、ワクリエ新居浜に生まれ変わり、この場所は住友グループのお膝元に立地し、大型商業施設が近隣にあるなど、各産業界の事業所が広く活動する地域であるため、本市の生涯活躍のまち拠点施設を整備するに適した立地であったと今ではうれしい気持ちと感謝の気持ちでいっぱいです。
先月、ワクリエ新居浜で行われた若宮校区の文化祭では、住友化学さんによる理科教室や新居浜工業の学生さんによるロボット教室を出前講座として提供していただきました。
これからも様々な連携や協業などを通して、ワクリエ新居浜が中心となり、地域、そして新居浜市内全体がわくわくするような施設へのさらなる進化に向けて、我々地元住民の皆さんとも頑張ってまいりますので、これまでと同様に行政からのバックアップをお願いいたします。
結びになりますが、最後に、新市長にお願いしたいことを申し上げます。
公約と議会対応、そして説明責任を大切にする市長であり続けていただきたいと思っています。
公約については、選挙で主張した市民とのお約束であり、政治家にとって最も大事な約束です。
議会対応については、市議会は二元代表制ですので、市長と議会の意見が異なることは当然出てくると思います。
説明責任について言えば、御自身の予算案を提出し、丁寧な説得を行い、それでも否決されれば、その経緯を含めて市民の皆様に説明責任を果たすべきだと思います。
他市ではありますが、市長選挙で耳障りのよい政策や財源の根拠のない公約と懸念されていた中でも、市民がその公約を信じて当選されたにもかかわらず、翌年度の予算案には公約のいずれも盛り込まれることなく、市民が失望することになったり、公約を守れなかった理由を市長になって初めて分かることもある。公約を100%実現する候補者はいないなどと市民との約束放棄を合理化してしまったことで全国ニュースでも問題視されることがありました。
新居浜市長は、市民の皆様からの税金、県や国からの交付金などを含めて約500億円の予算、そして職員約1,500名をお預かりされている立場です。市民の方は、公約を期待して一票を投じました。市役所職員さんも生活があり、家族がいます。市長は、市民の代表であり、市役所職員の代表でもあります。だからこそ、公約と議会対応、そして説明責任を大切にしていただきたいと思います。結果的に市民の皆さんを失望させ、職員を混乱させることのないよう、そして他市のような市のブランド価値が下がるようなニュースになることのないよう、新居浜市のかじ取り役をよろしくお願いいたします。
先ほども述べましたが、今回の質問は、何事も最初が肝腎であること、市民の皆様の疑問や不安を解消するためにも必要であり、古川市長の真意を市民の皆様へお示しするよい機会だと思いあえて深掘りしてお聞きしました。もし私の質問内容で失礼なことがありましたらおわびいたしますが、古川市長をはじめ、最後まで真摯に受け答えをしていただきました理事者の皆様へ感謝いたします。
私も新居浜市のために今できることを尽力させていただくこと、そして敵とか味方とか、あっち側、こっち側とかどうでもよい議論ではなく、中身を是々非々で議論していくことをお約束して、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。
○副議長(伊藤嘉秀) 以上で本日の一般質問並びに質疑は終わりました。
これをもって本日の日程は全部終了いたしました。
明12日は午前10時から会議を開きます。
本日はこれにて散会いたします。
午後 2時20分散会