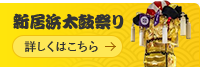サイト内検索
本文
令和6年第5回新居浜市議会定例会会議録 第2号
目次
議事日程
本日の会議に付した事件
出席議員
欠席議員
説明のため出席した者
議会事務局職員出席者
開議(午前10時00分)
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 一般質問 議案第77号~議案第80号
大條雅久議員の質問(1)
1 新しいにいはまについて
(1) ふるさと新居浜
(2) 若者の居場所
(3) 地方創生
古川市長の答弁
1 新しいにいはまについて
(1) ふるさと新居浜
(2) 若者の居場所
(3) 地方創生
大條雅久議員の質問(2)
1 新しいにいはまについて
2 小中学校体育館へのエアコン設置について
古川市長の答弁
2 小中学校体育館へのエアコン設置について
大條雅久議員の質問(3)
2 小中学校体育館へのエアコン設置について
3 公共交通の在り方について
(1) 通院バス、お買い物バス
(2) デマンドタクシー
古川市長の答弁
3 公共交通の在り方について
(1) 通院バス、お買い物バス
(2) デマンドタクシー
大條雅久議員の質問(4)
3 公共交通の在り方について
古川市長の答弁
3 公共交通の在り方について
大條雅久議員の質問(5)
3 公共交通の在り方について
4 奨学金返済支援事業について
加地企画部長の答弁
4 奨学金返済支援事業について
大條雅久議員の質問(6)
4 奨学金返済支援事業について
加地企画部長の答弁
4 奨学金返済支援事業について
大條雅久議員の質問(7)
4 奨学金返済支援事業について
5 地域コミュニティーの活性化について
(1) 協議会型地域運営組織
(2) 2024年地方自治法改正
長井市民環境部長の答弁
5 地域コミュニティーの活性化について
(1) 協議会型地域運営組織
(2) 2024年地方自治法改正
大條雅久議員の質問(8)
5 地域コミュニティーの活性化について
休憩(午前10時53分)
再開(午前11時04分)
篠原茂議員の質問(1)
1 新しい新居浜について
(1) 市政運営に対する思い
(2) 財政状況
(3) 市民への情報発信と対話型行政
(4) 独自政策
(5) 職員の意識改革
(6) 郷土愛の育成
(7) 経済対策
古川市長の答弁
1 新しい新居浜について
(1) 市政運営に対する思い
(2) 財政状況
(3) 市民への情報発信と対話型行政
(4) 独自政策
(5) 職員の意識改革
(7) 経済対策
高橋教育長の答弁
1 新しい新居浜について
(6) 郷土愛の育成
篠原茂議員の質問(2)
1 新しい新居浜について
2 これからの公民館について
(1) 地域づくり活動センター
(2) 人材配置
(3) 公民館版SDGs
竹林教育委員会事務局長の答弁
2 これからの公民館について
(3) 公民館版SDGs
長井市民環境部長の答弁
2 これからの公民館について
(1) 地域づくり活動センター
(2) 人材配置
篠原茂議員の質問(3)
2 これからの公民館について
長井市民環境部長の答弁
2 これからの公民館について
篠原茂議員の質問(4)
2 これからの公民館について
長井市民環境部長の答弁
2 これからの公民館について
篠原茂議員の質問(5)
2 これからの公民館について
3 農業振興地域について
宮崎経済部長の答弁
3 農業振興地域について
高橋建設部長の答弁
3 農業振興地域について
篠原茂議員の質問(6)
3 農業振興地域について
休憩(午後 0時01分)
再開(午後 1時00分)
藤原雅彦議員の質問(1)
1 市政運営の基本姿勢について
古川市長の答弁
1 市政運営の基本姿勢について
藤原雅彦議員の質問(2)
1 市政運営の基本姿勢について
古川市長の答弁
1 市政運営の基本姿勢について
藤原雅彦議員の質問(3)
1 市政運営の基本姿勢について
2 103万円の壁について
加地企画部長の答弁
2 103万円の壁について
髙橋総務部長の答弁
2 103万円の壁について
長井市民環境部長の答弁
2 103万円の壁について
宮崎経済部長の答弁
2 103万円の壁について
藤原雅彦議員の質問(4)
2 103万円の壁について
3 GIGAスクールで整備された端末の更新について
高橋教育長の答弁
3 GIGAスクールで整備された端末の更新について
藤原雅彦議員の質問(5)
3 GIGAスクールで整備された端末の更新について
高橋教育長の答弁
3 GIGAスクールで整備された端末の更新について
藤原雅彦議員の質問(6)
4 電話リレーサービスについて
久枝福祉部長の答弁
4 電話リレーサービスについて
藤原雅彦議員の質問(7)
5 電力スマートメーターフレイル検知事業について
久枝福祉部長の答弁
5 電力スマートメーターフレイル検知事業について
藤原雅彦議員の質問(8)
5 電力スマートメーターフレイル検知事業について
休憩(午後 1時59分)
再開(午後 2時10分)
伊藤義男議員の質問(1)
1 市長の政治姿勢について
(1) 外国人労働者
古川市長の答弁
1 市長の政治姿勢について
(1) 外国人労働者
長井市民環境部長の答弁
1 市長の政治姿勢について
(1) 外国人労働者
宮崎経済部長の答弁
1 市長の政治姿勢について
(1) 外国人労働者
伊藤義男議員の質問(2)
1 市長の政治姿勢について
(1) 外国人労働者
(2) 外国人の人口
加地企画部長の答弁
1 市長の政治姿勢について
(2) 外国人の人口
伊藤義男議員の質問(3)
1 市長の政治姿勢について
(2) 外国人の人口
(3) ワクチン接種健康被害
古川市長の答弁
1 市長の政治姿勢について
(3) ワクチン接種健康被害
伊藤義男議員の質問(4)
1 市長の政治姿勢について
(3) ワクチン接種健康被害
2 鳥獣被害について
(1) 健康政策から考える鳥獣被害
宮崎経済部長の答弁
2 鳥獣被害について
(1) 健康政策から考える鳥獣被害
伊藤義男議員の質問(5)
2 鳥獣被害について
(1) 健康政策から考える鳥獣被害
(2) 猿被害対策
宮崎経済部長の答弁
2 鳥獣被害について
(2) 猿被害対策
伊藤義男議員の質問(6)
2 鳥獣被害について
(2) 猿被害対策
3 災害時の遺体収容について
小澤市民環境部危機管理監の答弁
3 災害時の遺体収容について
伊藤義男議員の質問(7)
3 災害時の遺体収容について
4 太陽フレアについて
小澤市民環境部危機管理監の答弁
4 太陽フレアについて
伊藤義男議員の質問(8)
4 太陽フレアについて
5 障がい者福祉について
(1) 障がい者の意思疎通
久枝福祉部長の答弁
5 障がい者福祉について
(1) 障がい者の意思疎通
伊藤義男議員の質問(9)
5 障がい者福祉について
(1) 障がい者の意思疎通
(2) 外見からは分かりにくい障がい者への理解促進
久枝福祉部長の答弁
5 障がい者福祉について
(2) 外見からは分かりにくい障がい者への理解促進
伊藤義男議員の質問(10)
5 障がい者福祉について
(2) 外見からは分かりにくい障がい者への理解促進
(3) 障がい者の市政参加
久枝福祉部長の答弁
5 障がい者福祉について
(3) 障がい者の市政参加
伊藤義男議員の質問(11)
5 障がい者福祉について
(3) 障がい者の市政参加
古川市長の答弁
5 障がい者福祉について
(3) 障がい者の市政参加
伊藤義男議員の質問(12)
5 障がい者福祉について
(3) 障がい者の市政参加
散会(午後 3時10分)
本文
令和6年12月10日(火曜日)
議事日程 第2号
第1 会議録署名議員の指名
第2 一般質問
議案第77号 令和6年度新居浜市一般会計補正予算(第5号)
議案第78号 令和6年度新居浜市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
議案第79号 令和6年度新居浜市水道事業会計補正予算(第1号)
議案第80号 令和6年度新居浜市公共下水道事業会計補正予算(第1号)
――――――――――――――――――――――
本日の会議に付した事件
議事日程のとおり
――――――――――――――――――――――
出席議員(26名)
1番 小野 志保
2番 伊藤 義男
3番 渡辺 高博
4番 野田 明里
5番 加藤 昌延
6番 片平 恵美
7番 井谷 幸恵
8番 河内 優子
9番 黒田 真徳
10番 合田 晋一郎
11番 神野 恭多
12番 白川 誉
13番 伊藤 嘉秀
14番 越智 克範
15番 藤田 誠一
16番 田窪 秀道
17番 小野 辰夫
18番 山本 健十郎
19番 高塚 広義
20番 藤原 雅彦
21番 篠原 茂
22番 伊藤 謙司
23番 大條 雅久
24番 伊藤 優子
25番 仙波 憲一
26番 近藤 司
――――――――――――――――――――――
欠席議員
なし
――――――――――――――――――――――
説明のため出席した者
市長 古川 拓哉
副市長 原 一之
企画部長 加地 和弘
総務部長 髙橋 聡
福祉部長 久枝 庄三
市民環境部長 長井 秀旗
経済部長 宮崎 司
建設部長 高橋 宣行
消防長 後田 武
上下水道局長 玉井 和彦
教育長 高橋 良光
教育委員会事務局長 竹林 栄一
監査委員 鴻上 浩宣
市民環境部危機管理監 小澤 昇
――――――――――――――――――――――
議会事務局職員出席者
事務局長 山本 知輝
議事課長 德永 易丈
議事課副課長 鴨田 優子
議事課副課長 岡田 洋志
議事課調査係長 伊藤 博徳
議事課議事係長 村上 佳史
議事課主事 田辺 和之
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前10時00分開議
○議長(小野辰夫) これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程につきましては、議事日程第2号のとおりであります。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(小野辰夫) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において藤原雅彦議員及び篠原茂議員を指名いたします。
―――――――――― ◇ ――――――――――
日程第2 一般質問 議案第77号~議案第80号
○議長(小野辰夫) 次に、日程第2、議案第77号から議案第80号までを議題とし、議案に対する質疑と併せ、一般質問を行います。
この際、申し上げます。一般質問並びに質疑における各議員の発言は、それぞれ通告の時間以内となっておりますので、御了承願います。
順次発言を許します。まず、大條雅久議員。
○23番(大條雅久)(登壇) 会派自民クラブの大條雅久です。
まずは、初めに、古川拓哉新市長におかれましては、第25代新居浜市長への御就任おめでとうございます。去る11月10日に行われた新居浜市長選挙で、新居浜市民の信任を受けてからの1か月、古川新市長には、目まぐるしく忙しい日々を過ごされたかと存じます。しかしまた、この1か月の間、世界も大きく動いています。動乱と混沌とした世界情勢、日本国を取り巻く予測し難い政治経済の動きの中、日本国はもちろん、愛媛も新居浜市も無関係ではありません。私たち新居浜市民全員が、激変する時代の波はもちろん、変わり行く社会情勢の荒波をいかなる指針で航路を定め、こぎ出でていくか、難しいかじ取りが新市長と私たち市議会に託されています。大いに議論し、切磋琢磨する中で、次世代に誇りと希望を抱いてもらえる新居浜市を私たちも目指してまいりたいと思っています。
それでは、通告に準じて質問をさせていただきます。
古川市長が目指される新しい新居浜づくりに向けて、具体的に何を実行されるのか、お聞かせください。
私たちも災害と危機管理に強い町のためと併せて子供たちの健康管理を考えて、2番目の質問に、小中学校体育館への早期エアコン設置を、また誰もが取り残されない優しいコミュニティーづくりとして、3番目の質問に、交通弱者のための公共交通整備をお聞きするようにしています。しかし、このほかにもやるべきことは多々あると思います。古川市長が考える新しい新居浜実現のために、実行したい具体策をお聞かせください。
また、さきの市長選挙で私たちが推した加藤候補が上げた10の公約の1番目は、新居浜に大学をつくるでした。この公約が一番市民に伝わってなかったのかもしれません。伝える時間が、語る時間があまりにも足らなかったかなと思っています。それは、10の公約それぞれに言えることですが、その一番伝わりにくかった大学をつくるについてですが、新居浜市では、現在、約1,000人の子供が毎年高校を卒業しています。市内にある5つの高校の3年生が約1,000人、近隣の西条市や四国中央市からも生徒さんは通学していますが、同じくらい新居浜市の生徒が市外の学校に通っています。新居浜市に生まれた生徒さんは、高校を卒業した後、大学や専門学校にどのくらい、何人くらい進学しているのかなと考えてみますと、大学に限って考える材料としては、文部科学省の学校基本調査による2023年度の愛媛県の大学進学率が56.3%、その数字を使って考えると、約560人となります。民間のある信販会社が行った調査によると、大学生への仕送り額の平均は、月額10万8,350円だそうです。560人の子供に毎月10万円、それを12か月掛けると6億7,200万円になります。短大や専門学校を含む高等教育機関への進学率で見ますと、全国平均が84%ですから、この短大や専門学校を含んで考えると、新居浜市から1学年当たり10億円ぐらいの仕送りが送られているんではないでしょうか。短大、専門学校は2年間、大学が4年間、大学院や学部によっては6年間在学をしますので、平均4年間の在学と考えると、1回生から4回生への仕送りは、合計で年間40億円という金額になります。毎年40億円のお金が、新居浜市内で消費されずに、東京やその他の都市へ吸い込まれている。お金という富だけでなく、子供という家庭やふるさとの宝が、東京をはじめとする首都圏や大都市に吸い込まれていく、この日本の現状を変えないといけない。経済も人材もあらゆるものが東京一極集中、これが今後も同じように続くなら、ふるさと再生も地方創生もあったもんじゃないと私は感じております。国は、首都圏機能の地方分散を時々口にしますが、本気でやっているようには見えません。
では、生き残りをかけた地方が何から始めるか、人材確保、若者の流出抑制でしょうか。企業誘致、移住促進もしかりです。私のささいな経験ですが、高校卒業後、9年半ほど東京で暮らしていました。その後、結婚もして、新居浜に帰ったのが27歳のときです。家業のスーパーマーケットを手伝っていた4年半ほどの間に、10人くらいの桃山短期大学の学生さんと知り合いました。皆さん私の店でアルバイトをしていただいてます。新居浜市内の方でなく、全員が広島とか大阪とか、県外から桃短に通っていた男子学生です。真面目で結構気がついて、年寄りが多い店でしたので助かったことを覚えています。全員が中村や土橋に下宿していました。当時、昭和60年頃のことですが、保育士を目指せる幼児教育学科で男子学生を受け入れている短大は、西日本では桃山短期大学くらいだったそうです。卒業して保育士になられた方も結構いたと思います。
市長に改めてお聞きいたします。
18歳から22歳の若者がいる場所、目標が持てる場所が、新居浜市にもっとあればいいと思いませんか。そんな思いから、さきの市長選で私たちの推しの公約の1番が新居浜に大学をつくるになりました。特色ある学校、大学というなら、産業界と学校と行政が連携することで、住友企業を含め、地元企業に就職100%保証なんていうキャッチでもいいんじゃないでしょうか。そういう思いで訴えたのですが、古川市長はいかが思われますか。
今の日本の人口構造・分布は異常です。地方創生は、この東京一極集中の人口と経済を変えないと進まないと思います。今のままの国の取組ようでは、地方創生の実行はおぼつかないと私は感じています。地方創生の成否は、まさに地方に住む我々自身が、市が、町が、地方自治体が、知恵と勇気を結集して戦わないと成果は得られないと思っています。市長にとっては、いかがお考えでしょうか。
故郷に錦を飾るのではなく、故郷で錦を織りたい、そうお聞きしました。そんな同じ思いを故郷にいながら達成する若者の居場所があってほしいものだと私も思います。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) 大條議員さんの御質問にお答えいたします。
新しいにいはまについてでございます。
まず、新しい新居浜実現のために実行したい具体策についてお答えいたします。
私は、市長公約として、様々な施策を掲げておりますが、市民の皆様、市議会の皆様のお声を伺いながら、前例や慣習にとらわれることなく、実現可能な公約から取組を進めてまいりたいと考えております。もちろん、公約につきましては、市長任期内での実現を目指してまいりますが、その中でも特に子育て支援の充実、地域経済の活性化、防災能力の強化の3点につきましては、積極的に進めていきたいと考えております。
次に、若者がいる居場所、目標が持てる場所としての大学の新設についてでございます。
本市の若者が、目標を持ち、学び、成長できる環境を整えることは、本市の持続的発展において大変重要な取組であると認識いたしております。
大学の新設につきましては、全国的な少子化の進展により、多くの地方大学が学生確保に苦慮している現状があり、本市において大学設立を検討する場合においても、学生の確保は経営上のリスクとなる可能性があり、慎重な判断が求められるものと考えております。本市には、新居浜工業高等専門学校があり、市内外から多くの学生が入学を希望する地域の学びの場の一つとして大きな役割を果たしていただいており、貴重な地域の教育機関であるとともに、産学官連携の拠点でありますことから、今後も幅広い分野において、連携、協力を進めさせていただきたいと考えております。
今後におきましては、公約に掲げた子育て支援策の充実や地元企業との連携による魅力的な就業機会の創出、若者が楽しめる文化・スポーツ活動の拠点整備などに関する検討を進めるとともに、情報発信の強化に努め、若者にとって魅力のある新しい新居浜の実現に向けたまちづくりを推進してまいります。
○議長(小野辰夫) 大條雅久議員。
○23番(大條雅久)(登壇) 市長の答弁の中にありました高専の充実については、従来もですが、ぜひこれまで以上の力を入れていけばと私どもも思います。あわせて、連携だけではなく、学校の教員、また学生数の充実といったことにも働きかける必要があるかと思います。私は、18歳から22歳の若者が、目的を持てる場所という中で、大学ももちろんですが、もっと幅広く捉えていただいて、今後の市政に、ぜひ政策の検討をしていただきたいと思っております。工夫はあると思いますし、学校の形態自体が、今時代が変わってます。どんな名称であれ、若者が新居浜から外へ行かなくてもいい、これはある方が言ってましたが、地方で高等教育まで一貫して受けることができるかできないか、これがまさに地方創生にかかっていると。私も同感です。地方というくくりが、新居浜市で終わるのか、東予地域で見るのか、また県単位なのか、四国なのか、これはそのレベルによって変わると思いますが、まずやらなければいけないのは、東京一極集中、これを地方の側から打破していかなければ、その努力をしていかなければ、地方創生はあり得ない、そう思っております。
次の質問に移ります。
小中学校体育館へのエアコン設置について。
この点につきましては、さきの9月議会で、私自身の質問で石川前市長に要請したところ、早急な対応をしたいとの答弁をいただきました。これは、市政だより12月号に掲載されたとおり、小中学校体育館へのエアコン設置について、国の補助や緊急防災・減災事業債などを活用し、早期実現ができるよう取り組みたいと答弁をいただきました。
古川新市長におかれても、同様の認識と思ってよいのでしょうか。令和7年度中の設置を目指していただけるのでしょうか。答弁をお願いいたします。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) 小中学校体育館へのエアコン設置についてお答えいたします。
小中学校の体育館は、児童生徒の学習、生活の場であるだけでなく、社会体育や地域の交流の場、また災害時の避難所として指定されておりますことから、安全、安心な環境を整備し、児童生徒などの快適性を向上する必要があると考えており、私の公約においても、小中学校体育館への空調導入について検討することといたしております。
私といたしましても、小中学校体育館へのエアコンの設置につきましては、実現できるよう取り組んでまいりたいと考えており、実施時期につきましては、活用可能な財源を検討し、財政状況を見極め、適切に判断してまいります。
○議長(小野辰夫) 大條雅久議員。
○23番(大條雅久)(登壇) 前向きな答弁と受け止めておりますが、ぜひとも石川前市長が考えていた国の施策、国から財源を引っ張ってくる、この努力をして、令和7年度夏の実現をできれば市内全校ですが、半分の学校にでもできるように努力していただきたい。お願いいたします。
次の3番目、公共交通の在り方についてですが、高齢者はもちろんのこと、交通弱者と呼ばれる方々にとって、日々の通院や買物に使うバスやタクシーは不可欠なものであります。可能な限り、より安全で気軽に利用できてかつ安価であることが望ましい。しかし、現在の路線バスは、本数が少なく、路線も限られており、利用できるバス停の数も限られています。市民からは、既成の路線バスではなく、小型バスでの市内循環システムなどを要望する声がありますが、古川市長はいかがお考えでしょうか。
また、現在、新居浜市では、おでかけタクシーの名称でデマンドタクシー事業が実施されていますが、使い勝手が悪い、対応が親切でないなどの御意見が多々寄せられており、事業内容の見直しが必要と私たちは考えております。
見直ししたほうがよいと考える点を幾つか挙げますと、JR新居浜駅を中心に結節点と表現していますが、川西、川東、上部西、上部東と新居浜市内を4地区に分けて、地区を越える利用に条件をつけています。また、基本的には路線バスのバス停から300メートル以内にお住まいの市民は、利用登録が制限されています。私たちは、市民なら誰でももっと気楽に利用できるデマンドタクシー事業に改善すべきとさきの市長選で訴えました。古川市長も、交通弱者の市民に寄り添ったデマンドタクシー事業にすることには賛同いただけるかと思いますが、いかがでしょうか、市長のお考えをお聞かせください。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) 公共交通の在り方についてお答えいたします。
まず、通院バス、お買物バスについてでございます。
本年3月に策定いたしました新居浜市地域公共交通計画におきまして、市民生活を支える基幹公共交通軸及び支線軸として位置づけた路線バスとバス交通空白地をカバーし、基幹公共交通軸及び支線軸までをアクセスするデマンドタクシーを両輪として、新居浜市の公共交通を維持していくといたしており、基本的には、私もこの考え方を踏襲してまいりたいと考えております。
小型バスでの市内循環システムの導入につきましては、買物や病院などに安心して出かけることができる環境をつくるための手段として有効ではありますが、一方で運転手不足の中、多岐にわたる市民ニーズに沿ったルートや運行本数を確保することができるのか、デマンドタクシーの利用者とのすみ分けはどうするのか等の課題もございます。現在、新居浜市地域公共交通活性化協議会におきまして、市民の利便性を向上させるため、JRやデマンドタクシーとの接続を考慮し、効率的なバス路線の再編に向けた協議を進めていると報告を受けており、今後循環バスの導入も含めた公共交通網の拡充に努めてまいります。
次に、デマンドタクシーについてでございます。
選挙期間中、多くの方々からデマンドタクシーが不便だという切実な声をお聞きしました。デマンドタクシーは、バスとタクシーの中間に位置する公共交通であり、各事業者の経営を考慮しながら見直しを図り、地域交通を維持していく必要があるものと考えております。
また、デマンド交通とは、複数の予約をまとめることで、乗り合いをつくって効率を高めるものであり、行き先がばらばらで広域にわたると、迂回距離や乗車時間が長くなり利便性も悪くなることから、一定のエリア内に制限し、効率的な運行を図る必要がございます。
今後は、交通事業者等関係者とも協議しながら、デマンドタクシーの改善を進めるとともに、路線バス等他の公共交通との連携も含めて、市民がもっと便利に利用できる公共交通体系の構築を目指してまいります。
○議長(小野辰夫) 大條雅久議員。
○23番(大條雅久)(登壇) 古川市長も既にお気づきだと思うんですが、おでかけタクシーがなぜ不便か、運転手さんが親切かどうかというのは置いといて、それも結構言いたいことが市民からあるんだと言われましたが、例えば川西地区のデマンドタクシーは、イオンへ行けない。行けないというか、行く場所を決めてますから、目的をね、行く場所からなぜイオンが外れてるのか、よく分からない。これは全般的で、地域バスを新居浜市は古くから走らせてます。別子山から新居浜市内をつなぐバスです、御存じのとおりですが。市内のバス停の宣伝とか活用が十分でないと従来私は聞いてきたんですが、聞いてきたというのは、質問に取り上げてきましたが、変わりません。なぜか。タクシーもデマンドタクシー事業も地域バス事業も、既存のバス会社、タクシー会社に遠慮している。遠慮しているというよりも既得権を崩せないでいる。これに対してどういう対応をしていくかで次のスタイルが決まると思うんですよ。市長も18年、市議会議員、県議会議員をされてきて、お伺いしたい意味は分かるかと思うんですが、ここで既存の既得権をどう打破していくか、これが新しいスタイルをどうつくれるかにかかると思うんですが、今お考えになっていることがありましたらお聞かせください。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) 大條議員さんの既得権をどう打破するかという質問についてお答えをしたいと思います。
私自身は、既得権ということを守るのではなく、市民にとってどうすれば便利になるのかということを考えていきますとともに、やはり先ほどからお伝えしているとおりでありまして、ドライバーの不足であるとか、様々な事情も出てきております。そのような中で、市内の業者さんとは共存共栄を図りながら、どのようにしてより市民が便利に使っていただけるかということを念頭に置いて考えていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
○議長(小野辰夫) 大條雅久議員。
○23番(大條雅久)(登壇) ぜひとも市民にとって使い勝手がいい、よかったなと思える新しい公共交通機関、交通弱者に優しいデマンドタクシー、地域バスを進めていただきたいと思います。
次の質問に移ります。
奨学金返済支援事業についてです。
令和6年度の当初予算で、幾つかの補助金制度が継続されなかったとの御意見を聞き、私も担当課に問合せをいたしました。継続されなかった補助金制度の多くが、公募事業提案により創設されたもので、当初より3年間の実施期間が経過した時点で見直される規定になっていたものでしたが、それ以外にやはり支出の見直し、経費削減の流れの中で、削減や中断されたものが幾つか見受けられました。その一つが、今回質問に取り上げた奨学金返済支援事業です。平成28年度から実施していた奨学金返済支援事業について、その内容とこれまでの実績を教えてください。
また、今年度、今年の4月から新規の支援を打ち切ったとのことですが、なぜでしょうか。応募者がいなかったのでしょうか。新規支援中止の理由を併せて御説明ください。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。加地企画部長。
○企画部長(加地和弘)(登壇) 奨学金返済支援事業についてお答えいたします。
まず、事業内容についてでございます。
本事業は、若者の本市へのU・I・Jターンを目的としており、補助対象者は奨学金を1年以上返済し、1回目の交付申請日に満30歳以下、かつ新居浜市に本社のある中小企業で1年以上継続して雇用されている方、もしくは起業された方や第1次産業に従事して1年以上継続して事業を行っている方となっております。
補助金額は、年間返済額の3分の2を上限に、1回当たり20万円まで、申請回数は3回までとなっております。
また、補助実績につきましては、事業開始の平成28年度から令和5年度の8年間で181人、補助額5,576万円となっております。
次に、新規支援中止の理由及び応募希望者の有無についてでございます。
令和5年度に申請者23名に対しアンケートを実施いたしましたところ、全員が本事業を契機としたU・I・Jターンではないとの回答を得たため、本事業が直接U・I・Jターンに結びついていないと判断いたしました。
また、県においても同様の目的で奨学金返済支援事業が実施されていることから、令和5年度末をもって新規支援の受付を終了したものでございます。
新規支援の受付終了に際しましては、市ホームページ及び市政だよりにて周知を図ってまいりました。
今年度に入り、応募希望の問合せはございませんが、制度に関してのお問合せを2件いただいております。
今後におきましては、県の補助制度を本市出身学生及び市内企業に周知するとともに、若者のU・I・Jターンの促進を図れるよう、より費用対効果の高い政策を推進してまいります。
○議長(小野辰夫) 大條雅久議員。
○23番(大條雅久)(登壇) 新規募集の停止に当たって、23名の方にアンケートを取ったというお話がありました。私も担当課の方にお伺いして、なぜ中止をしたのかとお聞きする中でその点はお聞きしました。でも、調べると、ちょっと違うんじゃないですかね。確かに、県も同様の事業をしておりますが、ほかの町、今治市をはじめ、県下の多くの町が、大洲市もそうですし、宇和島市もそうですね、この事業を継続しております。県の事業と新居浜市のこの事業を比べると、一番違うのは、新居浜市の事業は、学校を卒業してなおかつ1年間、地元企業に勤めて、初めてエントリーする資格ができるんですね。確かに、各学校にパンフレットは送ってあったのかもしれませんが、在学中にアクションを起こすことができないんですね。ある意味では必要がないとも言える。だから、知り得ないんですよ。23名の方は、地元に帰って就職したときに、会社から、親から、自分が調べてこういう制度があるんなら1年たったら申請しよう、そういう流れなんで、就職を決める前には、新居浜市の事業は知らないし、エントリーするというアクションも起こせない。県の事業は、在学中にこの県の事業の制度を知ってエントリーするんですよ。ちょっときっかけが違うと思うし、アンケート自体が間違っているんじゃないんですかね。私の今の考えは質問です。
私はアンケートの取り方が違っていたと思うんですが、いかがですか。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。加地企画部長。
○企画部長(加地和弘)(登壇) 大條議員さんの御質問にお答えいたします。
アンケートについてでございます。
このアンケートは、予算編成に当たりまして、事業の効果を確認するために、申請者に対しまして、この事業がきっかけでU・I・Jターンをしましたかということの問合せに対しまして、全員が違うという回答を得ております。この事業は、U・I・Jターンを目的としておりますので、そういった結果が出ましたことから、新規受付については廃止をいたすという判断をいたしたものでございます。
○議長(小野辰夫) 大條雅久議員。
○23番(大條雅久)(登壇) やっぱりアンケートの取り方が違っていると思います。先ほども言いましたが、在学中に知り得ないんですよ。就職してから知るんですよ。皆さんは奨学金をもらって、こうやって地元に帰ってきて仕事をしている方って、聞かれたことを真面目に答えますよ。就職する前に知ってて、それを判断材料にしたかしないかだったら分かるけど、知らなかったものを判断材料にしたなんて誰も答えませんよ。その意味で、私はこれは終わったんですかって担当課に聞いたら、終わってない。終わってないですよね、2年目、3年目の方がいらっしゃるから。ただ、今年初めてもらおうと思った方がもらえないという。ですから、やっぱりやめてるわけですよ。私がこれを知ったのは、1年頑張って、地元の企業に勤めて、勤めたときにこの制度を知ったから、来年の春、この奨学金返済支援事業を申請しようと思っていた人から手紙をいただいた。担当課にも手紙のコピーをお渡ししましたけど、こうやって真面目な子がばかを見るようなやめ方はやめてほしい。再度考えていただきたいと市長にお願いをしておきます。また、そのお手紙が、多分市長にもまた届くと思いますので、どういう気持ちで、きょうだいが多いと、奨学金というのは必要です。高校に99%の方が進学し、大学や専門学校に84%の人が進学する中で、きょうだいが2人、3人にいる家庭もいらっしゃいますから、そういう中では奨学金というのは絶対欠かせないものです。よろしく御検討をお願いいたします。
次に地域コミュニティーの活性化について。
新居浜市では、令和3年3月に策定した新居浜市地域コミュニティ基本指針に基づき、持続可能な暮らしを実現するため、地域課題の解決に向けた取組を進める地域運営組織の設立を進めるとし、2年間の準備を経て、令和5年3月にモデル校区であった2つの校区、宮西校区及び中萩校区において新しい地域運営組織が設立され、活動を始めたとのことです。
地域運営組織の取組状況は、現在どのような状況でしょうか、お聞かせください。
また、地域コミュニティ課が発行し、にいはま地域運営組織の取組を紹介している地域づくりだよりでは、現在創刊号から第3号まで発行されておりますが、第3号で、今年9月24日に開催された令和6年度第1回新居浜市地域コミュニティ再生検討委員会の報告が記載されていました。その中で、地域コミュニティーアドバイザーの愛媛大学社会共創学部准教授の笠松氏の発言を拝見いたしました。発言の内容は、人々の価値観や生活のスタイルが多様化し、社会が多様化していることから、自治会や地域運営組織も社会の多様性への対応を考えなければミスマッチが起こる可能性がある。地域コミュニティーづくりでは、住民の意思がそこにあることが重要であるという内容でした。この発言から、私が思い出したのは、令和3年に新居浜市が地域運営組織をコミュニティー再生の手法として取り組むためにモデル校区を募集したところ、5つの校区が手を挙げました。2つの校区で始めたばかりの持続可能な暮らしを実現するための施策が、事情があって2つが今1つになってます。さきの審査で外れた3つの校区に参加の打診をしたのかと思ったのですが、一切していません。
今後の地域運営組織の方向性、活動目標と、併せてなぜなのか、お聞かせください。
次に、さきの9月議会の質問項目と重なりますが、時間切れで答弁を聞いていないことをお聞きいたします。
2024年6月19日に地方自治法の改正が国会で可決され、その大部分がこの9月に施行されました。この改正については、各種報道でも賛否が分かれ、いろんな問題点が指摘されておりますが、私はこの中で今回の改正の3つの柱のうちの3番目、地域の多様な主体の連携及び協働の推進に関する事項について、さきの議会質問で御答弁いただけなかったので、再度お聞きいたします。
地域の多様な主体の連携及び協働の推進に関する新居浜市の現在の取組と今後の目標についてお聞かせください。例えば、公民連携についての取組が、公共私連携の推進とより踏み込んだ言葉で表面に出ていると思います。今回の改正で出現した指定地域共同活動団体制度の創設とは、どのような仕組みと理解すればよろしいのでしょうか。
また、将来の地域コミュニティーのありようをどのように想像すればよいのでしょうか、御所見をお聞かせください。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。長井市民環境部長。
○市民環境部長(長井秀旗)(登壇) 地域コミュニティーの活性化についてお答えいたします。
まず、協議会型地域運営組織についてでございます。
現在の地域運営組織の取組状況につきましては、宮西校区では、今年度は活動2年目となり、地域のまちづくり計画に沿って、子供の居場所づくり、独居高齢者への見守り活動、防犯防災事業など様々な事業を実施いただいております。新たな人材の掘り起こしや自己財源の確保等の問題はあるものの、地域の各種団体が連携、協力しながら、地域自らが策定した10年間のまちづくり計画に基づき、地域の創意工夫によって主体的にまちづくりに取り組まれていることは、モデル事業の成果として一定の評価ができるものと考えております。
新しい仕組みであります地域運営組織が、モデル地区で設立されてからまだ1年間の活動実績でございますことから、中長期的な視点においても成果検証を行い、事業の進捗等を検討していく必要があると考えております。
また、新たなモデル校区募集から活動成果を検証していくには、一定の期間を要することなどから、新たなモデル校区を増やしていく考えは、現時点ではありませんが、引き続き宮西校区まちづくり協議会の活動状況等について、成果や課題を整理、分析しつつ、地域の皆様と協議を行いながら、今後の地域運営組織の方向性や活動目標を定め、持続可能な地域コミュニティーの活性化を図ってまいりたいと考えております。
次に、2024年地方自治法改正についてでございます。
まず、地域の多様な主体の連携及び協働の推進における市の現状の取組と今後の目標につきましては、多様で豊かなコミュニティーづくりを実現するため、本市が持つ地域の力が発揮できる環境を整え、市民と行政が協働して、地域の中で支え合い、助け合う、時代に即したコミュニティーを構築していくための共通の指針として、令和3年に地域コミュニティ基本指針を策定し、自治会、地域運営組織及び町全体のコミュニティーそれぞれにおいて各種の事業を展開しております。人口減少や地域力の低下が進展する中、持続可能な暮らしの実現のためには、従来の組織の枠を超えて、地域内の様々な分野の団体がより連携、協力し、共通の目的の下、地域の課題解決や住みやすい地域をつくるための仕組みづくりの構築が今後の地域コミュニティーの再生に向けての目標であると考えております。
次に、地方自治法改正による指定地域共同活動団体制度の創設につきましては、市町村の判断により、生活サービスの提供に資する活動を、地域の多様な主体と連携して行う団体について、指定地域共同活動団体として指定し、その活動を支援する制度であり、この制度創設により、住民の福祉の増進が、効率的かつ効果的に図られると認めるときは、団体への事務委託の随意契約や行政財産の貸付けが可能になり、また関連する活動との調整が図られるなど、地域の多様な主体による活動がより一層活性化され、行政では十分に対応し切れない地域特有の課題解決につながる取組が促進されるものと考えております。
なお、今回の法改正への対応につきましては、まずは地域の実情や関連団体の活動状況等を踏まえ、制度活用の効果、必要性、適用範囲、課題等を十分に調査研究をしていきたいと考えております。
次に、将来の地域コミュニティーの在り方につきましては、人口減少、少子高齢化など様々な課題が深刻化し、人材や財源といった地域の資源が限られている状況が明らかになってきており、地域社会を取り巻く環境が一層厳しくなる中、地域の多様な主体の連携と協働を推進し、自治と分権、すなわち地域のことは地域で決める、地域が主体的に取り組むことを念頭に、支え合い、助け合うコミュニティーづくりがこれから目指すべき将来の地域コミュニティーの在り方であると考えております。
○議長(小野辰夫) 再質問はありませんか。大條雅久議員。
○23番(大條雅久)(登壇) 笠松アドバイザーの発言というのは、みんなにやらせてみて、やれるところがやれたらいいじゃないですかという意味なんですよ。こんな全部決めて、地域の特質があるのに、全部マニュアルを作ってから始めるんじゃ意味がないと思います。12月8日の愛媛新聞に、藤目愛大名誉教授の記事が出ておりました。平成の大合併20年のシリーズの最新号ですが、地方分権、これは自治体内の分権も重要だというレポートです。読まれた方多いと思いますが、私が語るよりも再度読んでいただいたら、今回の最後の議論の意味合いがもう少し御理解いただけるかと思います。あわせて、お金のかけ方が違います、モデル校区への。(ブザー鳴る)
○議長(小野辰夫) この際、暫時休憩いたします。
午前10時53分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午前11時04分再開
○議長(小野辰夫) 休憩前に引き続き会議を開きます。
篠原茂議員。
○21番(篠原茂)(登壇) みらい新居浜の篠原茂です。
古川拓哉さん、第25代新居浜市長就任おめでとうございます。市議会議員、県議会議員としての経験を生かし、新居浜市の将来を担うリーダーシップの発揮を期待しています。共に新しい新居浜を創造していきましょう。
それでは、通告に従いまして質問いたします。私がこれまで感じてきた7点について、古川市長に質問させていただきたいと思います。
1点目、市政運営に対する思いです。
市長となり、どのような初心を持っておられますか。新しい新居浜として、常に挑戦するまち、目指せ愛媛ナンバーワンのまちづくり、笑顔あふれる人に優しいまちづくりの3点を掲げられておられますが、市民の信託を受けた古川市長の思いをお聞かせください。
これからの4年間の中で、どのような新しい新居浜をつくっていこうとしておられますか。新しいと言うからには、古い、旧態依然としたイメージが連想されますが、何を新しく変革していきたいのでしょうか。具体的に変えたいことがありましたら、お聞かせください。
2点目、財政状況。
新居浜市の財政状況は、どこまで厳しいのか、市民と共有してスタートしませんか。選挙の際、新居浜市の財政調整基金が、東予4市の中の最低水準で、底をつく状況であることを話されました。確かに、財政調整基金という市の貯金ですが、その一方で新居浜市は債務が少ない健全財政を保ってきたとも私は考えていました。現在の新居浜市においては、貯金も少ないが借金も少ない状況で、他の市町は、借金も多いが貯金も多い状態と理解しています。いずれにしても、厳しい状況に変わりはありませんが、どちらが望ましい状態であるのか、市民に分かりやすく説明をお願いいたします。
前市政時代になりますが、財政調整基金を取り崩している間を含め、5年間にわたって、実質単年度収支が赤字続きであったと聞いておりますが、赤字対策を実施せず、放置していた理由について、古川市長は、どのような報告を受けていますか、お伺いいたします。
今後の新居浜市における財政方針について、財政調整基金の減少の原因を詳細に調査し、収支を見直した上で対策を講じる必要があると考えます。古川市長のスタートに当たり、基金が減った明確な原因及び今まで実施してきた支出削減の在り方が妥当であったかどうかも含め調査検討し、今後の対策を市民の皆様に提示することが必要と思いますが、市長のお考えをお伺いいたします。
3点目、市民への情報発信と対話型行政。
市民に対して、政策形成のプロセスを分かりやすく情報発信して、市民と共に考え、実践するまちづくりが必要ではありませんか。新居浜市民には、多様な人がいます。老若男女、ハンディを抱えた人、経済状況も様々です。SDGsの柱には、誰一人取り残さないという理念が掲げられていますが、まちづくりに物言わない人の声は伝わってきません。しかし、物言わない人は、物が言えない状況にあったのかもしれません。今回の市長選挙でも、多くの方から発言できる場所づくりの提供を頼まれました。これからは、みんなが関わることに対し、物が言える仕組みづくりをしませんか。例えば、市民の将来を左右するプロジェクトに対しては、特定の関係者で判断するのではなく、多様な分野の人が集まって議論するプロジェクトチームをつくって多面的に考えたほうがよいのではないかと思います。市民文化センターの議論についても、文化に関連する市民だけではなく、環境や経済、さらには福祉など様々な分野で活動している人たちが関与することで、誰一人取り残されないすばらしい施設が生まれるのではないかと思います。
また、コンサル業者に全て頼るのはやめませんか。地域力を信頼し、みんなが知恵を出し合うことが、本当の地域の底力を育むのではないかと思います。
これまで市政懇談会や様々な審議会は開催されてきました。しかし、その実態は、シナリオどおりに流れ、アリバイづくりの会議になってしまうものも多かった気がします。今こそじっくりと市民の生の声に耳を傾け、ぶつかり合う意見を出し合って、その先に納得できる答えを発見する、古川市長も言われていますが、一緒に力を合わせ、よりよい新居浜をつくる、市民と共につくる対話型行政スタイルを目指すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
そこで話し合った内容については、市の発信する広報手段を駆使して市民に伝える、市民みんなに知ってもらえる機会をつくっていくべきではないかと考えますが、お考えをお伺いいたします。
また、市民との懇談会の開催もよいのですが、市長自らが現場に足を運んで、市の課題について直に知っていただきたいです。災害対策、医療・保健・福祉分野、地域コミュニティー、観光、物産など、現場を重視すべき分野は多くあります。市長自らが出向き、現場の意見や状況を直接見聞して、肌で感じることにより、机上の考えとは違った新たな発見が見つかるのではないでしょうか。市長の御意見をお伺いいたします。
4点目、独自政策。
四国中央市では、学校給食無償化を実施していると聞きます。また、国や県のレベルでは、政策展開が明らかになってない段階で実施するんであれば、市の単独事業として推進することになると思います。当然、多額の財政負担が生じます。しかし、そのような大胆さがなければ、古川市長が提唱する愛媛ナンバーワンのまちづくりは実現しないと考えます。給食だけでなく、独自政策として、市民の納得の上で予算をつぎ込んでも実現したいテーマがありましたらお伺いいたします。
5点目、職員の意識改革。
市役所には、現在約900人の正規職員がおります。非正規の職員も含めれば1,500人を超える大企業だと思います。私たち議員も含めれば、さらに大きくなり、新居浜市役所を超える企業は、市内でもほんの数社です。この大きな組織をどのように市民の幸福の実現のために生かしていこうとお考えでしょうか。
最近の企業は、社員こそ宝という視点から、従業員の意識を高め、個人の力を育てると同時に、組織の力を高めていくための努力を惜しみません。それなしでは企業は競争に打ち勝っていけないし、みんなの信頼を獲得することができない時代になっています。行政にとっても、人材は宝です。特に、現在の財政が厳しい状況で、補助金等が減額される中にあって、その減額分を補い、住民サービスの維持を図っていくためには、やる気があって行政の目的を十二分に理解した職員の働きが最も重要になると思いますが、聞くところによると、職員の研修予算は削減され、見聞を広める機会が減少し、日常業務の変革に生かされることは減少しているとの声も聞きました。古川市長がイメージしている新居浜市役所の組織力、チーム力及び職員像は、どのようなものでしょうか。
また、今後その力を伸ばしていくために、どのような人材育成をしていくのか、お考えをお伺いいたします。
6点目、郷土愛の育成。
高校を卒業して、大学に行って、新居浜市に戻ってくる若者はどのくらいおられるのでしょうか。私は、将来、3分の2の卒業生が新居浜で社会人として暮らすことができる町が実現できたら、人口減少社会の中でも生き残れると語った人の言葉が耳から離れません。働く場所がない、遊ぶ場所もない、そんなないない尽くしで都会に憧れる、そんな時代はもう終わったのではないかと感じるようになりました。都会から地方へ憧れ、やってくる若者が増えています。まだまだ一部の自治体ですが、社会は変わりつつあると実感しています。また、自分たちの町に愛着を持つ若者も増えています。地域社会の様々な人たちと子供の頃から公民館で交流する機会が多かった若者は、そんな傾向を持つという話もよく聞きます。有識者の話では、卒業後、進学で出ていった学生がUターンで戻ってくるほとんどが、強い郷土愛を持っており、Uターンを促すための方策として、高校を卒業するまでに郷土愛を醸成しなければ効果はないとのことです。今年の出生者数は、全国で70万人を切るという状況です。新居浜市でも700人を切ることは避けられない状況です。この子供たちが大人になったときに、新居浜市で暮らしたいと思える町にしていくためには、何をやっていきたいか、教育はすぐに答えは出せないかもしれませんが、学校だけでなく、子供たちに夢と希望を捨てさせないために、教育委員会としてどのようなことをやっていきたいのか、お考えをお伺いします。
7点目、新居浜市の経済対策。
新居浜市の経済は、別子銅山が元禄4年、1691年の開坑に始まり、鉱山から派生した住友グループとその関連企業により、四国有数の工業都市として発展してきました。現在も住友グループを中心としたものづくり産業が中心となり、新居浜市の経済を支えていることは、新居浜市民として疑いを持ちません。新居浜市にとって、住友各社の繁栄が、新居浜市の活性化に大きく寄与してくれています。
このような産業形態を持つ新居浜市において、市と住友グループとの連携強化を図ることにより、今まで以上にお互いの信頼関係を強固なものとして、持続可能な関係を維持していく必要があると思います。新居浜市と住友グループとの共存共栄の下、両者が共に発展していくための信頼関係の構築にどう取り組んでいくのか、お伺いいたします。
新居浜市の経済においては、少子高齢化、人口減少に伴う人材確保対策が最重要課題となっています。近い将来には、受注があっても人材不足が影響し、仕事を受けることができず、経営難に陥り、黒字倒産に至る事業者が生じることが危惧されます。人材不足は、全国的にも問題となっていることは承知しておりますが、新居浜市の企業に対する人材不足の歴史は古く、市やハローワークにおいても数々の支援対策を実施してきましたが、どれも決め手に欠ける状況であります。住友の大手企業でさえ人材確保に苦労されていますが、新居浜市として継続的に経済発展を図るためには、何を差し置いても人材確保対策を大胆かつ早急に財政状況が厳しい状況にあっても取り組まなければならないと考えますが、市長のお考えをお伺いいたします。
次に、企業支援についてですが、新居浜市においては、新居浜市中小企業振興条例補助金等により、市内事業者に対し各種の支援を行っていますが、支援内容がどうしてもものづくり産業を中心としたものになっています。
お手元の資料を確認ください。これは、令和3年の経済センサスの活動調査に基づく新居浜市の産業別事業所数の割合を円グラフにしたものです。令和3年の経済センサス活動調査によると、新居浜市の全事業所数は5,123事業所で、そのうち製造業が7%の約360事業所となっています。それに対し、事業所数が多い業種から順に、卸売業、小売業が26%、宿泊業、飲食サービス業が13%、建設業が11%、生活関連サービス業、娯楽業が10%となっており、この業種で全業種の60%、約3,070事業所を占めております。ものづくり産業が新居浜市の牽引役として重視していることは承知しておりますが、業種別事業所数の調査結果から、60%の事業所数を占める卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、建設業、生活関連サービス業、娯楽業等の製造業以外の業種へも支援の範囲を広げていただきたいと思います。特に、製造業以外の業種は、小規模事業者、いわゆる零細企業が多いことから、額は少なくても構いませんから、補助要件を緩和した使い勝手のよい支援制度の創設をお願いします。この件について古川市長のお考えをお伺いいたします。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) 篠原議員さんの御質問にお答えいたします。
新しい新居浜についてでございます。
まず、市政運営に対する思いについてお答えいたします。
私が市長として大切にしたい基本姿勢といたしましては、常に現場の声を聞き、市民の皆様との対話を何より重視することであり、これからの市長任期の4年間、この姿勢、初心を貫いてまいりたいと考えております。
新しい新居浜に向け、何を変革していくかにつきましては、人口減少や物価高騰など、本市を取り巻く環境は厳しさを増しており、市民の皆様の中にも、閉塞感が漂っていると感じておりますが、この町が持っているポテンシャルを最大限に引き出し、既存の取組を時代に合った形でアップグレードしていくことで、市民の皆様が夢や希望を持てる新しい新居浜へ変革していきたいと考えております。
次に、財政状況についてでございます。
まず、貯金と借金がともに少ない状態と貯金と借金がともに多い状態のどちらが望ましいかについてお答えいたします。
どちらの状態が望ましいのかにつきましては、地方公共団体の財政状況や公共サービスの多寡によって御質問の状態に対する見方は異なってくるものと考えております。しかしながら、本市の財政調整基金残高は、財政規模から勘案いたしましても、また他市との比較においても、非常に少ない状況にございますので、貯金と借金のバランスに注意を払いながら、今後の財政運営を行う必要があるかと考えています。
次に、赤字対策に係る報告についてでございます。
平成30年度から令和3年度までの4年間にかけて、財政調整基金の大幅な取崩しが続いたことから、令和4年度までの5年間で、基金残高が約30億円減少したこと及びそれぞれの年度における社会変動等の特殊財政事情やこれまでの歳出削減に対する取組についての説明は受けております。引き続き、検証も含め、今後の財政運営において、持続可能な財政を維持できるように努めてまいりたいと考えております。
基金減少の原因及び過去の支出削減の在り方の妥当性の調査検討並びに今後の対策を市民の皆様へ提示することにつきましては、丁寧な分析を行い、積極的で分かりやすい情報開示に努めてまいりたいと考えております。
次に、市民への情報発信と対話型行政についてでございます。
私が公約で掲げましたみんなでつくる新しいにいはまの実現のためには、積極的な市民との対話が不可欠だと考えております。このことから、対話型行政スタイル、現場の意見につきましては、私自ら様々な現場に出向き、これまでまちづくりに参加できなかった世代や10年後に主役となる世代とも積極的に対話を進め、より幅広い世代の方に気軽に参加していただけるよう、オンライン開催等も含め、時代にマッチした実施方法を検討してまいります。
そこで話し合った内容の市民への発信につきましては、市のホームページやSNS、広報紙等により、多くの市民の皆様に情報提供が可能となる広報活動に取り組み、きめ細やかに幅広い周知の機会を創出してまいります。
いずれにいたしましても、積極的に現場に足を運び、対話を重ねる機会を拡充し、市民の皆様への情報発信と信頼関係の構築に努めてまいります。
次に、独自政策についてでございます。
実現したいテーマにつきましては、私の公約の柱であります子育て支援の充実、地域経済の活性化、防災能力の強化の3点に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。市長としての公約は、そのほかにもございますが、現在の厳しい財政状況を考慮いたしますと、あらゆる公約を直ちに実施することは難しいと認識いたしております。今後、事業の実績等も確認し、新たな財源確保の可能性も探りながら、独自施策の推進と公約の実現に向けた検討を進めてまいりたいと考えております。
次に、職員の意識改革についてでございます。
まず、私がイメージしている新居浜市役所の組織力、チーム力及び職員像についてお答えいたします。
私自身、これまで市議、県議として多くの職員と関わる機会がございましたが、いずれの方も非常に仕事熱心で能力が高いと感じておりました。新居浜市役所の組織力は、こうした職員の皆さんが、個々の能力を存分に発揮するとともに、チームワークを大切にすることによって最大化されるものであると考えております。
この組織力、チーム力を高めるために、私が職員に期待する職員像といたしましては、いかなるときも、まず市民のために今何をすべきかを自発的に考えることのできる職員であってほしいと思っています。そして、政策立案や日々の業務の中で、困っている市民が優しさやぬくもりを感じてもらえるような市役所でありたいと私は考えています。そのために、法令遵守は当然のことでありますが、常に公平、公正な立場で、相手の意見をしっかりと聞き、同時に自分の考えをきちんと説明することを大切にしていただきたい、そのようなイメージを持っているところでございます。
次に、今後の職員の人材育成につきましては、私自身、学ぶべきことが多い中で、共に切磋琢磨し、議論を重ねながら、一緒に成長していきたいと考えているところでございます。具体的には、派遣研修や日常業務の中での様々な学びを通して、広い視野と先見性を持ち、多様化、複雑化する住民ニーズを的確に捉えることができる人材を育成してまいりたいと考えております。
次に、経済対策についてでございます。
まず、住友グループとの信頼関係の構築についてでございます。
本市が持続的に発展していくためには、住友諸企業とそれを支える地元産業界、行政がそれぞれの役割を主体的に担っていくという関係性を引き続き維持していくことが重要であると考えております。そのため、愛媛県知事、地元産業界の皆様と住友諸企業の本社を訪問するトップミーティングや経済懇談会の開催等による情報交換を含め、信頼関係の深化に努めてまいります。
次に、人材確保対策についてでございます。
本市では、高校生や大学生等を対象とした合同企業説明会の開催、小中高生や産業技術専門校生に対しての企業見学など、様々な人材確保対策を実施しております。若年者をはじめとする労働力の確保は、本市のさらなる経済発展、市政発展のため非常に重要な課題であると考えておりますことから、これまでと異なった視点も含め、人材確保支援に注力してまいりたいと考えております。
次に、小規模事業者に対する支援制度の創設についてでございます。
新居浜市中小企業振興条例補助金等の中小企業者に対する補助制度につきましては、製造業以外の業種や小規模事業者につきましても、原則として補助対象としているところでございます。今後は、来年度に新居浜市中小企業振興条例補助金の見直しを予定していることから、財政状況も考慮しながら検討してまいります。
○議長(小野辰夫) 高橋教育長。
○教育長(高橋良光)(登壇) 郷土愛の育成についてお答えいたします。
子供たちの郷土愛を育成するため、教育委員会では、公民館において、地域教育力向上プロジェクト推進事業を実施しております。具体的な内容といたしましては、地域の方が子供たちと一緒に地域の歴史や文化を探索する事業やとうどおくりやしめ縄づくりなど、伝統行事を子供たちも一緒になって行う事業、七草の由来を学び、七草がゆを一緒に食べるといった三世代交流など、事業を通じて子供たちと地域の方とのつながりが生まれるとともに、郷土を知る重要な機会となっております。
また、はたちの集いにおいては、人生の節目に全市を挙げてお祝いをすることで、改めて新居浜に対する思いを深めてもらい、地元とつながる機会となるよう取り組んでおります。
市内小中学校においては、郷土愛を育む学習として、別子銅山や多喜浜塩田についてのふるさと学習を行っており、学校での学習と公民館での活動との相乗効果により、郷土愛を醸成してまいりたいと考えております。
○議長(小野辰夫) 篠原茂議員。
○21番(篠原茂)(登壇) 答弁ありがとうございました。
2点ほど要望したいと思います。
職員研修の件なんですけど、今年の10月に北海道の東神楽町の山本町長が新居浜市に来られました。そのときにまちづくり推進課、くらしの窓口課、建設水道課の若手職員が一緒に見えられ、泉川のまちづくり、西条市のいとまちマルシェ、今治市のバリクリーンを見学し、そしてそこで意見交換をして帰られました。山本町長は、若い職員が机上の勉強以外に実際に現場を見ての体験が重要ですから一緒に来ましたとお話しされていました。新居浜市でも、若手職員の多くの体験、見聞が、大変重要になると思います。ぜひ職員研修をよろしくお願いいたします。
それから、もう一点、経済対策なんですけど、新居浜市と住友グループの連携強化、これは大変重要な課題です。古川市長は、11月10日に当選後、2日後には新居浜市内の住友企業に挨拶に回り、そして先日には東京の住友本社にも御挨拶に伺ったとお聞きいたしました。今後もフットワークを軽く、住友各社との信頼関係を強固なものとして、持続可能な新居浜市の発展をよろしくお願いいたします。
それでは、続きまして、次の質問に移ります。
これからの公民館について質問いたします。
先ほど大條議員が話されたこととかぶるところもありますけど、よろしくお願いいたします。
中萩公民館と口屋跡記念公民館の2館がモデル館になって、住民自治の拠点となることを目指した実証事業に取り組み、現在も口屋跡記念公民館では独自の新しい公民館づくりを推進しています。しかし、これからの方向性は、まだ見えません。残りの公民館も今後の歩むべき道について不安に感じていると聞きました。私の住んでいる泉川校区では、昨年5月にまちづくり連合自治会の生涯学習部会が企画して、西予市の田之筋地域づくり活動センターに研修にお伺いいたしました。たしか口屋跡記念公民館も西予市に地域コミュニティ課の職員と一緒に研修に行ったと聞いております。私は、この研修で西予市の現在の活動に多くの示唆に富んだアイデアをいただいたので、本市と比較対照して質問させていただきます。
まず、1点目ですが、地域づくり活動センター。
西予市は2年前から全ての公民館を地域づくり活動センターとして市長部局の所管に切り替えたそうです。その基盤には、これまで10年以上、小規模多機能自治を推進するために必要な地域の新しいまちづくり組織をつくるために、交付金制度などを活用して、各地域の特性を踏まえた入念な準備期間があったと伺っております。公民館という施設を新しいセンターにするだけではなく、住民意識を変革し、自分たちの地域を何とかしてよい地域にしたいというムードを醸成してきた、その結果として地域づくり活動センターなるものが立ち上がったと聞きました。
それに比べて、新居浜市の今回の取組は、地域のムードを醸成するための期間も手間も不足していたのではないでしょうか。地域コミュニティ課の職員の方は、西予市の取組から何を感じましたか。西予市の取組を踏まえて、新居浜市では公民館のセンター化についてどのように考えているのか、いつまでにその方向性を示されるのか、まずこの点についてお伺いいたします。
2点目は、人材配置です。
住民自治に対する考え方です。
西予市の人口は、2060年には現在の約3分の1になると推計されているそうです。現在、3万4,000人弱なのが1万2,000人弱になるそうです。この人口減少は、地域の存続にとって大きな課題です。何とかして人口減少を食い止めるために、庁内に人口減少対策のためのプロジェクトチームを立ち上げ、部局の枠を超えて、地域課題に取り組むための具体策を打ち出し、地域活動センターを拠点として、地域づくり組織が当事者意識を持って行政と協働で取り組んでいました。その際に、地域住民と行政をつなげる人材として、係長、課長補佐級の市職員を配置するとともに、地域の諸団体の事務局を担う地域雇いの職員に対する給与を支給しているとのことでした。
新居浜市では、公民館が地域の諸団体の文書の作成に当たっている公民館がありますが、西予市のような人的な補充は行われていないため、主事や主事補の負担増になっているとの声も聞かれます。西予市のように、管理職への登竜門として、地域づくりの最前線を担う経験を積ませる人事や地域が雇用して自分たちの活動を支えてくれる人材を配置する仕組みができないものでしょうか。これからの人材配置に当たっての基本的な考え方をお伺いいたします。
3点目は、公民館版SDGsです。
愛媛県公民館連合会が策定した公民館版SDGsに対して、本市がどのように関わっているのか、お伺いいたします。
国連が定めたSDGsをまねして、愛媛県公民館連合会では、持続可能な公民館にするための16の目標やその下に事業の視点を明示しています。私は、この中にこれからの公民館を考える上で貴重なアイデアがたくさん含まれていると感じています。
本市の公民館では、この公民館版SDGsをどのように活用してきましたか。西予市では、この評価指標を独自に調整して、全センターで分析し、地域の強みや弱みを踏まえて活動に有効活用していました。新居浜市の公民館活動をこのSDGsの目標の方向性と比べてみると、かなりずれている気がします。このSDGsの策定に当たっては、新居浜市の公民館職員も参加したはずなので親しみもあるのではないでしょうか。社会教育課が音頭を取って、職員研修や日常の公民館活動を評価するために活用してみてはいかがと思いますが、お考えをお伺いいたします。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。竹林教育委員会事務局長。
○教育委員会事務局長(竹林栄一)(登壇) これからの公民館についてお答えいたします。
公民館版SDGsについてでございます。
令和4年度に愛媛県公民館連合会において策定された公民館版SDGsは、公民館をさらに発展させていくための16の目標と各目標の達成度をはかるための5つのチェックポイントから成り立っております。
本市におきましても、昨年度の公民館職員研修会において、公民館版SDGsの策定に関わられました若松進一氏を講師に迎え、公民館版SDGsの目的について学ぶ研修を実施し、各公民館の取組に生かしていくよう努めております。
また、愛媛県教育委員会が主催する公民館活動活性化ステップアップセミナーや愛媛県公民館研究大会において、本市の公民館職員が、公民館版SDGsの目標達成に向けた人づくりや情報発信などに関する取組の事例発表を行っております。
次に、公民館活動を評価するための公民館版SDGsの活用につきましては、目標や評価を意識することで、現在の取組の改善につながりますことから、各公民館でのさらなる積極的な活用を促してまいりたいと考えております。
○議長(小野辰夫) 長井市民環境部長。
○市民環境部長(長井秀旗)(登壇) 地域づくり活動センターについてお答えいたします。
西予市では、人口減少社会に立ち向かうことができる持続可能な住民自治を目指し、令和5年4月に公民館を一斉に地域づくり活動センターに移管し、社会教育を推進する場に加え、支え合い、つなぎの場や地域づくりの場等の機能や役割を拡充し、地域の身近な公共施設として、人口減少における地域課題に直面する地域を現場で支える仕組みを構築しています。
また、公民館のセンター化に併せて、公民館分館制度の見直しや支所配置人員の削減、センターでの業務拡充を行っており、西予市では、市町合併の経緯から、従来から公民館の分館制度が存在していたことや公民館に支所機能を付与されていたことなど、本市と相違するところがありますが、将来にわたって持続可能な地域基盤を形成し、行政主導による行政サービスだけではなく、行政と地域の協働の取組による新たなサービスの創出にもチャレンジしていく等の西予市の取組につきましては、これからの本市公民館の在り方を検討していく上で大変参考になる事例であると感じております。
西予市では、人的支援及び財的支援を行いながら、既に27の旧小学校区で地域づくり組織が発足している中でのセンター化に取り組んでおります。
本市におきましても、教育委員会とも連携しながら、今後の公民館の役割、機能、事業展開等、地域住民の皆様と十分な協議を重ね、検討を進め、またモデル校区での活動状況について、中長期的な期間での検証を行いながら、まずは地域運営組織の形成について取り組んでいきたいと考えております。
次に、人材配置についてでございます。
市職員の配置につきましては、今後公民館の在り方が定まった時点で、その円滑な運営に必要な人材につきまして人事担当部局と協議してまいりたいと考えております。
また、地域任用職員の配置につきましては、地域運営組織の活動を円滑に進めていく上で、地域の現状をよく理解する人材の配置は大変有効であると考えておりますため、地域の意向も踏まえながら、また市職員の人員配置も勘案し、その必要性について判断してまいりたいと考えております。
○議長(小野辰夫) 篠原茂議員。
○21番(篠原茂)(登壇) 地域運営組織は、宮西校区、中萩校区でスタートいたしましたが、この3年間の取組をどのように評価していますか。
また、これから先はどのような日程で進むのか、教えてください。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。長井市民環境部長。
○市民環境部長(長井秀旗)(登壇) 篠原議員さんの御質問にお答えをいたします。
モデル校区の成果についてどのように考えているかという御質問でございました。
これまでの宮西校区ではございますけれども、モデル校区の成果といたしましては、地域の代表制を持つ運営組織が設立されたこと、ホームページやお知らせなどの全戸配布による地域への情報発信の強化が図られたこと、部会による事業企画と執行による地域課題の解決が推進されていること、地域の学校との連携の強化あるいは保護者の事業参画などが図られていることなどが一定モデル校区の成果として考えております。
今後につきましては、まちづくりや事業への参加者数の推移あるいは地域課題への取組の成果、課題の解決数、参加世代の変化、団体との連携状況、ホームページの訪問者やSNS発信などの情報発信の頻度、自己財源の取組などにつきまして、地域の声も参考に、また経過年数による推移も含めて評価を進めていきたいと考えております。
それから、期間の御質問でございました。いつまでにという期限を申し上げるのは非常に困難ではございますけれども、宮西の成果を確認しながら、まずは全校区において地域運営組織の設立を目指していきたいというふうに考えております。
公民館につきましては、地域の皆さんの意向も尊重しながら、今後どうしていくかも含めて、先ほど申し上げました機能や運営方法なども含めて今後検討を進めていきたいというふうに考えております。
○議長(小野辰夫) 篠原茂議員。
○21番(篠原茂)(登壇) 長井部長は、自治会の加入率のことをお話しせんかったんですけど、宮西校区の自治会の加入率は、案外低いですよね。でも、自治会の加入率のことは、今からあまり言わなくてもいいんじゃないかなと私の個人的な考えでは思っております。泉川校区でも、自治会加入率が物すごく減ってますから。自治会の加入率を上げるということに力を注ぐことはそう必要ないんじゃないかと思うたりもします。そして、宮西校区でお話をしてみますと、やはり災害のときの助け合い、そのときは自治会に入っとろうが、入ってなかろうが、校区の人が全員このような活動に参加できるようなことをしていきたいというようなことを話しておりましたけど、なるほどそのほうがいいなとは感じました。
それから、西予市の場合は、市長部局に地域づくり活動センターを置いてますけど、新居浜市も市長部局に移管するつもりでしょうか。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。長井市民環境部長。
○市民環境部長(長井秀旗)(登壇) 篠原議員さんの御質問にお答えをいたします。
公民館を市長部局に移管するのかどうかというお話でございました。
私の部局では、地域運営組織の取組を行っておりますので、その関連から答弁をさせていただきたいと思います。
私は、長年取り組んできました地域主導型の公民館につきましては、地域主導で地域が主体性を持って様々な学びや公民館活動を行うことを通じて、地域の未来を担う人づくりを進めてきたものと思っております。
今後の公民館につきましては、地域の方が集い、そして話し合い、10年後、20年後を目標に、誰もが孤立することなく、住みやすい地域づくり、まちづくりを進めるため、これまでの公民館の機能や役割を一層進化させ、地域のネットワークの拠点にしたいというふうに考えております。地域の人にとって使いやすい施設となりますように、地域のニーズも踏まえまして、市民部局へ移管するということも選択肢の一つとは考えておりますけれども、今後地域の皆様との協議も含めて、庁内全体で今後の在り方を検討していきたいというふうに考えております。
○議長(小野辰夫) 篠原茂議員。
○21番(篠原茂)(登壇) よろしくお願いいたします。
先日の愛媛新聞紙上のお話ですけど、今大條議員さんが藤目先生のお話ししたんですけど、藤目先生の内容を大條議員さんが発表しなかったから、私が代わりに発表するんですけど、藤目先生は、組織やそれぞれの地域が自立しても、自分たちの頭で考え、実践しなければ、どんなシステムをつくっても駄目だと言っています。私も同感です。実践を通じて、新しい新居浜を創造していく思いを伝えまして、次の質問に入ります。
農業振興地域についてお伺いいたします。
市中心部新須賀町、田所町、八雲町、庄内町のうちの農業振興地域の見直しについて質問いたします。
本年6月20日の本会議にて、宮崎経済部長から、令和7年3月までに意向調査を実施し、基礎調査を取りまとめて、令和8年3月までに50年ぶりの農業振興地域整備計画書の全体見直しを取り組むと答弁されましたが、現時点での進捗状況を教示ください。
また、指定解除と同時進行にて、この地域の経済活性化のためには、特定用途制限地域を用途地域へ都市計画の変更をして、固定資産税等の税収アップに向けての必要があると思いますが、新居浜市のお考えをお伺いいたします。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。宮崎経済部長。
○経済部長(宮崎司)(登壇) 農業振興地域についてお答えいたします。
農業振興地域の見直しの進捗状況についてでございます。
現在、意向調査のための全対象農用地の選定、地番の分筆、合筆の整備、所有者の確認、調査内容の検討などの準備作業を進めているところでございます。数十年ぶりの計画見直しに向けた取組でございますことから、準備作業に想定以上の時間を要しておりますが、年度内をめどに意向調査を実施し、来年度基礎調査結果を取りまとめ、県との協議を進めてまいります。
○議長(小野辰夫) 高橋建設部長。
○建設部長(高橋宣行)(登壇) 用途地域の指定についてお答えいたします。
用途地域の指定は、前提として、都市の拡大、成長による無秩序な市街地の拡散を抑制し、計画的な市街地の形成をすることを目的としており、地域の特性に応じた土地利用を定めることで、都市の将来像を実現していくものでございます。
しかしながら、近年急速に進行していく人口減少や少子高齢化社会においては、都市を収縮しながら暮らしやすさを損なわず、インフラ投資の効率化等による持続可能な都市経営を確保したまちづくりを実現していくことが求められており、本市におきましても、既存ストックを有効活用しながら、コンパクトなまちづくりを推進していくことを目指しております。
当該地は、現在農用地及び農業振興地域に指定されており、土地利用については、都市計画と農業との健全な調和を図りつつ、土地利用及び諸施策との十分な調整が必要であるため、今後農政部局の進捗状況に応じ、関係機関と協議を行ってまいります。
なお、税収増加につきましては、農用地の指定解除後は、特定用途制限地域の土地利用規制に応じた建築物の立地が促進されることによる税収増が期待されること及び既に公共下水道の事業計画区域のエリアとなっておりますので、都市計画税が賦課されることが見込まれます。
○議長(小野辰夫) 再質問はありませんか。篠原茂議員。
○21番(篠原茂)(登壇) 答弁ありがとうございました。
意向調査なんですが、意向調査は割かし簡単だと言ったら失礼なんですけど、案外スムーズに進むんですけど、基礎調査になりますと、それはもう莫大な、今宮崎部長も言われておりましたけど、資料もたくさんそろえなくてはいけないので、ぜひ早めに段取りをして、またいろいろな職員の応援なども要るかも分かりませんけど、それらのことを考えていただきまして、順調に進めていただくことをお願いして、質問を終わります。ありがとうございました。
○議長(小野辰夫) この際、暫時休憩いたします。
午後 0時01分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午後 1時00分再開
○議長(小野辰夫) 休憩前に引き続き会議を開きます。
藤原雅彦議員。
○20番(藤原雅彦)(登壇) 公明党議員団の藤原でございます。
本来では、初めはおめでとうございますとの挨拶をすべきところでございますが、私は現在、新居浜市を取り巻く状況を顧みたとき、市長選に立候補された勇気、そして市長に就任し、困難に立ち向かい前進されようとする勇気に古川市長に対し、最大の敬意を払います。
それでは、通告に従い質問をさせていただきます。
まず、1番目、市政運営の基本姿勢についてお伺いいたします。
午前中に篠原議員さんが、多くの質問をしました。どんな答弁が来るか心配しておりますが、明快な答弁をよろしくお願いいたします。
古川新市長が就任され、初めての議会ということで、市政運営の基本姿勢について質問させていただきます。
新しいリーダーを迎えた新居浜市において、市民が抱える期待や課題は多岐にわたっています。これらにどのように向き合い、政策を進めていくのかが重要です。古川市長がどのようなビジョンや価値観を持って市政運営に臨まれるかは、市民全体の暮らしや地域の未来に直結するものです。そのため、以下の点について市長の御所見をお伺いいたします。
市長に就任し、ますます市民との対話を重ねられることになりますが、どのように市民の意見を取り入れ、市政に反映させていくのでしょうか。例えば、市民の声を行政に反映させるための市民参加型の政策立案プロセスや定期的な対話の場の設置など、具体的なものがあればお示しください。
市政運営において、行政の透明性と説明責任を果たすことは、市民の信頼を得るために欠かせない要素です。特に、政策決定や予算執行に関する情報公開については、多くの市民が関心を寄せております。市長として透明性を確保するための具体的な取組方針をお聞かせください。
また、政策の成果や課題をどのように市民に伝え、説明していくか、お考えをお伺いいたします。
先ほど述べたように、新居浜市が直面する課題は、非常に多岐にわたります。例えば、財政再建、少子高齢化問題では、子育て支援策や高齢者福祉の強化、地域経済の活性化では、企業誘致や観光振興、防災・減災では、インフラ整備や市民への啓発活動など、市長としてどの課題を最優先に取り組むべきと考え、それぞれの課題に対する優先度をどのように考えておられるのでしょうか、お伺いいたします。
特に、11月18日の初登庁に伴う市長挨拶に、まずは財政の健全化と不測の事態に備えた財政調整基金の立て直しを行うとともに、未来に向けた種まきも行いたいと考えていますと述べられています。市長選において、新居浜市の財政運営に対し、めり張りのないばらまき行政と指摘されていました。市長就任後、担当部局より財政の状況をお聞きかと思いますが、どのような御所見をお持ちでしょうか、お伺いいたします。
また、財政調整基金の立て直しですが、現在の経済環境や将来を見据えた際に、財政調整基金の適正な規模について、古川市長はどのように考えておられるのでしょうか、具体的な積立目標額がある場合はお示しください。
また、同じく、市長挨拶に、最少の経費で最大の効果を上げることと言われておりましたが、新居浜市の近年における一般会計当初予算は、コロナ禍もありましたが、500億円余りで推移しています。このことから、予算計上をする上での目標金額、新居浜市の適正な当初予算規模をどのように考えておられるのでしょうか、お伺いいたします。
市政運営は、市長だけでは成り立ちません。市長挨拶では、多くの施策や熱い思いを実現するためには、私一人の力で実現することはできませんと述べられておりました。当然ながら、市役所職員と力を合わせ、一体となって市民サービスの向上に取り組むことが重要だと思います。市長として、職員の意欲を引き出し、より効果的な市政運営を行うために、どのような組織づくりを目指すのでしょうか。
また、働きやすい環境づくりや人材育成についてのお考えをお伺いいたします。
地方自治は、市民から選ばれた首長と、同じく市民から選ばれた議員で構成される議会の二元代表制で成り立っております。この二元代表制をより効果的に機能させるには、首長と議会の連携強化が大事とされております。そのために、議会との情報共有や意見交換などを経て、政策に反映させることも重要と考えますが、市長の御所見をお伺いいたします。
また、このことについて、何か具体的な取組があればお示しください。
1番目の最後として、市長として新居浜市の未来をどのように描いているのか、そのビジョンをお聞かせください。特に、SDGs、持続可能な開発目標の達成に向けた取組や若い世代が住み続けたくなるまちづくりへの施策について、市長の考えをお伺いいたします。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) 藤原議員さんの御質問にお答えいたします。
市政運営の基本姿勢についてでございます。
まず、市民の意見をどのように市政に反映するのかについてお答えいたします。
私は、市民が主役の新しい新居浜を実現するため、対話を基本とした市政運営に取り組んでまいりたいと考えております。このため、積極的に市民の皆様との対話を重ね、信頼関係を構築した上で、各施策を推進してまいりたいと考えております。
また、市民参加型の政策立案プロセスや定期的な対話の場につきましては、まずは市民や外部有識者に参画いただいております各種会議等の状況を確認した上で、より幅広い各層の方々が参加し、意見を出しやすい柔軟な形態となるよう、オンライン等のデジタル技術の活用促進も含め検討してまいります。
次に、市政の透明性を確保するための方針についてでございます。
市政の透明性の確保は、行政の公平性や信頼性を高めるとともに、情報の共有を通じ、市政を身近に感じてもらい、市民の市政参画の機会につながるなど、市民目線による市政運営の基本となるものであると考えております。
そうした認識の下、広報紙やホームページだけでなく、様々な情報媒体を活用し、市民の皆様に対し情報発信を行うとともに、積極的な情報公開を進めてまいります。
また、必要に応じて、私自身が直接説明するなど、透明性のある市政運営を心がけてまいります。
次に、課題の優先度についてでございます。
まず、公約の柱として、子育て支援の充実や地域経済の活性化、そして防災能力の強化について積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
また、こうした取組の推進には、新たな予算措置や財源の確保も必要となりますことから、未来を見据えた公益性の観点に基づく施策の必要性を判断するとともに、今後の社会環境に適した効率的で無駄のない行財政運営を目指してまいります。
次に、財政状況に対しての所見についてでございます。
財政状況につきましては、財政調整基金に依存した財政運営がされていたことから、現在、基金残高が著しく減少しており、非常に厳しい状況にあると考えております。
次に、財政調整基金残高の適正規模につきましては、平成16年の豪雨災害時の災害復旧に要した費用を考慮し、標準財政規模の10%から20%程度の30億円から50億円の基金残高が必要と考えており、目標額につきましては、財政状況を見ながら、長期的な視点で計画的に設定してまいりたいと考えております。
次に、予算計上目標額及び当初予算の適正規模についてでございます。
当初予算の適正規模につきましては、社会情勢に変動のない平時におきましては、本市の財政状況を勘案いたしますと、現時点では500億円程度が適正であると考えております。しかしながら、政府や愛媛県の予算規模も、社会情勢の変動に伴い増加傾向にあることから、令和7年度当初予算における計上目標額を含め、現時点でお示しすることは困難でございます。
次に、職員の意欲を引き出し、より効果的な市政運営を行う組織づくりについてでございます。
職員が意欲的に職務に取り組むためには、職員個々の業績に対する評価が正しく行われることが重要であり、その評価に基づき、適材適所で人材を活用してまいりたいと考えております。
効果的な市政運営のための組織づくりにつきましては、その時々の市民ニーズや課題に対応できる効率的な組織を目指してまいります。
次に、働きやすい環境づくりにつきましては、職員がやりがいや充実感を感じながら、それぞれの職責を果たすことができるよう、ワーク・ライフ・バランスにも配慮してまいります。
人材育成につきましては、全ての職員が、日常業務を通して、組織全体で広い視野と先見性を持って多様化、複雑化する住民ニーズを的確に捉えることができるよう取り組んでまいります。
また、異動、昇任、昇格と人事評価、研修などを総合的に連携させた人事マネジメントを確立し、職員の意識改革と人材育成を図ってまいります。
次に、議会との情報共有や意見交換についてでございます。
私は、笑顔あふれる人に優しいまちづくりを目指し、市民一人一人の声を丁寧に拾い上げる姿勢を大切にしていきたいと考えており、この姿勢は、議会との対話、連携にも通じるものと認識をいたしております。私自身も議員経験者として、様々な政策形成段階において、議会の皆様と情報を共有し、積極的な議論を交わすことで、本市が抱える課題に対応した最善の道筋を模索してまいりたいと考えております。
次に、未来へのビジョンについてでございます。
本市は、令和4年にSDGs未来都市に選定され、官民を挙げて市内全域でSDGsに関する取組の輪を広げる活動を展開しております。そうした持続可能な町の実現に向けた取組は、未来を担う世代が、安心して暮らし、夢を描ける環境づくりに結びつくものと考えております。
また、先ほど子育て支援の充実に取り組みたいと申し上げましたが、子育てに関する相談体制の充実や経済的負担の軽減、教育環境の整備を通じ、四国で一番の子育て支援を目指すことで、若い世代が新居浜市で暮らし続けたいと心から思ってもらえるよう、取り組んでまいります。
○議長(小野辰夫) 藤原雅彦議員。
○20番(藤原雅彦)(登壇) 答弁をいただきました。今、私が一番感じているのは、これは皆さんそうだと思うんですが、大事なのは財政再建だと思います。やはり、様々な公約を実現するためには、財政的基盤、財政的な裏づけがないと公約は実現できないと思います。「歴史は繰り返す」ということわざがあります。今までも新居浜市は、行財政改革に取り組んだ時代がありました。私が初当選した平成15年に122億円余りの財源不足が判明し、創造の10年へ!5%の行政経営改革をスローガンの下、財政改革の取組の中、平成16年の豪雨災害に見舞われ、その復旧・応急対策への財源として、財政調整基金からの予期せぬ財政支出があり、平成17年度以降の新居浜市の財政状況は、まさに危機的な状況になりました。この危機を乗り越えるため、より一層10か年戦略プランを加速させました。具体的な取組としては、経常的経費はもちろんのこと、当時の駅前土地区画整理事業の延期やそしてあらゆる施策について見直しを行い、財政構造の変革に取り組みました。特に、各種団体においては、今まで支出されていた補助金が減額、廃止となり、事業ができなくなる事態も生じ、市民生活や市民協働活動に多分に影響を及ぼすこととなったわけであります。しかし、将来の新居浜市のために、当時佐々木市長は、不退転の決意で財政再建に取り組み、粘り強く市民との対話を重ねた結果、全国の自治体の中でもトップクラスと言えるような財政再建をなし得、そして石川市政へとつなげたわけでございます。その渦中においては、恐らく古川市長も市議会議員として4年間おられたと思います。多分そのことは覚えているかと思います。つまり、佐々木市政の3期12年は、財政再建の12年間だったと言えます。
このことを踏まえ、再度古川市長の財政再建に対する決意をお聞かせください。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) 藤原議員さんの御質問にお答えいたします。
今お話しがありましたように、私自身も市議会議員当時、財政再建の道半ばの中で、大変苦しい思いをしたということを覚えております。市民の皆様にも、随分と我慢をしていただいたことで立て直したというようなことや、また厳しい意見もかなりいただいたことも覚えております。そのようなことも考えながら、やはり財政再建は、私自身が先頭に立って進めなければならない重要な課題だと考えており、まずは現状を把握し、市民の皆様に理解していただくことから始めたいと思います。財政再建には、痛みも伴うことがありますが、未来を生きる子供たちに誇れる新居浜市を残すため、市民の皆様、議員の皆様、そして職員と対話を重ね、議論を重ねながら取り組んでまいりたいと考えております。
○議長(小野辰夫) 藤原雅彦議員。
○20番(藤原雅彦)(登壇) 先ほど冒頭部分で古川市長の勇気に対して最大の敬意を払うということを言わさせていただきました。今財政再建において、これから大事なのは、勇気とともに不退転の決意が僕は大事かと思います。そういった意味で、今期の4年間、どうか財政再建に向けたその不退転を忘れることなく突き進んでいただきたいことを要望いたします。
続きまして、2番、103万円の壁についてお伺いいたします。
これは、最近、10月の国政選挙が終わって、急にこの103万円の壁が毎日テレビで放送されております。まだまだ政府の中ではどういうふうになるか決まっておりません。あくまでも私が考えた想定の中での質問でございます。答えられる範囲で結構でございますので、何とぞ答弁よろしくお願いいたします。
103万円の壁とは、配偶者控除の適用要件である年収103万円以下という基準を指します。この基準は、長年配偶者の働き方や家計の収入構造に影響を与え、特に女性の就労調整の原因の一つとなってきました。政府は、現在、この壁を撤廃し、パート労働者を含む多様な働き方を促進する税制改正を検討していると報じられております。この改正が実施されれば、労働市場全体に変化が生じ、地方自治体における税収にも影響を及ぼす可能性が高いと考えます。
そこで、以下の点について見解をお伺いいたします。
まず、新居浜市におけるパートタイム労働者や配偶者控除を受けている世帯の実態についてお伺いいたします。
市内で配偶者控除を受けている世帯数や、そのうち103万円の壁の影響を直接受けている可能性がある世帯について、その実態を把握しているのでしょうか、お伺いいたします。
103万円の壁撤廃による経済効果は、世帯収入の増加、消費支出の拡大、ひいては地域経済の活性化につながる可能性があります。しかし、一方で、市税収への影響、特に住民税減収の可能性も懸念されております。
住民税減収の可能性を踏まえ、新居浜市では財政運営にどのような影響を想定されているのでしょうか。できれば具体的な減収額の試算とその財政への影響についてお伺いいたします。
ちなみに、11月21日付の愛媛新聞に、年収の壁が178万円に引き上げられた場合の県内の歳入影響として、個人住民税、地方交付税、合計約260億円の減収となるようです。このように、減収分を補うための財源確保策、あるいは歳出削減策について、具体的な計画などは考えておられるのでしょうか、お伺いいたします。
103万円の壁が撤廃されることで、働き方の自由度が増し、パートタイムや非正規労働者の収入が増加することが期待されております。これにより、市内での消費活動が活発化し、結果として地方税収が増加する可能性も考えられます。
新居浜市として、就労促進による地域経済への波及効果についてどのように認識されているか、お伺いいたします。
また、女性の就労環境の変化についても、重要な視点であると考えます。この改正を契機に、女性が働きやすい環境づくりを進めることが、新居浜市の課題となると考えますが、市としてどのような認識をお持ちでしょうか、お伺いいたします。
市内企業への働きかけや保育施設の拡充といった取組が具体的に考えられると思います。税制改正に伴い、自治体としてシステム改修や広報活動、住民への説明対応など、新たな負担が発生することが予想されております。特に、住民税の計算方法や申告内容の変更が生じた場合、税務担当部局の業務量が増加する可能性があります。
新居浜市として、このような負担増にどのように対応し、円滑な運営を図るお考えでしょうか、お伺いいたします。
103万円の壁見直しに関する情報を市民に的確に伝えるための具体的な計画について、これからの将来のことになるんですが、周知活動や相談窓口の設置など、市民の理解促進につながる具体的な施策などは検討されているのでしょうか、お伺いいたします。
この改正が、地域社会に与える影響をどう評価し、市民の生活の質の向上につなげるかについて市長の御所見をお伺いいたします。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。加地企画部長。
○企画部長(加地和弘)(登壇) 103万円の壁についてお答えいたします。
まず、減収額の試算と財政への影響についてでございます。
愛媛県が公表した市町への影響額の試算では、住民税約170億円、地方交付税約90億円となっており、この結果から、本市の減収額を試算いたしますと、住民税が約15億3,000万円、地方交付税が約3億1,000万円、合計18億4,000万円と推計いたしております。
住民税の減収と地方交付税の減少は、歳入予算に直接影響を与えることになりますので、財政運営上、看過できない重大な問題であると捉えておりますが、この歳入減少に対する国の財政措置がどの程度の規模になるのかにより、その及ぼす影響は異なってまいりますことから、国の動向を注視してまいりたいと思います。
次に、減収分を補うための具体的な計画についてでございます。
住民税の減収等の影響は、不透明な点が多くございますが、その影響は一時的なものではなく、継続的なものになると考えます。このことから、一時的な財源確保で対応することには限界があるため、国への要望と併せ、これまで以上に財政調整基金に依存しない歳入準拠の予算編成と財政運営のため、さらなる歳入の確保と歳出の抑制に努める必要があると考えております。
次に、地域社会に与える影響に対する評価と市民生活の質の向上についてでございます。
この改正により、より自由な働き方が可能になり、市民生活の質の向上や企業活動へも一定の好影響を与えるのではないかと期待をしているところでございます。
一方、税制改正に伴う減少分に対する国の補填がない場合には、道路や公園などのインフラ整備や福祉サービス、ごみ処理など、市独自で行っている住民サービスに大きな影響があるものと考えておりますことから、今後の国の議論を注視してまいりたいと考えております。
○議長(小野辰夫) 髙橋総務部長。
○総務部長(髙橋聡)(登壇) 配偶者控除を受けている世帯数と103万円の壁の影響を受ける可能性がある世帯の実態把握についてお答えいたします。
配偶者控除を受けている世帯数につきましては、令和6年度市民税において、令和6年12月4日現在、1万3,204世帯でございます。このうち、103万円の壁の影響を受ける可能性がある世帯につきましては、現在国で行われております議論の中で、既に配偶者控除の対象となっている世帯は、控除対象となる基準が変更となりましても、引き続き配偶者控除の対象の範囲となることが想定されますので、税額への影響は大きくないと考えております。
次に、市民税課税事務の負担増への対応についてでございます。
大規模な税制改正があった場合には、事務の負担も相当程度増加するものと考えられますが、事務内容の変更に伴うシステム改修など事前に十分な検討と準備を行い、円滑な運営を図ってまいりたいと考えております。
次に、広報等の検討状況についてでございます。
今回の改正の議論は、令和7年度税制改正として検討が進められておりますが、対象とする範囲、金額、手法及び時期等は未定で、現時点で具体的な施策をお示しすることはできませんが、税務署、愛媛県、そして法人会や青色申告会とも連携を図り、広報や相談窓口の設置等により、市民の理解促進に努めてまいりたいと考えております。
○議長(小野辰夫) 長井市民環境部長。
○市民環境部長(長井秀旗)(登壇) 103万円の壁の改正を契機として、女性が働きやすい環境づくりを進めることについてお答えいたします。
103万円の壁が撤廃されることにより、これまで以上に女性が働きやすい職場環境づくりが重要となりますことから、女性自ら意識と能力を高めるための学習機会の提供や職場、家庭、地域におけるワーク・ライフ・バランスの推進のための各種講座の開設や情報の提供等を実施していくことが必要になると認識いたしております。
本市では、男女共同参画社会基本法の基本理念に基づき、令和3年に第3次新居浜市男女共同参画計画を策定し、女性の社会参画の促進を図っております。また、新居浜市女性活躍等推進事業所認証制度を設け、仕事と家庭、地域生活の両立支援や男女が共に働きやすい職場環境づくり、女性の能力活用に向けた取組を行う事業所の認証を行うとともに、これからの新居浜の未来を担う企業等の若手・中堅女性リーダーの育成を図るにいはま女性ネットワーク活動の支援をいたしており、今後におきましても、さらなる男女共同参画社会の実現に向け取り組んでまいります。
○議長(小野辰夫) 宮崎経済部長。
○経済部長(宮崎司)(登壇) 就労促進による地域経済への波及効果についてお答えいたします。
103万円の壁の撤廃で、パートタイム等で働く方が、収入の上限を気にせずに働けるような税制等の改正となった場合、可処分所得の増加による消費支出の一定の増加や労働時間の増加による人手不足の緩和などが予想されますことから、地域経済への効果も一定期待できるものと考えております。
次に、改正を契機として、女性が働きやすい環境づくりを進めることについてでございます。
103万円の壁の改正に伴い、これまで以上に就労する女性や労働時間を増加させる女性が増えることが予想されますが、女性の活躍を期待する企業にとりましては、女性に選ばれる企業となる必要があるものと考えております。そのため、本市といたしましては、現在実施しております労働環境の改善のために要した費用の一部を補助する労働環境改善事業や誰もが働きやすく、活躍できる職場づくりを目指している企業を認定する新居浜市働き方改革推進企業認定制度などの事業を引き続き実施し、このような事業を通じ、女性が働きやすい職場づくりを推進していく企業の取組を支援してまいります。
○議長(小野辰夫) 藤原雅彦議員。
○20番(藤原雅彦)(登壇) 103万円の壁は、先ほど言いましたように、国ではまだまだ具体的なことが決まってなくて、私のほうから想定という形で質問させていただきました。たくさんの答弁をいただきまして、誠にありがとうございます。改めて、想定に対する答弁を本当に丁寧にしていただいたことを心から感謝いたします。ありがとうございました。
103万円の壁というのは、単なる税制改革ではなく、先ほど言いました地域の労働力確保や経済活性化、さらにはジェンダー平等の促進にも寄与する可能性を秘めております。新居浜市がこの機会を活用し、市民の利益を最大化する施策を展開するよう、要望いたします。
続きまして、3番目、GIGAスクールで整備された端末の更新についてお伺いいたします。
GIGAスクール構想は、2019年12月に文部科学省が補正予算を計上したことに始まり、児童生徒に1人1台の端末を配備し、個別最適な学びをICT端末を活用して実現していく構想です。翌2020年の新型コロナウイルス感染拡大に伴い、子供たちの学びの機会を守るため、急速に普及し、今年8月現在、GIGAスクール端末は、全国で約950万台に上るそうです。
新居浜市において、これらの端末が来年度から順次更新時期を迎えていくとお聞きしております。GIGA第2期では、政府の負担で都道府県に基金を創設し、原則として都道府県ごとの共通仕様書を基に共同調達することになっており、調達の大型化が予想されております。
新居浜市においては、来年度以降、何台の端末を更新されるのでしょうか、お伺いいたします。
都道府県に基金を創設しとありますが、どのように運用されるのでしょうか。基金ですから、新居浜市として幾ら拠出されるのでしょうか。また、端末の更新において、新居浜市として負担額はどれぐらいになるのでしょうか、お伺いいたします。
都道府県を中心とした共同調達などとありますが、端末の調達は、どこが窓口になるのでしょうか、お伺いいたします。
次に、新たに更新する端末の選定についてですが、児童生徒の学びを最大限に支援するためには、端末の性能だけではなく、操作性、安全性、そして教育目的に応じた適切な仕様が求められております。現状の端末使用状況や教員からのフィードバックをどのように活用し、更新端末の選定基準を設定するのか、具体的な方針があればお伺いいたします。
また、OSの選定やクラウドサービスの活用におけるセキュリティー対策についても新居浜市としてどのように対応を検討しているのか、お伺いいたします。
GIGAスクール構想が開始されて以降、ICTを活用した教育の効果が様々な形で報告されております。
一方で、大きな予算を投入して、整備された端末が十分に活用されていないケースや使用状況に大きなばらつきがあるとの指摘もあります。これまでの端末活用状況について、新居浜市としてどのような検証を行ってきたのでしょうか、お伺いいたします。
使用済み端末の廃棄やリサイクルについてお尋ねいたします。
ICT端末の更新には、環境負荷が伴います。廃棄物を適切に処理するだけではなく、可能であれば再利用やリサイクルを進めることが重要ではないでしょうか。
新居浜市では、使用済み端末の処理について、どのような計画を立てられているのでしょうか。
また、SDGsの観点から、どのように環境負荷軽減に取り組んでいかれるのでしょうか、お伺いいたします。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。高橋教育長。
○教育長(高橋良光)(登壇) GIGAスクールで整備された端末の更新についてお答えいたします。
まず、新居浜市立小中学校における端末の更新につきましては、令和2年度に導入いたしましたタブレット端末のリース期間が満了いたしますことから、令和7年度に約9,500台の端末を更新する予定としております。
次に、都道府県に創設される基金の運用につきましては、都道府県が基金を設置し、補助事業を創設した上で、市町村が直接この補助事業に申請するものでございます。
なお、基金は、文部科学省からの基金造成経費により創設されることから、市町村の拠出はございません。
次に、端末の更新に係る本市の負担額につきましては、基金の補助率が3分の2となりますことから、端末経費の残り3分の1を負担することとなります。現在、機種の選定中でありますことから、費用については確定しておりませんが、令和7年度当初予算計上に向け精査を行ってまいります。
次に、共同調達に係る窓口につきましては、愛媛県教育委員会及び各市町教育委員会の関係課長で構成する愛媛県GIGAスクール推進協議会で端末の選定や調達を行うこととなっております。
次に、更新端末の選定に向けた現状の端末の使用状況やフィードバックにつきましては、令和6年1月に、全教職員にアンケートを行い、意見を集約いたしております。その中で、現端末機について、小学校においては、写真、動画撮影など、ICT機器になれ親しむことには一定の成果があった一方で、タイピングなど今後子供たちに必要となる能力についても定着が必要という意見もあり、更新時には考慮してまいりたいと考えております。
次に、セキュリティー対策につきましては、ウイルスなどの攻撃を受けにくいシステムソフトウエアを採用するほか、児童生徒用端末と教員用端末のネットワークへのアクセス権限を分けることで、機密性の高い情報へのアクセスを制限するとともに、教員用端末には学習系、校務系両方のネットワークへのアクセス権を付与することで、情報連携と業務の効率化を図ってまいります。
次に、これまでの端末活用状況の検証につきましては、教員向けアンケートを行った結果、85.7%の教員が積極的に活用している、できるだけ活用していると回答しており、教育委員会としましては、残る14.3%の教員に対し、現状を把握した上で指導を継続し、活用率とスキルの向上に取り組んでまいります。
次に、使用済み端末の処理につきましては、本市では、リース契約により運用していることから、端末を返却するため、廃棄はいたしませんが、返却先において適正な手続の下、データ消去を行い、リユースや原材料への再資源化を行うと伺っております。
○議長(小野辰夫) 藤原雅彦議員。
○20番(藤原雅彦)(登壇) 端末活用状況の検証についてですが、IT教育先進国と言われている北欧諸国では、タブレットを活用した学習を進めてきた中で、現在それに逆行する流れが生まれつつあるようです。IT先進国と言われたスウェーデンでは、2023年8月中旬から始まった新学期では、全土の学校で印刷された本や静かに本を読む時間、手書きの練習に重点が置かれるようになりました。タブレットを使った自主的なオンライン調査、キーボード操作のスキルに割く時間は減らされたそうです。その背景にあるのが、2016年から2021年にかけて、スウェーデンの児童の読解力が低下しているとされています。このことから、スウェーデンのカロリンスカ研究所において、デジタル情報源から知識を得るのではなく、印刷された教科書と教師の専門知識を通じて知識を得ることに重点を戻すべきだと考えているとの声明を発表しました。
このことを踏まえ、世界的にIT教育先進国であったスウェーデンにおいても、子供たちの成長期におけるタブレット使用を減らし、紙と鉛筆のアナログ教育に戻す計画が発表されております。子供たちのタブレット使用における学力低下の議論がある中で、教育委員会としてどのような認識をお持ちでしょうか、お伺いいたします。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。高橋教育長。
○教育長(高橋良光)(登壇) 藤原議員さんの御質問にお答えをいたします。
タブレット使用に関する学力低下の論議における教育委員会の認識についてでございます。
新居浜市におきましては、国のGIGAスクール構想により、2020年11月に1人1台の端末を導入し、現在5年目となります。2010年から1人1台端末の導入を進めたスウェーデンと比べると、年数も短く、ようやく端末の利活用が進んできた段階だというふうに考えております。市が令和6年9月に行った小学生向けアンケートでは、端末を利用した学習は分かりやすいですかという質問に対し、80%以上の児童が分かりやすいと回答しており、端末の活用についても一定の効果があると認識をしております。
しかしながら、スウェーデンでは、2016年から2021年にかけて、児童の読解力が低下しておるという結果も出ておりますため、国内外の端末の活用状況と学力の関係性について注視し、長年培われてきた教育と最先端のICT、それぞれの特性を生かした効果的なベストミックスについて調査研究を進めてまいります。
○議長(小野辰夫) 藤原雅彦議員。
○20番(藤原雅彦)(登壇) では、次の質問、4番目に移ります。
電話リレーサービスについてお伺いいたします。
聴覚障害を持つ方々にとって、電話でのコミュニケーションは依然として大きな課題です。特に、緊急時の対応や日常生活における重要な連絡の場面では、電話の利用が制限されることで、十分な情報伝達が困難となり、安全や生活の質が損なわれる可能性があります。
こうした背景から、電話リレーサービスは、聴覚障害者の方々の社会参加を支える重要な基盤であると認識しております。
このことを受け、近年、総務省を中心に、聴覚障害者が電話を利用できる環境整備として、電話リレーサービスが全国的に導入されています。このサービスは、聴覚障害者が通訳オペレーターを介して、手話や文字チャットで通話できるものであり、日常生活だけではなく、緊急時の連絡手段としても非常に重要です。同サービスの実現に、公明党の山本博司参議院議員も当事者の方々の声を聞き、強力に推進し、2021年7月から24時間365日使える公共インフラとして整備され活用が進んでおります。ちなみに、令和5年9月末時点で、1万3,757人の方がサービス登録されております。電話リレーサービスによって、店や病院などの予約を聴覚障害者自身ができるようになり、警察や消防などへの緊急通報機能が使えるとともに、聴覚障害のある方などの社会参画の支援につながるものです。
このように、電話リレーサービスは、聴覚障害者が日常生活や緊急時に他者と円滑にコミュニケーションを取るための重要なツールであり、彼らの社会参加や生活の質の向上に直結しています。
新居浜市として、この課題に積極的に取り組むことが、全ての市民が平等に暮らしやすい社会の実現につながると信じております。
しかし、市内の聴覚障害者がこのサービスを十分に利用できる環境が整っているか、また電話リレーサービスに対する市民全体の理解が進んでいるかについては、課題が残っているのが現状ではないでしょうか。それについて以下の点についてお伺いいたします。
現在、新居浜市では、聴覚障害者の方に対する電話リレーサービスの周知や啓発活動をどのように行っているのか、お伺いいたします。
また、新居浜市のホームページや市政だよりなどの広報紙などを活用した情報発信を行ったことがあるのでしょうか、お伺いいたします。
電話リレーサービスの利用に当たり、専用アプリやデバイスの設定、使い方の指導が必要です。
新居浜市として、これらについて支援策を講じる取組が大事であると考えますが、御所見をお伺いいたします。
また、利用者負担軽減のための助成制度や利用者ニーズを反映した柔軟な支援体制の整備についての御所見をお伺いいたします。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。久枝福祉部長。
○福祉部長(久枝庄三)(登壇) 電話リレーサービスについてお答えいたします。
本市の聴覚障害のある方に対する電話リレーサービスの周知や啓発活動については、県から提供された啓発用のポスターやパンフレットを地域福祉課や障がい者福祉センターに設置し、周知啓発を行っておりますほか、新たに身体障害者手帳を取得された方にも御案内いたしております。
また、情報発信につきましては、市政だよりなどの広報紙には掲載しておりませんが、地域福祉課ホームページや障がい福祉のしおりに掲載し、広く周知に努めております。
本サービス利用に当たっての設定や使い方の指導につきましては、地域福祉課窓口において支援に取り組んでいるところでございます。
利用者負担軽減のための助成制度につきましては、利用者が負担する費用が通話料であり、御利用分の支払い方法が多様で、それぞれをどう確認するかなどの課題もあることから、直ちに事業化することは難しいと考えております。
また、利用者ニーズを反映した柔軟な支援体制の整備につきましては、今後も窓口等での丁寧な説明やきめ細やかな利用支援を行うとともに、聴覚障害者協会や難聴者協会とも連携して、市民全体の理解促進に努めてまいります。
○議長(小野辰夫) 藤原雅彦議員。
○20番(藤原雅彦)(登壇) 次、5番目に参ります。
電力スマートメーターフレイル検知事業についてお伺いいたします。
11月14日に人口減少対策特別委員会として、長野県松本市へ行政視察に参りました。視察内容に電力スマートメーターを活用したフレイル検知事業がありました。現在、この電力スマートメーターを活用した様々な取組が全国的に行われているようです。その中で松本市がフレイル検知に特化した事業を行っていました。電力スマートメーターフレイル検知事業とは、電力会社や関連事業者が、電力スマートメーターを活用して、高齢者や要介護者などの生活状況を把握し、異常を検知する取組のことです。この事業は、高齢化が進む社会において、高齢者が安全に生活できる環境を支援するための重要な技術とされております。電力スマートメーターは、電力の使用状況をリアルタイムで計測、送信する装置です。これにより、家庭での電力使用パターンが把握できます。電力使用パターンのデータを分析することで、例えば朝起きてからの電力使用がない、夜間に電力使用が増えているなど、通常と異なる生活リズムを検知できます。異常が検知された場合、事前に設定された家族や地域の福祉担当者に通知が送られ、速やかな対応が可能になります。メリットとしては、先ほど申したように、高齢者が倒れて動けなくなった場合など、早期発見が可能になります。また、電力スマートメーターで常時見守るため、見守り隊の人員などを削減できるとされております。電力スマートメーターでの監視は、カメラやセンサーによる監視と比べ、電力データはプライバシーへの影響が少ないとされております。また、災害時に活用することもできるようです。電力スマートメーターは、災害時に停電エリアの把握や孤立世帯の検知にも有用と言われております。例えば、地震や台風などでライフラインが途絶した場合に、電力データを活用すれば、復旧作業の優先順位を効率的に決定できるだけではなく、孤立の危険性が高い住民への迅速な支援が可能となります。
しかしながら、新たな取組や技術を導入する際には、コストと財政的影響を慎重に考慮する必要があります。フレイル検知事業の導入は、初期投資や運用コストがかかる一方で、災害対応の効率化や高齢者の見守り強化など、社会的な費用対効果も期待されております。現在、自治体や電力会社が連携して、高齢者世帯への電力スマートメーター設置を進めている地域もあるそうです。松本市もその一つでした。また、データ分析技術を持つIT企業やベンチャー企業が、異常検知アルゴリズムを提供するケースも増えているようです。
以上の観点から、新居浜市において、この電力スマートメーターを活用した検知事業の導入の検討をすべきと考えます。この事業は、高齢者支援、防災対策、地域の安全強化という多方面にわたる課題解決につながる可能性を秘めています。現在、新居浜市で、電力スマートメーターが設置されているのでしょうか。もし設置されているとすれば、何台でしょうか、お伺いいたします。
それらの電力スマートメーターから収集されたデータは、どのように活用されているのでしょうか。管理は四国電力となりますので、分かる範囲で構いません。
今後市民の生活の質を向上させるためにも、電力スマートメーターの活用を積極的に検討していただきたいと考えますが、御所見をお伺いいたします。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。久枝福祉部長。
○福祉部長(久枝庄三)(登壇) 電力スマートメーターフレイル検知事業についてお答えいたします。
本市における電力スマートメーターの設置状況について、四国電力送配電株式会社に確認いたしましたところ、正確な設置台数は確認できませんでしたが、昨年度末時点において、電気契約をしているほぼ全てのお客様に電力スマートメーターの設置を完了しているとのことでございました。
収集されましたデータが、どのように活用されているかについては、電気使用量の確認や停電、電気の開始、廃止など、送電に関する確認操作に活用しているとのことですが、高齢者や要介護者などの生活状況の把握や異常を検知する取組については活用されていないとのことでございました。
現在、本市では、高齢者が安心して生活できるために、独居高齢者見守り推進事業や健康長寿地域拠点づくり事業など様々な事業に取り組んでおりますが、松本市の取り組んでいる電力スマートメーターフレイル検知事業につきましても、フレイル予防などにつながる有効な方法の一つであると考えられますことから、今後電力スマートメーターの活用など先進的な取組についても調査研究してまいります。
○議長(小野辰夫) 再質問はありませんか。藤原雅彦議員。
○20番(藤原雅彦)(登壇) ぜひとも調査研究よろしくお願いいたします。
最後ですが、改めて古川市長は就任に際して、多くの期待と責任を背負われております。新居浜市の発展や市民生活の向上を目指すに当たり、リーダーとしての信念や覚悟、そして具体的な行動計画を示すことが求められております。ぜひ古川市長の力強いリーダーシップの下で、市民が安心して暮らせる、そして未来に希望を持てる新居浜市を実現していただきたいことを心からお願いを申し上げます。大変ありがとうございました。質問を終わります。
○議長(小野辰夫) この際、暫時休憩いたします。
午後 1時59分休憩
―――――――――― ◇ ――――――――――
午後 2時10分再開
○議長(小野辰夫) 休憩前に引き続き会議を開きます。
伊藤義男議員。
○2番(伊藤義男)(登壇) 本日最後の一般質問をさせていただきます自参改革クラブ、参政党の伊藤義男です。
古川市長、このたびは御当選誠におめでとうございます。これから4年間、新居浜市の発展と市民の安全、安心なまちづくりをしていただくことを強くお願いし、私は議員の立場として、是々非々で市長と共に歩んでいく所存です。
それでは、通告に従いまして質問させていただきます。
初めに、市長の政治姿勢について質問させていただきます。
外国人労働者についてです。
先般の市長選挙前に公開討論が行われました。そのときに、古川市長から、人口減少の問題で、労働人口をどう補うのか、今生まれてくる子供たちは、これから戦力になるまでに20年かかります。じゃあ一旦は外の力を借りよう、外国人の労働者を借りよう。じゃあ外国人が来てくれる町はどうなのかというところで発言時間が来たために区切られてしまい、市長の考えを聞くことができませんでした。現在、我が国においては、移民政策と思われるような政策がどんどん打ち出されています。まず、移民の定義は、国際的に正式な法定定義はありませんが、多くの専門家は、移住の理由や法的地位に関係なく、定住国を変更した人々を国際移民とみなすことに同意しています。しかし、日本政府は、移民政策だと認めることをしません。過度な移民政策を行うと、どのようなことが起こるのか、国内外の事例を紹介いたします。
アメリカでは、移民の増加の影響で、労働賃金が低下する傾向があることが報告されています。移民労働力の1%増加が、アメリカ人労働者の賃金を0.3%から0.4%低下させるという研究結果も出ています。実際、アメリカでは、1980年から2000年までの間に、移民の労働力が11%増加し、その影響でアメリカ人労働者の平均賃金は3.2%低下したとも言われています。
また、ドイツでは、2015年の難民危機で多くの中東難民が流入し、公共スペースの利用や宗教行事に関する誤解が原因で文化的摩擦が発生しました。
スウェーデンでは、移民集中地域で、生活習慣の違いが衝突を引き起こしており、ストックホルム郊外で文化的摩擦が表面化しています。
イタリアでは、北アフリカからの移民増加が治安悪化を招き、移民コミュニティーと現地住民の間で摩擦が生じているなど、移民の受入れは国外でも様々な影響を及ぼしています。
国内に関しては、埼玉県川口市において、2023年7月、病院に100人近くの外国人が集結する騒動が発生しました。
また、外国人のコミュニティーが拡大し、ごみ出しのルールや生活習慣などの違いにより、住民との摩擦も起きています。
さらに、特定技能2号の制度が昨年4月に改正されて、特定技能2号の対象分野が大幅に拡大されました。これにより、従来の建設と造船・舶用工業に加えて、ビルクリーニング、工業製品製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業など多くの職業を選択することが可能となり、在留期間は無期限で、家族帯同も可能になりました。また、特定技能2号の対象分野が拡大されたことで、外国人労働者はより多くの業種で再就職の機会を得ることができるようになりました。
以上のことから、今後国内において、外国人が増えてくることは間違いありません。
そこで、先ほどもお伝えした海外の事例や国内の事例のようなことが本市でも起こる可能性を考えなければいけません。
そこで、市長に5点質問いたします。
1点目、公開討論で言いかけになった外国人が来てくれる町はどうなのかの続きをお聞かせください。
また、外国人が来てくれる町とは、どういう町なのかを詳しく御説明ください。
2点目、今から生まれる子供が戦力になるまで20年の間は、一旦外国人の力を借りようとのことですが、20年の間で何人の市内外国人労働者が増えれば、新居浜市の人材不足は解決するのか、その人数の算出方法も併せてお答えください。
3点目、今生まれる子供もいれば、来年から就職する子供もいます。そういった就職活動をしている子供たちや学生の就職支援はどのように考えられているのか。
あわせて、日本人より外国人が優先されて職に就けるということがないように、どのような対策を考えられるのか、お答えください。
4点目、一旦は外国人の力を借りようとのことですが、私たちの世代が経験した超就職氷河期が再来した場合、外国人労働者はどのように扱うつもりなのか。自国へ帰ってくださいと言って帰国を促すのか、日本人の働く場所がなくなるのは本末転倒です。市長のお考えをお聞かせください。
5点目、都市部では、外国人が増えて、地域住民とトラブルになる事例が多発していますが、本市において、外国人と地域住民がトラブルにならないようにどのような取組をすべきだと考えられているのか、お答えください。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) 伊藤義男議員さんの御質問にお答えいたします。
私の政治姿勢についてでございます。
外国人労働者についてお答えいたします。
外国人が来てくれる町につきましては、愛媛労働局が公表した資料によると、本市には技能実習や専門的・技術的分野の在留資格者など1,400名近くの外国人労働者が生活されています。私は、新しい新居浜の実現に向けた基本姿勢として、笑顔あふれる人に優しいまちづくりを掲げていますが、これは国籍にかかわらず、本市で暮らすあらゆる方々にとって、優しさがあふれ、たくさんのぬくもりを感じることができる新居浜市を目指すものであります。母国を離れ、不慣れな土地で暮らす外国人労働者が抱える生活習慣への戸惑いや混乱を少しでも軽減できる環境づくりを図り、新居浜で働けてよかった、また新居浜で働きたいと思っていただける町でありたいと考えておりますし、そうした町であることは、私が目指す人に優しいまちづくりの実現につながるものであると考えております。
○議長(小野辰夫) 長井市民環境部長。
○市民環境部長(長井秀旗)(登壇) 外国人と地域住民がトラブルにならないための取組についてでございます。
異なる文化を持つ外国人を受け入れ、地域住民とのトラブルを防ぐためには、転入された外国人、受け入れる側の地域住民の双方がお互いの文化的違いを認め合い、理解する姿勢を持つことが重要であると考えております。
そのための取組といたしまして、新たに転入された外国人にごみの出し方や交通マナーなどを解説した外国人のためのガイドブックを配布し、また地域からの要望に応じて、外国語でごみの出し方についての講習会を開催するなど、地域で生活する上で必要なルールの理解促進に取り組んでおります。
また、受け入れる側の地域住民に対しましては、国際交流協会が実施しております異文化理解講座や各種イベント、外国から招聘している国際交流員の活動などを通して、市民の国際化意識の啓発に努めているところでございます。
今後におきましても、新居浜市国際化基本指針の基本理念である誰もが住みたい住み続けたい多文化共生のまちにいはまの実現に向けて取り組んでまいります。
○議長(小野辰夫) 宮崎経済部長。
○経済部長(宮崎司)(登壇) 20年の間で、何人の外国人労働者が増えれば、新居浜市の人材不足は解決するのかについてお答えいたします。
20年後に何人の外国人労働者が必要かということにつきましては、社会・経済状況の変化に大きく影響されるものであり、その予測は非常に困難でございます。
しかしながら、JICA、国際協力機構が公表しております2030/40年の外国人との共生社会の実現に向けた調査研究外国人労働者需給予測更新版によりますと、2040年におきまして、国が目標とするGDP、国内総生産を達成するための労働力人口とベースラインの労働力人口の差から計算される外国人労働需要量は688万人になると予測されております。
また、同資料によりますと、2040年の愛媛県の外国人労働需要量の対生産年齢人口比率は、国立社会保障・人口問題研究所の日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)において予測されております生産年齢人口の6.0%から8.0%とされており、その推計を基にいたしますと、本市の外国人労働需要量は、3,000人から4,000人程度になると予測されます。
次に、就職活動をしている子供たちや学生の就職支援についてでございます。
本市の就職支援といたしましては、高校生や大学生等と企業との出会いの場の創出のための合同企業説明会を開催するとともに、市内の小中学生や産業技術専門校生に対して企業見学を実施するなど、職業観の醸成に取り組んでいるところでございます。
また、日本人より外国人が優先されて職に就けることがないようにどのような対策を考えているのかにつきましては、その時々の社会情勢や企業の採用計画に基づき、それぞれの企業が適切に判断し、採用活動を実施していかれるものと認識いたしております。
次に、就職氷河期が再来した場合、外国人労働者をどのように扱うつもりなのかについてでございます。
就職氷河期のような厳しい経済状況下におきましては、まずは国による雇用維持支援や職業訓練、生活支援の強化を図っていくことが重要になるものと考えております。その中で、外国人労働者の方が身につけた技能や経験を生かし、多様性を尊重しながら、地域経済の回復と発展に貢献できるよう、日本人、外国人の別なく、全ての労働者が共に活躍できる環境づくりを推進していくことが重要だと考えております。
○議長(小野辰夫) 伊藤義男議員。
○2番(伊藤義男)(登壇) 市長の言葉だったので、市長のほうから考えをお聞きしたかったんですけども、国の政策なので、外国人労働者の受入れを止めることは難しいです。市民や理事者が問題点を認識して、共有できていれば、未然に問題も解決できると思います。
そこで、外国人労働者の増加により、地域の労働市場や賃金水準にどのような影響が生じるのか、具体的な経済モデルやシミュレーション結果を公表すること、外国人受入れに伴う地域社会の摩擦を解消するために、外国人の地域コミュニティー参加や自治会加入の促進、外国人労働者の日本語教育やその家族の教育環境整備、日本人労働者が不利益を被らないようにするための具体的な対策、外国人受入れに関する住民理解を得るために、市民説明会を開催すること、これらを要望しまして、次の質問に移ります。
次に、外国人の人口についてです。
現在、新居浜市のホームページトップ画面には、総人口や世帯数、男女比が掲載され、定期的に更新されていますが、外国人住民の人口に関する情報は含まれておりません。市長が外国人労働者を増やすと言われている中、市民の間では、外国人住民の増加に伴う治安や生活環境の変化などについて懸念の声も聞かれます。
このような状況において、外国人住民の現状を市民が正しく理解できる情報を提供することは、市民の不安を解消するために有効だと考えます。
そこで、お伺いします。
ホームページトップ画面にて、外国人の人口を掲載し、更新していくべきだと思いますが、市長の考えをお聞かせください。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。加地企画部長。
○企画部長(加地和弘)(登壇) 外国人の人口についてお答えいたします。
外国人の人口につきましては、現在、本市ホームページの地域コミュニティ課ページにおいて、月末時点の国籍別人員数を掲載いたしております。
しかしながら、当該ページは、トップページからの階層が深いため、検索しづらい状況となっております。
このことから、より分かりやすい形での情報提供となりますよう、トップページの人口掲載欄から直接リンクされております統計情報ページにおいて外国人人口を掲載するとともに、統計情報ページから国籍別人員数の掲載ページへリンクできるよう対応いたします。
○議長(小野辰夫) 伊藤義男議員。
○2番(伊藤義男)(登壇) このことによって、市民が現状を正しく理解し、行政と市民が連携して課題解決に向けた取組を進めることができますので、速やかに掲載していただくことを要望しまして、次の質問に移ります。
次に、ワクチン接種健康被害についてです。
現在、新居浜市では、健康被害に関する進達16件、認定13件、否認1件が確認されており、愛媛県全体では、進達114件、認定71件、否認23件、さらに死亡認定15件という状況です。市長が、県議時代にワクチン接種を推奨していたかどうかに触れるつもりはありませんが、現状として多くの方が健康被害で苦しんでいる事実を踏まえ、被害者への支援が重要だと考えます。
現在の健康被害救済制度では、被害認定後に一時金や医療手当の支給が行われるのみで、その後の継続的なサポートが不足しています。
そこで、市長にお伺いします。
新型コロナワクチンによる健康被害について、どのようにお考えでしょうか。
また、市独自のサポート策としてどのような具体案を検討されているか、お答えください。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) ワクチン接種健康被害についてお答えいたします。
新型コロナワクチンは、有効性や安全性が確認された上で薬事承認されてはおりますが、ワクチン接種による健康被害に苦しんでおられる方がいることも認識いたしております。
本市といたしましては、ワクチン接種の効果や副反応、健康被害救済制度について十分御理解いただいた上で接種を受けていただくことが肝要であると考えており、ホームページへの掲載や委託医療機関でのポスター掲示等により周知に努めているところでございます。
市独自のサポートにつきましては、新型コロナウイルス感染症の予防接種による健康被害は、国の予防接種健康被害救済制度が利用できますことから、市独自の救済制度等は考えておりませんが、被害者の方に寄り添った丁寧な健康相談を行うとともに、予防接種健康被害救済制度の十分な説明と申請に係るサポートを行ってまいります。
○議長(小野辰夫) 伊藤義男議員。
○2番(伊藤義男)(登壇) 泉大津市では、新型コロナワクチン接種後に副反応などで健康被害を生じ、国の予防接種後健康被害救済制度の申請をされる方を対象に、申請までにかかった医療費などの費用の一部を市独自の支援金として支給したり、市独自のサービスを行っています。新居浜市においても、市独自のサポートをいち早く行っていただくことを要望し、次の質問に移ります。
次に、鳥獣被害についてお聞きします。
健康政策から考える鳥獣被害についてです。
現在、新居浜市において、鳥獣被害が拡大しています。主に、阿島、船木、角野、中萩、大生院の山側で被害が相次いでおり、多くの市民が家庭菜園、農作物被害やふんに悩まされています。その中でも、猿、イノシシ、ハクビシンなどの被害により、家庭菜園を諦める家庭が増えています。
大分県立看護科学大学のホームページには、なぜ姫島村は健康寿命が長いのかという記事があります。大分県北部の姫島の住民は、健康寿命が長く、その理由を調査した結果、家庭菜園と健康寿命に関連があることが示されています。姫島では、畑仕事を月1回以上実施している人の割合が、全国平均の2倍以上で、高齢者の歩行能力が優れ、1日の歩数が多く、体を動かす活動時間が長く、ストレスが少ないことが報告されています。この調査により、姫島の長い健康寿命には、家庭菜園での畑仕事が関与している可能性が示唆されています。
また、早稲田大学の堀口健治名誉教授と弦間正彦教授の調査によると、自営農業者の医療費は、それ以外の人に比べて約3割少ないことが明らかになっており、農業と健康寿命の延伸には関係があると報告されています。
しかし、新居浜市の山際の地域では、鳥獣害により多くの市民が家庭菜園や農業を諦めています。新居浜市の長期総合計画では、健康づくりと医療体制の充実を目指し、健康寿命の目標値を設定していますが、目標を達成するためには、家庭菜園と健康寿命の関係を考慮する必要があります。
そこで、お伺いします。
健康寿命延伸と家庭菜園の関係を市はどのようにお考えなのか、あわせて、現在、新居浜市では、有害鳥獣被害防止対策事業費補助金を出していますが、上限額が低いため、負担軽減にならない、申請に申請書と口座振替依頼書と誓約書兼調査同意書に必要事項を記入し、購入する資材の見積書を添えて農林水産課窓口まで提出することになっているが、手間がかかるから面倒だ、手続をしているうちに被害が拡大してしまうなどの意見を市民の方からいただいています。上限額の引上げと申請の簡略化ができないか、お答えください。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。宮崎経済部長。
○経済部長(宮崎司)(登壇) 鳥獣被害についてお答えいたします。
健康政策から考える鳥獣被害についてでございます。
まず、健康寿命延伸と家庭菜園の関係につきましては、農作業を通じて、日々体を動かすことは、ストレス解消や生きがいづくりが図られ、健康づくりに寄与しているものと考えております。
また、本市におきましては、自然農園での野菜づくりを推奨し、令和6年12月1日現在で223人の方が土と触れ合い、汗を流し、収穫する喜びとともに人との交流を深めており、この活動も健康づくりにつながるものと考えております。
次に、有害鳥獣被害防止対策事業費補助金の上限額引上げにつきましては、現在、補助金の上限額は、消費税抜きで、認定農業者の方は5万円、一般農家の方は3万円といたしております。令和6年11月末現在の実績で、43件の申請がございますが、消費税抜きの総事業費に対する補助割合は、平均で約42%となっており、補助金の上限額に達していない状況でございます。
このようなことから、現状を維持しながら、今後も多くの方に利用していただけるよう、周知啓発に努めてまいります。
また、申請の簡略化につきましては、申請場所の確認や被害の状況を踏まえた効果的な複合柵などの設置のため、面談による指導、助言も必要となってまいりますので、現状の申請方法を踏襲することがやむを得ないものと考えております。
○議長(小野辰夫) 伊藤義男議員。
○2番(伊藤義男)(登壇) 鳥獣害対策の予算は、昨年、令和5年度も余っていました。これだけ市内全域において鳥獣被害が拡大しているのに、予算が余るのはおかしいです。鳥獣害の撲滅に向けて、市民が使いやすいサービスの提供を要望し、次に移ります。
次に、猿被害対策についてです。
9月30日に角野公民館で開催した猿の特性を学ぶ出前講座の案内のため、角野地区で猿被害があると思われる地域の500軒を個別で案内に行き、一軒一軒声を聞いてきました。その聞き取りで分かったことをお伝えします。
まず、里山整備が問題となっています。昔は、みんなが季節ごとに里山へ出かけて、山菜採りをしていたと伺ったおうちで聞きました。そうやって人間がいることで、居住地域より山側に人間と猿との境界線が自然にできていたのだと思います。
次に、耕作放棄地が増えています。これは高齢化というより、猿被害で果樹園などが廃業した事例が多いです。家庭菜園なども猿の被害が多いので耕作をやめていました。猿被害で耕作放棄地が増え、その耕作放棄地に猿が生息して、広範囲に広がっていくという負の連鎖がありました。
空き家問題も大きな問題です。空き家にすみ着く猿が増えています。私も訪問して話をしている最中に、空き家から出てきた猿と遭遇しました。おうちの方が、あなたの話をしよるんぞねと猿に話しかけていました。高齢化が原因で空き家が増え、高齢化が進むと、猿を追い払う元気が住民になくなってきます。実際、若い人が講座を受けに行って追い払いをしてくれないだろうかと言われる高齢の方がいらっしゃいました。猿は、空き家を拠点にして生息範囲を広げていきます。そして、猿が生息地を広げて、住宅街の空き家にすみ着いた場合は、追い払いが難しくなります。煙火を用いた追い払いは、住宅街では火災や騒音問題の原因になるため使用できない場合があります。今、煙火で追い払いをやっている地域が、最終防衛ラインであり、これを突破されると取り返しがつかなくなる可能性もあります。これは、猿被害を受けている人だけの問題ではなく、地域全体の問題であり、いろんな社会問題が原因だということに気づくことができました。
以上、実際に市民の方から話を聞いてきた事実です。
実際に、私が住む角野校区は、猿の被害が深刻になっています。私の家の目の前まで猿が出没し、学校のグラウンドや校庭にも猿が現れています。猿が人前に出てきて、それが常態化すると、室内に猿が侵入する事態に発展するとも言われています。授業中に猿が校舎に入ってきたり、給食の時間に猿が子供の給食を奪うといったことも考えられます。そういった事態にならないように、現在、角野では、住民たちが結束して、何とか追い払いをしようと呼びかけています。煙火を用いた追い払いのほか、資料1を御覧ください。これは、PTAや地域住民で猿が隠れたりする場所をなくすために、校庭の木を剪定したり、餌になる実がなる木を剪定したときの写真です。住民が一体となって、この鳥獣害に立ち向かっています。
しかしながら、住民たちの力も限界があります。やはり、行政の補助がなければ、正直しんどいです。
そこで、5点お伺いします。
1点目、現在、鳥獣害対策の係が定期的な猿の出前講座や煙火の講習、配布を角野公民館で開催してくれていますが、これを市全体の鳥獣害がある地域の公民館で毎月定期的に開催できないか、追い払いは続けることに意味がありますが、煙火がなくなった場合、市役所へ取りに行くのが面倒だという理由で追い払いをやめてしまうケースがあります。そのことも踏まえて、開催の有無をお答えください。
2点目、現在、本市においては、追い払いをメインでやっていますが、追い払いは地域住民の継続的な活動が必要になってきます。やはり、追い上げをやらなければ、住民負担が大きいです。しかし、追い上げのためには、専門的な知識や情報収集が必要になります。市として専門家を入れて追い上げを本格的にやっていただけないか、お答えください。
3点目、猿は煙火のような大きな音で一時的に退散します。しかし、またすぐに群れで出現します。福井県では、モンキーバスターズという組織が結成され、JA福井県女性部の女性有志3名が、電動エアガンで追い払いに成功したという事例があります。やはり、猿にも痛い思いをさせないといけないのかもしれません。
そこで、本市として、猿の追い払いを目的とする電動エアガンの購入に補助金を出せないか、お伺いします。現在の電動エアガンは、威力も制限されて、免許なしで使用でき、安全装置もついている安心できる物となっており、一番安い商品で2万円ほどになります。猿に当たっても猿を傷つけることなく、痛いと思わせることができ、弾も土に戻るものが販売されています。煙火を用いた追い払いにも限界を感じている部分もあるので、補助できないかお伺いします。
4点目、新潟県阿賀町では、猿被害対策として、猿の群れの個体にGPS装置を装着し、リアルタイムで猿の群れの位置情報が分かるアニマルマップを活用しています。これを導入することで、地域住民が事前に猿の出没を把握し、追い払いを行うことで、効率的な追い払いができるとのことです。
新居浜市としても、このシステムを導入し、農家や住民の被害対策に活用できないか、お答えください。
5点目、先ほど御説明したモンキーバスターズですが、福井県に確認すると、高齢化が原因で令和3年に解散したとのことです。その後どうなったか聞いたところ、以前と同じように、猿がまちなかに出没するようになったとのことでした。現在、猿の捕獲に向けた最新の捕獲器である地獄おりを導入しているところがあります。最終的には、捕獲をしていかないと難しい現状を踏まえて、市としても最新の捕獲器である地獄おりを導入できないか、お伺いします。
以上、5点お答えください。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。宮崎経済部長。
○経済部長(宮崎司)(登壇) 猿被害対策についてお答えいたします。
まず、出前講座や煙火講習の定期的な開催についてでございます。
ニホンザルの習性や行動から学ぶ被害対策の理解を市民の方に知っていただくため、市では出前講座を申込みに応じて随時開催しており、令和6年度は角野校区のほか、船木・中萩校区の自治会などの申込みにより、計5回開催いたしております。
また、煙火講習も希望者の御都合に合わせて随時行っており、講習を終えた方は、市役所にお越しいただいて煙火を配布いたしております。
御提案の講座や講習の定期的な開催につきましては、申込件数を考慮いたしますと、現状では要望に応じた開催を継続してまいりたいと考えております。
また、煙火の配布につきましても、煙火自体の取扱いや本人確認など、慎重にすべきものと考えておりますことから、市民の方には御足労をおかけいたしますが、引き続き市役所にお越しいただきたいと考えております。
次に、追い上げについてでございます。
追い上げとは、ニホンザルの群れを威嚇などの手段を用いて農地や住宅地から隔たった目標の地域へ積極的に追い立てるもので、追い払いより一歩踏み込んだ対策と伺っております。
追い上げに際しては、地形、植生、気象条件、農地、住宅地の防護などの環境整備や追い上げへの地域住民の参加協力などクリアすべき条件も多く、5年以上の長期的な計画が必要となるなど、専門家を交えて組織的な体制づくりが必要であると伺っており、地域主体の取組が前提となってまいります。そのため、地域ぐるみで取組を進めたいとの地域からの申出がございました場合には、相談内容に応じて、県を通じて専門家を派遣してもらうなど実施に向けて協力してまいりたいと考えております。
次に、電動エアガン購入補助金についてでございます。
現在のところ、煙火を中心とした追い払いを推進いたしておりますので、現状の対策を引き続き活用しながら、地域全体で追い払いが進むよう努めてまいりたいと考えております。
次に、アニマルマップシステムの導入についてでございます。
アニマルマップシステムは、ニホンザルの位置情報を事前に把握できますことから、効果的な対策が可能となりますが、費用が多額になりますことから、現在のところ導入は困難であると考えております。
次に、最新捕獲器の導入についてでございます。
大型囲いわなである地獄おりの導入につきましては、現在、本市では設置いたしておりませんが、四国中央市において設置事例があり、視察にも伺っております。地獄おりは、一般的に一度に大量のニホンザルの捕獲も可能と言われておりますが、餌づけに期間を要すること、新鮮な餌の継続的な補給や見守りなど、その管理に多大な労力や費用負担も生じるため、駆除の協力を依頼している猟友会はもとより、市が直接的に購入、管理することは、現状では難しいものと考えております。
今後におきましても、愛媛県や他市との連携、情報共有を図りながら、効果的なニホンザル被害対策について調査研究してまいります。
○議長(小野辰夫) 伊藤義男議員。
○2番(伊藤義男)(登壇) 先日も公民館で作業中に煙火が鳴り響き、現地に行ってみると、住民の方が干し柿を全部猿に食べられたとお怒りになられていました。角野小学校は、ほぼ毎日のように猿が校庭まで来ています。これが続けば、猿が校舎内へ入って、子供たちに実害も出ると思います。角野小学校だけではありません。他の小学校の通学路にも、猿が出没するエリアがあります。子供たちの安全と地域の方の安心のためにも、先ほど質問しました各公民館での講座と講習の定期開催、追い上げの実施、電動エアガン購入の補助、GPS装置による群れの確認と共有、地獄おりの導入、以上、5点を要望し、次の質問に移ります。
次に、災害時の遺体収容についてお聞きします。
災害時には、被害を最小限に抑えるように計画することは、市として当然の責務でありますが、多数の犠牲者が出る可能性も同時に考えなければなりません。適切な遺体収容所の確保は、市民の尊厳を守り、混乱を防ぐためにも重要と考えます。
しかしながら、現在本市では、災害時の遺体収容所の具体的な指定がなされていないと伺っています。
そこで、お伺いします。
災害時の遺体収容所は、平時の今、決めることはしないのか、お答えください。
あわせて、遺体収容所として想定される施設はどこなのかもお答えください。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。小澤市民環境部危機管理監。
○市民環境部危機管理監(小澤昇)(登壇) 災害時の遺体収容についてお答えをいたします。
災害時の遺体収容所につきましては、新居浜市地域防災計画では、市内の寺院、公共施設等死体受入れに適当な場所を選定して死体安置所を開設することとなっております。
現在のところ、候補地の選定には至っておりませんが、事前に選定しておく必要があるものと認識いたしております。
なお、市で選定する候補地のほか、令和5年に市内葬祭業者4社と災害時における葬祭業務に関する協定を締結し、遺体を安置するための施設を提供していただけることとなっております。
今後におきましては、事前の候補地選定に向け、関係機関等と協議、調査を進めてまいります。
○議長(小野辰夫) 伊藤義男議員。
○2番(伊藤義男)(登壇) 遺体収容所が決まっていない場合、災害発生時に適切な対応が難しくなるおそれがあります。災害は予測が困難であることから、発生時には迅速な対応が求められますので、今のうちに収容施設の確定をしていただくことを要望し、次の質問に移ります。
次に、太陽フレアについてお聞きします。
太陽フレアとは、太陽の表面に見える黒点周辺で起こる大規模な爆発を指します。今年から来年にかけて、太陽が活動を活発化させる極大期に入り、今後一年は太陽フレアが頻発し、通信障害や大停電が起きる可能性があると総務省から宇宙天気予報の高度化の在り方に関する検討会の報告書や宇宙天気の警報基準に関するWG報告:最悪シナリオという題名で報告書も出されています。
しかしながら、ほとんどの市民がこのことを知らないのが現実です。実際に、通信障害や大停電が起きた場合、情報を得る手段がほとんどなくなり、市内が大パニックに陥る可能性もあります。
そこで、お伺いします。
最悪の事態になった場合、市民が冷静に行動できるように事前の周知が必要だと思います。市政だよりやホームページを通じて、市民に周知することはできないでしょうか、お答えください。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。小澤市民環境部危機管理監。
○市民環境部危機管理監(小澤昇)(登壇) 太陽フレアについてお答えいたします。
伊藤議員さん御案内のとおり、太陽フレアとは、太陽表面で発生する巨大な爆発現象のことであり、大規模なフレアが発生した場合には、停電や通信障害、人工衛星を利用したGPSの精度低下などの影響が懸念されております。
本市といたしましては、まず国において令和4年に開催された宇宙天気予報の高度化の在り方に関する検討会の報告書等を確認し、太陽フレアに関する被害想定や対策に関する情報収集に努めてまいります。
また、今後におきましては、国の対策や動向を注視しながら、大規模な太陽フレアが発生し、市民生活に影響を及ぼすと想定される場合には、市ホームページなどを通じて、国からの情報を迅速に市民の皆さんへ提供してまいります。
○議長(小野辰夫) 伊藤義男議員。
○2番(伊藤義男)(登壇) この太陽フレアの障害に関しては、来年の話でもありますので、早めの周知徹底をお願いしたいと思っております。それを要望して、次に移ります。
次に、障がい者福祉についてお聞きします。
障がい者の意思疎通についてです。
先日、全国特別支援学校知的障害教育校PTA連合会の全国役員・都道府県代表者連絡協議会に参加してきました。その際、日本マカトン協会代表の方が講師として来られ、マカトン法セミナーと題して講話がありました。マカトン法とは、言葉やコミュニケーションに困難のある人のためにイギリスで開発された方法で、話し言葉に加え、手指のサインやシンボルを組み合わせて使用します。330の核語彙から個人のニーズに合わせた語彙を選び、生活の中で繰り返し活用することで、言語概念の形成やコミュニケーションの促進を図り、マカトンサインは簡単で覚えやすく、話し言葉よりも獲得が容易です。例えば、家族でサインやシンボルを決めて意思表示をしていても、家庭を出ると共通したものがないため、自分の意思を伝えることができなくなります。そこで、当事者は、ストレスを抱え、問題行動を起こしてしまうなど、意思表示ができないことで様々な弊害が生まれます。そういった弊害をなくすためにも、共通の意思表示ツールが必要ではないでしょうか。
また、障害者による情報の取得利用、意思疎通に関わる施策を総合的に推進し、共生社会の実現に資するという目的で、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法が令和4年5月に施行されています。
そこで、お聞きいたします。
現在、国内においては、マカトン法のような共通のシンボルやサインといった共通のツールがありません。
新居浜市内で共通するものがあれば、障害者がもっと社会に出て生活できるため、共生社会の実現になると思います。そのためには、まず市民に対しマカトン法の周知が必要だと思います。マカトン法の周知を含め、新居浜市で先進的に導入できないか、お答えください。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。久枝福祉部長。
○福祉部長(久枝庄三)(登壇) 障がい者福祉についてお答えいたします。
障がい者の意思疎通についてでございます。
御案内のマカトン法は、絵が描かれたカードやサインなどを使った視覚による支援の手法の一つと理解しております。視覚による支援を利用することによって、文字を読むことや言葉で表現することに困難がある方、今後の見通しを持つことが苦手で、先の予定が分からないことに強い不安を持つ方などにとって理解しやすく、伝えたいことを発信し、相手に伝わるという経験を重ねることで、さらにコミュニケーションの幅を広げることにつながります。学校や療育施設では、それぞれの方の特性や障害の程度に応じて、絵や写真、サインなどいろいろな手法を用いたコミュニケーション支援が行われており、一つの手段にこだわるのではなく、複数の方法を場面に合わせて使い分けることも有効と考えております。
今後におきましては、新居浜市障がい者自立支援協議会の専門部会や理解促進・啓発事業などにおいて、マカトン法などのコミュニケーション支援について紹介し、市民や関係者の理解を求める機会を設けてまいります。
○議長(小野辰夫) 伊藤義男議員。
○2番(伊藤義男)(登壇) 皆さんもそうですが、自分の意思を伝えるということは大切です。意思を伝えることで、健全なコミュニケーションが生まれ、良好な人間関係が構築されます。発語に障害がある方などの意思表示のためにも、共通の言語ツールを導入していただくことを要望し、次の質問に移ります。
次に、外見からは分かりにくい障がい者への理解促進についてです。
現在、市内においても、身体障害以外の障害者人口は増え続けています。それに伴い、外見からは分かりにくい障害を持つ方も増えています。そういった方は、自立して活動することが可能で、まちなかを歩いていても障害があることは分かりません。しかし、そのような方たちの中には、物事の理解や行動に時間がかかったり、障害者特有の行動が見られたりして、周囲からの偏見を受けることもあります。しかし、そのようなことは、あまり市民に対して周知啓発ができていないのが現状ではないでしょうか。
資料2、3を御覧ください。
これは、宮城県立古川支援学校のPTAが作成し、外見からは分かりにくい障害を持つ子供の理解促進のために街頭で配布しているものです。この学校では、ハートバッチというものを作り、資料2には、外見からは分からない障害者への理解を求めるために、障害からくる様々な行動を説明する内容や、資料3には、我が子に障害があることを周囲の人に理解してもらい、温かく見守ってほしいという願いでバッジを作製したことなどが書かれています。保護者としては、外見で分からないために理解できていない人から心ない言葉をかけられて傷ついたり、親亡き後にだまされたりしないか、職場での理解は大丈夫なのかなど、様々な不安を抱えています。障害者の自立と共生社会の実現の上でも、これらの情報の周知や啓発は非常に重要です。
また、国が示している障害者計画においても、知的障害、精神障害、発達障害、難病、高次脳機能障害、盲聾、重症心身障害、その他重複障害など、より一層の国民の理解が必要な障害や外見からは分かりにくい障害について、その障害特性や必要な配慮などに関する理解の促進を図ることとされています。
このことから、新居浜市においても、この部分の啓発を進める必要があります。
そこで、お伺いします。
新居浜市の市政だよりやホームページ、その他学校の配布物や職場に対して、資料にあるような理解を促す内容の周知啓発を行っていただけないでしょうか、お答えください。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。久枝福祉部長。
○福祉部長(久枝庄三)(登壇) 外見からは分かりにくい障がい者への理解促進についてお答えいたします。
本市では、知的障害、精神障害、発達障害や内部障害などの障害により、外見からは分かりにくくても、周囲の配慮が必要となる方に対し、思いやりのある行動をお願いするヘルプマークやヘルプカードの普及に取り組んでいるところでございます。
また、昨年度の障がい理解促進研修・啓発事業では、障害者への合理的配慮についてや精神障害者の方が地域で安心して暮らせるまちづくりについての講演会を実施し、障害への理解を促す周知啓発を行っております。
今後は、今回御紹介をいただきました宮城県立古川支援学校PTAの皆様の取組のような障害からくる様々な行動について、市ホームページにおいて周知啓発を行うほか、障がい理解促進・啓発事業の中で具体的に市民の皆様にお伝えすることができるよう、障害者団体や関係機関と連携し取り組んでまいります。
○議長(小野辰夫) 伊藤義男議員。
○2番(伊藤義男)(登壇) 心配をすることなく、障害者が自分たちで楽しく過ごせる新居浜市になることを期待し、障害者への理解促進、周知啓発を要望して、次の質問に移ります。
次に、障がい者の市政参加についてです。
障害者の共生社会を実現するためには、障害者自らの意見を聞き、市政に反映していくことが重要です。市では、定期的な意見交換会は開催されていますが、市長や議員、部長級の方を交えた意見交換会は行われていないように思います。
そこで、お伺いします。
年に1回でいいので、障害を持つ方と市長、理事者を交えた意見交換会を開催していただけないか、お聞きいたします。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。久枝福祉部長。
○福祉部長(久枝庄三)(登壇) 障がい者の市政参加についてお答えいたします。
本市では、これまで障害のある方からの御意見や御要望は、新居浜市心身障害者(児)団体連合会の定例会や福祉のつどいなど障害のある方が参加されるイベント等の場においてお伺いしてまいりました。
また、昨年、第7期障がい福祉計画及び第3期障がい児福祉計画を策定した際には、障害のある方や関係団体、事業所等へのアンケート調査を実施し、お悩みや困り事などをお伺いいたしました。
障害のある方からの御意見を直接お伺いし、市政に反映する場として、地域の障害福祉に関する関係者で構成されました新居浜市障がい者自立支援協議会がございますが、市長や議員の皆様、部長級の職員を交えた意見交換会につきましては、関係団体の皆様の御意見も伺いながら、開催の必要性を検討してまいります。
○議長(小野辰夫) 再質問はありませんか。伊藤義男議員。
○2番(伊藤義男)(登壇) 先ほど古川市長から、対話の市政運営という言葉が聞かれましたが、この件を市長はどうお考えでしょうか、お答えください。
○議長(小野辰夫) 答弁を求めます。古川市長。
○市長(古川拓哉)(登壇) 再質問にお答えいたします。
先ほどお答えしましたとおりではありますが、これからも前向きに検討していきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(小野辰夫) 再質問はありませんか。伊藤義男議員。
○2番(伊藤義男)(登壇) ありがとうございます。障害者の積極的な市政参加は、誰にも優しいまちづくりの基本になると思います。ぜひ実際に生の声を聞いて、市政に反映していただきたいです。そのために、毎年1回の市長や理事者を交えた意見交換会の実施を要望し、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○議長(小野辰夫) 以上で本日の一般質問並びに質疑は終わりました。
これをもって本日の日程は全部終了いたしました。
明11日は午前10時から会議を開きます。
本日はこれにて散会いたします。
午後 3時10分散会