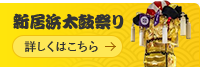サイト内検索
本文
学校・保育園などでケガをした場合
令和6年4月診療分より、学校や保育園などでのケガなどの治療(お薬代を含む)で、「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」の対象となるものは、子ども医療費助成の対象となりません。

医療費の支払いは、子ども医療費助成受給資格証を使用せずに自己負担分を支払い、学校や保育園などを通じて災害共済給付の申請を行ってください。※ひとり親・重度心身障がい者医療費助成の対象となっている方も同様です。
子ども医療費の助成について
子どもの医療費のうち、保険診療における一部負担金を以下のとおり助成します。
※ただし、医療保険適用外の費用(予防接種、健康診査、診断書料、差額ベッド代、食事代、大きな病院での初診等にかかる選定療養費 など)は対象外となります。全額自己負担です。
1 対象となる方
(1)新居浜市に保護者および子どもの住民票があること。
(2)国民健康保険やその他の健康保険に加入していること。
※保護者が市外在住で、子どものみが単身で新居浜市在住の場合は、助成対象外となります。
※保護者が市内在住で、子どもが就学のために市外在住の場合(例:市外の中学・高校へ就学のため、子どもの住民票を市外に移している)、申請により助成対象となる可能性があります。詳しい要件や必要書類、申請手続きについては、お問い合わせください。
2 対象年齢
18歳到達後、最初の3月31日までの間にある方
※令和3年10月診療分から対象年齢を拡大しました(令和3年9月30日までは中学校卒業までが対象)。
※学生に限らず、就労・婚姻している方も助成対象となります。
※小学生以上で、ひとり親家庭医療費助成または重度心身障害者医療費助成を受給中の子どもは、それらの助成が優先して適用されます。
3 助成の範囲
外来・入院すべての診療科にかかる医療費のうち、保険診療における自己負担分全額
4 助成の手続きについて
助成を受けるには、受給者証が必要です。
出生や転入の際は、子どもの保険情報が確認できるもの(健康保険証、資格確認書等)をお持ちになり、市役所1階のこども未来課(16番窓口)にお越しください。受給者証を発行します。
※マイナ保険証の利用登録がお済の方はマイナポータル等で保険情報の確認が可能です。マイナポータルでの確認の場合は、ログインするために、マイナンバーカードが必要となりますのでご持参ください。
5 助成の方法
(1)愛媛県内での受診
医療機関窓口にて、子どもの保険が確認できるもの(健康保険証、資格確認書等)を提示してください。保険診療であればその場で助成が適用されますので、窓口にて自己負担分をお支払いしていただく必要はありません。
※マイナ保険証の利用登録がお済の方はマイナポータル等で保険情報の確認が可能です。マイナポータルでの確認の場合は、ログインするために、マイナンバーカードが必要となりますのでご持参ください。
(2)愛媛県外での受診
県外では受給者証はお使いできませんので、医療機関でいったん自己負担分をお支払いいただいた後、こども未来課に払い戻しの請求を行ってください。払い戻しの請求に必要なものは、次のとおりです。医療機関の受診日の翌日から2年以内に払い戻しの請求を行ってください。10割の医療費をお支払いになられた場合は、ご加入の保険組合によっては7割分の医療費の払い戻し請求に期限が設けられています。保険組合からの払い戻し請求が不可能となってしまった場合には、3割分の払い戻し請求も受け付けられませんのでご注意ください。
1 領収書(患者氏名、領収金額、診療報酬点数、診療年月日、病院名等の記載があること)、または市役所にある「子ども医療費助成金請求書」に医療機関の証明を受けたもの(原本)
2 受給資格者(保護者)名義の通帳(ただし、児童手当に登録のある口座への払い戻しであれば必要ありません)
3 子どもの保険情報が確認できるもの(健康保険証、資格確認書等)
4 子ども医療費助成受給資格証
5 高額療養費支給決定通知書など(保険組合から高額療養費や付加給付金などの支給がある場合)
※保険組合から高額療養費や付加給付金の支給がある場合、その支給分を控除した金額を払い戻します。
※原則、毎月20日までの受付分を、翌月10日に振込みいたします(祝日等の都合により、予定が変更になる場合があります)。
※マイナ保険証の利用登録がお済の方はマイナポータル等で保険情報の確認が可能です。マイナポータルでの確認の場合は、ログインするために、マイナンバーカードが必要となりますのでご持参ください。
(3)補装具等の代金
自己負担後、以下の手順で払戻しの請求ができます。補装具等の作成日の翌日から2年以内に払い戻しの請求を行ってください。ご加入の保険組合によっては7割分の補装具等の費用の払い戻し請求に期限が設けられています。保険組合からの払い戻し請求が不可能となってしまった場合には、3割分の払い戻し請求も受け付けられませんのでご注意ください。
1 医師の指示に従い、補装具等を購入してください(医師の意見書が必要です)。
2 ご加入の保険組合にて、保険適用分(7割もしくは8割)の払戻しを受けてください。
3 1~2の完了後、上記の払戻し請求に必要なもの、医師の意見書、保険組合の支給決定通知書を揃えて、こども未来課に残りの自己負担分(3割もしくは2割)の払戻し請求をしてください。
※必ず先に保険組合から払戻しを受けてください。2が完了していない場合、こども未来課へ払戻し請求はできません。
※保険組合へ領収書等の原本を提出する場合、こども未来課への提出は写しで構いません。保険組合へ払戻し請求する際は、事前に領収書等の写しをとっておくことをお勧めします。
6 注意事項
(1)住所、氏名または、保険情報等に変更があった時は、変更届の提出が必要です。届出の際は、受給者証、子どもの保険情報が確認できるもの(健康保険証、資格確認書等)をお持ちください。
(2)小・中学生で、新居浜市医師会内科・小児科急患センターで受診された場合は、愛媛県外の医療機関で受診する場合と同様の取扱いとなりますので、いったん自己負担分をお支払いいただいた後、こども未来課に払い戻しの請求を行ってください。
(3)交通事故などの第三者行為による傷病で受給者証を使用する場合は、こども未来課に届出が必要です。
(4)市外へ転出される場合は、受給資格がなくなりますので、受給者証をこども未来課まで返却してください。ただし、就学のため子どものみ学校等所在地である市外へ住所を移す場合は、申請いただくことで引き続き助成対象となる場合がありますので、詳しくはこども未来課までお問い合わせください。
※マイナ保険証の利用登録がお済の方はマイナポータル等で保険情報の確認が可能です。マイナポータルでの確認の場合は、ログインするために、マイナンバーカードが必要となりますのでご持参ください。
限度額適用認定証・高額療養費について
- (マイナ保険証をお持ちでない方、オンライン資格確認を導入していない医療機関等を受診される方)
入院や手術などで医療費が高額になる場合は、限度額適用認定証を使用してください。
子ども医療費受給者に係る医療費は新居浜市が負担しています。限度額適用認定証を使用することで、市が負担する医療費を自己負担限度額にとどめることができます。限度額適用認定証はご加入の保険組合にて発行されますので、事前に交付を受けて医療機関窓口にて提示してください。
なお、医療費が高額になった場合の高額療養費は、市が保険組合へ申請し受領することになります。高額療養費が発生した場合、市が負担した高額療養費が保険組合から市へ支給されるよう書類をご提出いただく必要があります。社会保険にご加入の方で高額療養費に該当する可能性がある場合は、高額療養費支給申請書を送付しますので必要事項を記入のうえご提出ください。
- (マイナ保険証をお持ちでない方)
医療機関等(※)の窓口でマイナ保険証を提出し、「限度額情報の表示」に同意することで、自己負担分の医療費を限度額内にとどめることができます。この場合、事前の限度額適用認定証の申請は不要です。
適正な受診のお願い
医療費助成制度は、医療機関や市民のみなさまのご理解とご協力によって支えられています。これからも安心して必要な時に医療を受けられるように、医療機関の適正な受診をお願いします。
かかりつけ医を受診しましょう
かかりつけ医を決めることで、病状や病歴、体質などを踏まえた診療などを受けることができます。気になることは、かかりつけ医に相談し、必要に応じて紹介状等により他の医療機関を受診してください。
紹介状をお持ちでない方が大きな病院を受診した場合、特別初診料(選定療養費)がかかります。これは、診療費(3割負担等)とは別で、特別にかかる料金であるため、全額自己負担となります。子ども医療費では助成されませんのでご注意ください。
できるだけ診療時間内に受診しましょう
急患センターは医療機関の当番体制で支えられています。本当に必要とする人が安心して救急医療を受けられるよう、診療時間内にかかりつけ医に受診するよう心がけましょう。
夜間・休日の救急外来において、緊急性の低い患者さんが時間外に受診された場合、時間外選定療養費を請求される場合があります。選定療養費は、子ども医療費では助成されませんのでご注意ください。また、夜間・休日に受診すると、診療時間内に受診するよりも初診料などが高くなります。
安易な重複受診は控えましょう
同じ病気で複数の医療機関を受診すると、医療機関を変えるたびに初診料等がかかるため、医療費増加の一因となります。気になることは、できるだけかかりつけ医に相談しましょう。
ジェネリック医薬品の利用について
新薬と同等の効き目や安全性で価格の安いジェネリック医薬品を利用することで、医療費の軽減につながります。ご利用をお願いします。
愛媛県子ども医療電話相談「#8000」をご利用ください
#8000とは
夜間に突然、お子さんの身体の具合が悪くなった時「どうしよう…」と困ったことはないですか。
看護師や医師などが家庭での応急対処の方法などについてアドバイスをします。お困りの時には、ぜひご利用ください。
- 短縮ダイヤル: #8000
※相談無料、県内通話料がかかります
- ダイヤル回線: 089-913-2777
- 利用できる時間帯
平日 19時~翌朝8時
土曜日 13時~翌朝8時
日曜日・祝日 8時~翌朝8時
愛媛県子ども医療電話相談「#8000」ご利用にあたっての注意事項
- 電話による限られた情報に基づく相談であり、直接、子どもの状態を診て行う診断・治療ではありません。あくまでも相談される方のご判断の参考としていただくためのものです。
- 医療機関の紹介を受けた場合は、必ず電話をかけてから受診するようにしてください。
- 電話中の場合は、しばらく時間をおいて、あらためてかけ直してください。
- 通話料については、県内通話料金をご負担いただきます。
救急医療は、夜間などに急病やケガですぐ治療が必要な患者さんのために整備されたものです。本当に救急医療が必要な患者さんのために、次のことを守りましょう。
- 昼間に起こった症状は、その日の診察時間内にかかりつけ医に診てもらいましょう。
- 翌日まで待てそうな軽い症状の時は、翌日、かかりつけ医を受診しましょう。
詳細については、下記(愛媛県ホームページ)でご確認ください。https://www.pref.ehime.jp/page/4362.html<外部リンク>