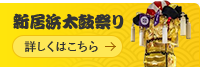サイト内検索
本文
電動車いす(シニアカー)は“歩行者”です!
しかしながら、死亡事故など重大な事故も発生しており、安全に利用するには、利用者はもとより市民のみなさまにシニアカーのルールを理解していただくことが非常に重要です。
利用される方へ
電動車いす(シニアカー)が通行できる場所
歩道のある道路では、必ず歩道を通行しましょう。
歩道のある場所では、必ず歩道を通行してください。歩道を通行する際には、歩行者や自転車に注意し、ゆずり合って通行しましょう。
歩道がない道路では、右側を通行しましょう。
歩道のない道路では、道路の右側(路側帯)を通行してください。通行する際には、歩行者や自転車だけでなく自動車にも注意しましょう。
道路の中央を通行してはいけません。
道路の中央寄りを通行すると、大変危険です。必ず歩道や路側帯、道路の右側を通行してください。

道路標識を守りましょう
歩行者等専用

歩行者専用道路であることを示す標識です。電動車いすは歩行者として取り扱われるため、この標識がある道路を通行できます。
横断歩道

電動車いすは、横断歩道を通行することができます。
特定小型原動機付自転車・自転車専用

電動車いすは歩行者として取り扱われるため、通行できません。
歩行者等横断禁止

歩行者は横断できないことを示す標識です。歩行者として取り扱われる電動車いすは、通行できません。
自動車を運転される方へ
電動車いすの事故で最も多いのが、道路横断中の事故です。自動車を運転される方は、安全確認を徹底し、電動車いす利用者を思いやる運転を心がけましょう。
横断歩道
横断歩道を渡ろうとしている電動車いすは、歩行者と同じです。電動車いすが横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして電動車いすに道を譲らなければなりません。
歩道のない道路
電動車いすは、歩行者と同じ右側通行です。歩道や車道の区別がない道路を走行するときは、電動車いすとの間に安全な間隔をあけなければいけません。また、それが無理な場合は徐行しなければいけません。不意に横断を始めることも考えられますので、電動車いす利用者の安全が図られるよう、十分な間隔をあけておきましょう。
電動車いすの保険(補償)について
保険の種類
電動車いす(シニアカー)の利用にあたって、保険に加入する義務はありません。しかし、万が一に備えて保険に加入しておくことで、電動車いす(シニアカー)の運転中に事故があった場合には保険が適用されます。保険は以下の二種類があります。
相手方に対する賠償
電動車いす(シニアカー)を運転していて、相手にけがを負わせたり、物を壊した場合に適用されます。
本人の補償
電動車いす(シニアカー)を運転していて、ご自身が負傷したり、電動車いす(シニアカー)が壊れた場合に適用されます。
保険の加入方法
電動車いす(シニアカー)は歩行者と同じ扱いとなるため、基本的には個人賠償責任保険となります。すでに契約済みの火災保険などに特約付加(日常生活賠償補償)があれば、新規に保険加入の必要がない場合もあります。
現在入っておられる保険会社や電動車いす(シニアカー)の販売店などにご相談ください。
関連リンク
警察庁のホームページから「電動車いすの安全利用の手引き」がダウンロードできます。
警察庁「電動車いすの安全利用について」<外部リンク>
(一社)愛媛県交通安全協会が主体となり、平成26年1月1日から、「電動車いす安全登録制度」が設けられています。この制度は、電動車いす利用者に対する交通事故防止広報や安全運転講習の充実を図り、併せて、電動車いすの盗難・遺失防止及び早期発見・返還に資することとしたものです。
愛媛県交通安全協会「電動車いす安全登録制度について」<外部リンク>