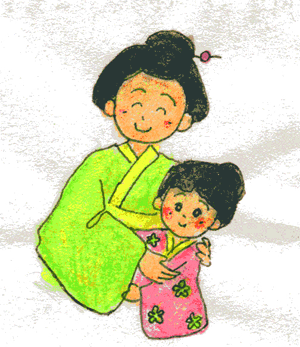 新居浜市の大島に、喜衛門という漁師がいた。
妻はお菊といって、やさしい女であった。
2人の間にはお雪というかわいい1人娘があり、家族3人は幸せにくらしていた。
ところが、お雪が5つの時、喜衛門に好きな女の人ができた。喜衛門が、その女を新しく妻にしようとしたため、今まで幸せだったかぞくは、たちまち不幸になってしまった。 お菊は驚き悲しんで、喜衛門に何度も思い直してくれるように頼んだが、すっかり心変わりをした喜衛門には通じなかった。お菊は、とうとういとしいお雪を残したまま里へ帰ってしまった。
喜衛門の妻になった女は心の冷たい、ひどい女であった。
まま母は、お雪に何かとつらくあたり、食事もじゅうぶんにあたえなかった。
そのうえ、自分の仕事まで小さいお雪にさせて、お雪がよくできなかったり、失敗したりすると、ひどくぶっていじめた。喜衛門も女のいいなりになって、お雪をしかるようになっていた。まま母にいじめられるのはがまんできても、父親にかばってもらえないのが、お雪にとって何よりつらいことであった。だから、しかられるたびに母親のお菊のもとへ行っては、泣き泣きつらさを訴えていた。お菊は、わが子の話を聞きながら、自分がいじめられ、傷つけられてでもいるように心を痛め、お雪といっしょになげき悲しんだ。
こんな事がたび重なるにつれて、お菊は、お雪のことを心配するあまり、とうとう気が狂ってしまい、喜衛門と女をたいそううらみながら死んでしまった。
まま母は、悲しみにうちしおれているお雪をいじめ続けた。
「かあちゃんは、なんでわたしを残して死んでしまったのだろう。かあちゃんに会いたい。死んでかあちゃんの所へ行きたい。」
ある晩、お雪は、母の墓で歩いて行って、そこで思いっきり、泣き明かした。これがいつしか習慣のようになって、お雪は月夜でも闇夜でも、毎晩こわさを忘れて母の墓へ通うようになった。そして、生きている人にものをいうように、母のお墓に泣きながら悲しみを訴えるのだった。
そんなある夜のことである。その夜も、お雪が、まま母にひどくぶたれ、母のお墓の前で泣いていると、ふと目の前が、ぼっと青白く明るくなった。墓のうしろから、あのなつかしい母親が現れたのである。お雪は息がつまるほどおどろいたが、思わずこの世の人でない母の胸にとびついて行った。お菊も、わが子をしっかりとだきしめた。
「ああ、かわいそうなお雪。かあちゃんは、おまえがいつかは、いじめ殺されてしまうのではないかと思うと、心配で成仏できないんだよ。」
お菊はそういってお雪をいとおしそうにいっそう強くだきしめた。
「だから、少しでも早く、この寺の尼さんになり、仏様のお力におすがりして、かあちゃんが安心して仏様になれるようにとむらっておくれ。そして、おまえのようなかわいそうな子供を救っておあげ。それから、もう今夜かぎり、お墓へ泣きにくるのはおよしなさい。その代わり、かたみとしてこの着物の片そでをあげるから、かあちゃんと思ってたいせつにしておくれ。」
2人はしばらくかたくだき合ったまま、別れをおしんだ。ゆうれいのお菊は自分の着物の片そでをぴりぴりと引きちぎってお雪にわたすと、かき消すように消えてしまった。
しばらくの間ぼんやりしていたお雪は、はっとわれにかえると、母にいわれたとおり尼になるため、すぐにその足で寺にかけこんだ。尼になったお雪は、いっしんに仏に仕え、母の霊をなぐさめた。そしてまた、不幸な子どもたちの世話をよくし、困っている人たちを助けた。やがて、お雪は、島の人たちから仏様のようにうやまわれながら73歳でなくなった。お雪が母からもらったかたみの片そでは、今も大島の願行寺に「ゆうれいの片そで」と呼ばれて、たいせつに残されている。
愛媛のむかし話(坂上頼正の文) | 

